EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

情報センサー2019年4月号 Digital Audit
Digital Audit推進部 公認会計士 加藤 信彦
製造業や小売業の会計監査に従事した後、現在は金融機関における会計監査、アドバイザリー業務に従事。2016年11月にアシュアランス・イノベーション・ラボ統括責任者、17年11月に監査統括本部 Digital Audit推進部 部長に就任。主な著書(共著)は『Q&A コーポレートガバナンス・コードとスチュワードシップ・コード』(第一法規)。公認会計士、米ニューハンプシャー州公認会計士。
Ⅰ はじめに
202X年、二つの監査用人工知能(AI)が財務諸表を監視している。不正会計予測モデルを搭載したアナリティクスツール(EY Dolphin)が決算短信・有価証券報告書などの開示書類やアナリストレポート・ニュース・SNSなどをリアルタイムに分析し、過去不正のあった財務諸表と同じような財務指標(棚卸資産回転率や売上債権回転率など)の異常な動きや定量化された非財務情報から抽出されたビジネスリスクについて検出された都度、担当する監査チームのスマートフォンにアラート通知が自動で配信される。一方で、世界中にビジネスを展開する監査先企業の連結財務諸表を構成する国内外拠点の総勘定元帳や補助元帳のほか、契約書、取締役会議事録などビジネス文書をデジタル化したデータベースに会計仕訳異常検知アルゴリズムを搭載したアナリティクスツール(EY Helix GLAD)が接続され、会計仕訳やその裏付けとなる取引の監査証拠を分析し、過去の同企業の取引パターンから外れる異常な取引がないか、過去不正があった企業と類似のパターンの取引がないかリアルタイムに監視し、異常な取引があれば、担当する監査チームのスマートフォンにアラート通知が自動で配信される。ビジネスを深く理解する監査チームメンバーは、このようなマクロとミクロのアプローチでAIが抽出した異常な財務指標の動きや取引、潜在的なビジネスリスクを専門家として分析・評価し、リスクを識別した場合には監査先企業に早期に伝達していく。
当法人では、このような2020年代に到来すると予想される未来の監査の姿(<図1>参照)をイメージ動画にして内外に伝えていますが、前述したAI機械学習を組み込んだアナリティクスツール(EY DolphinとEY Helix GLAD)は日本ですでに開発し、一部の監査業務に導入しています。会計仕訳異常検知アルゴリズムについては18年に日本で特許も取得しており、提携する海外のEYでも正式なツールとして利用してもらうべく、海外の監査先企業の会計仕訳データに対してパイロットテストを実施しているところです。ただし、未来の監査の実現には幾つかの課題があるため、Digital Auditの現状と未来の監査に向けた課題を整理して、今後の対応につなげていきたいと考えています。

Ⅱ Digital Auditの現状
1. デジタル活用とEY Canvas
監査先企業から集めた監査証拠や監査人が作成した監査調書は監査プラットフォームと呼ばれる監査調書保管システムに保存されているのが一般的ですが、EYではこの全世界共通の監査プラットフォーム(EY Canvas)を世界中全ての監査業務で利用するとともにメールの代わりのコミュニケーションツールとしても活用しています。具体的には監査先企業とウェブ上のEY Canvasで資料のやりとりをすることが可能であるため、効率的な資料授受に貢献しています。また親会社の監査チームが日本にいながらEY Canvasで海外子会社の監査チームと必要な資料のやりとりをしたり、グループ監査のスコープ外の海外拠点も含めた法定監査の進捗(しんちょく)状況も確認できるため、海外子会社の管理強化に貢献することが可能です。
2. アナリティクスとEY Helix
最近では総勘定元帳や補助元帳などの財務情報はデータで取得できるケースが多いため、当法人では売上など主要なビジネスサイクルを分析するための、全世界共通のデータ・アナリティクスツール(EY Helix)を活用し、財務諸表に潜む異常な取引の特定に効果を発揮しています。例えば売上の監査手続においては、売上から入金に至るまでの勘定科目間の相関関係の理解・評価に入金テストを組み合わせることで母集団全体を精査的に検証することが可能となります。一定の条件はありますが、売上の原始証憑(しょうひょう)(契約書や納品書・受領書など)の代わりに対応する入金を確認することで監査手続を代替させることができれば、監査先企業の担当者が過去の原始証憑を探す手間がなくなり、監査対応負荷の軽減に貢献できる可能性があります。今後はこのEY Helixを利用した監査手続が全世界のEYの監査手法(メソドロジー)の中心になることが予定されており、監査人および監査先企業双方の生産性向上に貢献することが期待されています。また、当法人では監査先企業から入手するデータの加工やEY Helixへの投入にRPAなどの自動化ツールを導入しているほか、EY Helixに投入されたデータを利用して一部の監査調書を自動的に作成する取り組みを行っており、作業が中心の定型的な監査業務から判断を伴う専門的な監査業務へ監査時間のシフトを進めています。
3. 監査業務の生産性向上
このほか、監査業務の生産性向上の取り組みには棚卸立会時のドローンと3D解析技術の導入があります。特に屋外に野積みされている鉄鉱石など原材料の体積を正確に測量することは難しく、専門的な測量技術を用いても数日要していましたが、当法人と監査先企業にて共同した実証実験では、ドローンに搭載したカメラで原材料を上空から写真撮影し、その後撮影した写真を3D解析して体積を計算するまで数時間で実施することができました。今後はドローンを活用した具体的な棚卸立会手法や監査手続を確立するとともに、多くの監査業務へ適用するためのスケーラビリティを検討した上で2020年度中の監査での実現を目指しています。
4. 最先端技術の活用
当法人では監査手続の効率化を進める一方で、冒頭に記載したようなAI監査ツールを実用化して不正検知力の向上やビジネスリスクの変化の把握に役立たせています。EY Helixは異常な取引を経験豊富な監査人が選ぶのに対して、EY Helix GLADは総勘定元帳(General Ledger)の異常検知(Anomaly Detector)を監査人に代わってバイアスのかからないAIが行いますが、両者を併用して行うことで異常な取引の抽出に漏れがないようにすることが可能です。また、ブロックチェーン技術で構築されたデータベースが将来的な財務・非財務情報を他社と共有する基盤となり得ることも踏まえ、グローバルベースで監査業務への対応を検討しています。例えば仮想通貨交換所の監査では、ビットコインなど一部の仮想通貨の取引データをパブリック型ブロックチェーンから抽出して分析するEY Blockchain Analyzerを開発し、日本でも導入を進めています。このような先行事例での導入を踏まえ、未来の監査に備えています。
5. クライアント体験
監査業務のデジタルトランスフォーメーション(DX)を進める前に監査先企業のDXを理解した上で、監査対応を図る必要があります。監査先企業のビジネスモデルはデジタル技術によって大きく変革しており、収益の源泉だけでなくオペレーションやビジネスプロセスも変化していますので、監査手続として実施するリスクの識別・評価やリスク対応手続を環境変化に合わせる必要があります。
EYでは、パリやニューヨークなど全世界の主要拠点に最新鋭のデジタルテクノロジーを備えたイノベーションセンターであるEY wavespaceを設置しています。当法人では、EYのグローバルネットワークともダイレクトにつなぐことが可能なEY wavespace Tokyoを日比谷の新オフィスに設置してDigital Auditの取り組みを紹介するだけでなく、監査先企業のDXの理解と監査対応のための協議をすでに始めています。監査品質を担保しながら、監査の付加価値を向上させ、監査先企業の監査対応負荷を軽減させるには双方のDXを最大限活用していくことが不可欠であるため、EY wavespaceのような非日常的な空間で将来に向けた協議を進めていくことが有用と考えています。
6. 人材育成
未来の監査を実現するためには、監査業務のDXのほか、デジタル人材の育成も重要となります。EYでは、デジタルリテラシーを高めるワークショップや研修を行うとともに、全世界共通のEY Badges(デジタル時代を見据えた社内資格制度)を導入しています。アナリティクス、AI、デザイン思考、セクターナレッジなどを英語によるオンライン研修、関連する業務経験、法人への貢献を考慮し、四つのレベル(ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ)のデジタルバッジを付与するものです。導入から1年が経過し、EY Japan全体で30人以上がバッジを保有しています。今後はバッジ保有者のネットワークを強化するとともに、当法人の在るべき姿であるグローバルとデジタルに強い人材を継続的に育成する必要があります。
Ⅲ 未来の監査に向けた課題への対応 -会計監査のエコシステムとデータ活用
1. 財務情報の標準化と集中化
未来の監査を実現するには、会計監査のエコシステム(<図2>参照)全体で対応しなければならない課題が幾つかあります。財務情報のデータソースである会計システムや販売・購買システムは監査先企業ごとに異なる上、連結財務諸表を構成する同じグループ会社でも必ずしも同じシステムを導入しているとは限りません。欧米の企業は、M&Aで取得した企業にまずは自社のERPシステムを導入することで経営情報を一元化し、必要に応じて現地の規制や財務報告制度に合わせて外部報告時に組み替えることが多いのに対して、日本企業は現地の規制や制度にあった既存のシステムを利用して外部報告し、親会社への内部報告時に連結パッケージとして組み替えることが多いといわれています。
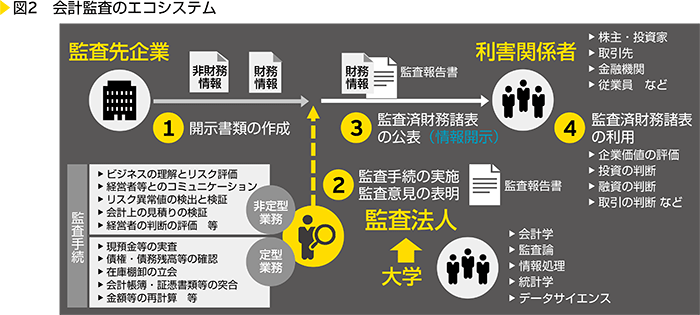
また日本企業は自社のビジネスプロセスに合わせERPシステムをアドオンして導入するのに対して、欧米企業は標準的なERPシステムに合わせビジネスプロセスを変更する傾向にあるようです。
このようなシステム環境の相違もあるため、日本の監査実務では財務データをデータ・アナリティクスツールに投入するためのデータ加工に時間がかかるケースが多いですが、欧米の監査実務ではデータ加工にそれほど時間がかからないといわれています。最近では、システム変更時に標準的なERPシステムに合わせて自社のビジネスプロセスを変更する日本企業も増えていますが、大幅なシステム変更をしなくても、海外拠点を含め、連結財務諸表を構成するグループレベルで必要な財務・非財務情報データだけをデータウェアハウスに保存する方法が一つの選択肢になり得ると考えられています。
グループレベルで財務データが標準化された上でデータベース上に集中管理されるようになれば、経営判断に資する財務情報のリアルタイムな活用だけでなく、会計監査の進め方も大きく変革することが想定されます。特に、現状ではグループ監査における国内外拠点の法定監査結果の利用や連結パッケージの財務分析など財務諸表レベルでの検証が中心であるのに対して、連結財務諸表を構成する全ての総勘定元帳や補助元帳などをあらかじめ異常検知した上で、子会社の監査では異常検知された取引の検証に注力を注ぐことが可能です(<図3>参照)。
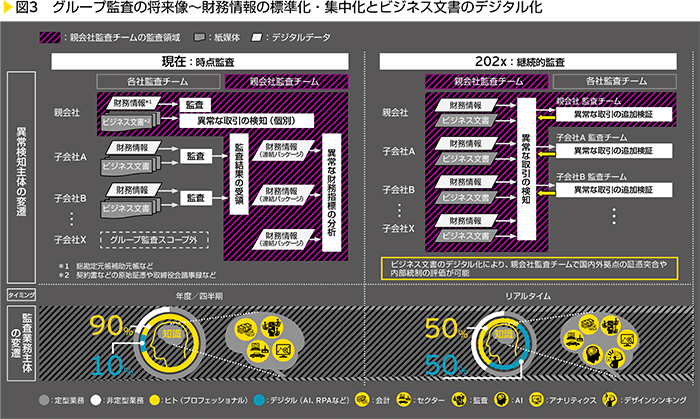
2. ビジネス文書のデジタル化とプロセスマイニング技術の応用による内部統制の評価
財務情報に記録された取引の裏付けである契約書、受領書などの原始証憑や企業の意思決定の根拠となる取締役会議事録、稟議(りんぎ)書などビジネス文書のデジタル化は日本ではe-文書法に規定される要件を満たせば可能となり、徐々に実務に浸透しています。現場ではペーパーレス化が進み、さらにテキストデータのまま保存されることが想定されますが、タイムスタンプや電子署名などを利用して改ざん防止の仕組みが必要不可欠となります。このようなビジネス文書のデジタル化が進めば、AIを活用したテキスト分析を行い会計上や監査上の判断を支援することも可能です。EYではリース契約などの紙の契約書をOCRで読み込み、テキスト情報にした上で、リース期間や契約書の署名者など会計上の判断に必要な情報をAIが自動的に抽出して、監査上の検証に役立てる取り組みを行っています。まもなく英語版の契約書テキスト分析ツールが監査現場で活用できるようになりますが、ビジネス文書のデジタル化により紙の契約書からテキスト情報にする必要がなくなりますので、テキスト分析の精度が飛躍的に向上します。
このようなビジネス文書のデジタル化に加え、請求書の受領や承認などのイベントログがERPシステムからデータとして抽出できれば、ビジネスプロセスのフローを可視化したり、異常なフローを抽出するプロセスマイニング技術(本誌19年2月号 参照)も監査で活用できるため、内部統制の自動化に加え、整備運用状況の評価に効果を発揮します。
3. 非財務情報のテキスト分析によるリスクの識別と評価
18年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードに「上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである」と明記されるとともに、18年11月に金融庁から公表された「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案(19年1月公布)や同年12月に公表された「記述情報の開示に関する原則(案)」でも非財務情報の開示拡充が求められています。以前から非財務情報の開示が充実している米国では、このような非財務情報の開示書類をテキスト分析することで、ビジネスリスクや不正会計を見抜く学術研究が行われていますが、日本でも日本語の自然言語処理技術を応用させながら、監査上のリスクの識別・評価に活用することが可能となりつつあります。また最近では開示書類に記載されている非財務情報だけでなく、アナリストレポート、ニュース、SNSなども学術研究の対象となっており、当法人でも公開されている膨大な非財務情報から監査先企業に関連する情報を特定し定量化することでビジネスリスクの識別・評価に役立たせる研究を行っています。
4. 産学が連携したデジタル人材の育成
財務・非財務情報のデータ活用と高度なデータ分析技術を駆使できる環境整備に加え、会計監査を担う人材のデジタルリテラシーを向上させることが必要不可欠となります。未来の監査チームには公認会計士、不正対応やIT専門家以外にも監査先企業から効率的にデータを取得するためのIT環境を構築するコンピューターエンジニア、入手したデータ処理の専門家であるデータキャプチャースペシャリスト、入手したデータの分析やアルゴリズム・モデルを構築するデータサイエンティストなどさまざまな専門家が関与することになります。これからの監査人は会計監査の専門的知見をもとに監査先企業のビジネスを深く理解するとともに、さまざまな専門家と協業(コラボレーション)しながら専門家の能力を生かして監査先企業と協議(ファシリテーション)し、監査先企業のDXの理解と監査対応(イノベーション)を推し進めていく必要があります。
当法人に入所後は、前述したEY Badgesを取得したり、EY Gradlabと呼ばれるSTEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics)人材育成の短期間の特別プログラムに参加したりしながら、監査実務の中でデジタルを学んでいくことになります。また、最近では大学からの依頼を受け、会計学や監査論の授業において未来の監査に直結する講義を行うことが多くなってきています。
例えば監査論の講義の中で、プロフェッショナルとして若いうちから貴重な経験が積める公認会計士の仕事の魅力やグローバル展開する企業の監査業務を紹介したり、冒頭紹介した未来の監査のイメージ動画を上映し、AIと会計士が共存して監査業務を行う姿を紹介することで、AIが会計士の仕事を奪うという誤ったイメージを払拭する取り組みを行っています。また米国の会計学の講義では、EYで使用しているアナリティクスツールを学生向けにカスタマイズするとともに、不正や誤謬(ごびゅう)の仕訳を含むダミー企業の総勘定元帳データとセットで提供し、アナリティクスツールで企業の不正や誤謬が発見できるかをグループで競わせたりするなど、より監査実務に近い形で講義を行っています。
Ⅳ 未来の監査の姿
1. AIなどデジタル技術との共存による不正根絶社会
このような課題を乗り越えた先にある未来の監査の価値とは、リアルタイムに財務・非財務情報から異常検知を行う継続的監査(本誌19年3月号 参照)によりAIをはじめとしたデジタル技術とプロフェッショナルが共存してリスクをいち早く発見し、監査先企業とコミュニケーションしていくことにありますが、最終的な目標は会計不正を根絶する会計監査のエコシステムを継続的に構築していくことにあります。例えば、改ざんできないといわれているブロックチェーン技術ですが、量子コンピュータの登場で暗号技術が解読される懸念がある一方で、米国では耐量子コンピュータ暗号を公開鍵に利用する研究を進めているようです。このような会計監査のエコシステムの安定化に利用できるデジタル技術の進展に注視しながら、EYではグローバルベースで監査実務への活用可能性に関する研究開発を進めています。
2. リアルタイム監査による働き方改革と監査報酬モデルの変化
未来の監査では、財務・非財務情報をリアルタイムに監視することになるので、開示書類の検証は開示の頻度によりますが、取引の検証については、これまでのような四半期決算のタイミングで行う必要がないため、年間の業務量が平準化する可能性があります。また、監査手法もデータ・アナリティクスが中心となるため、堅牢なセキュリティ環境の下、通常は在宅勤務で監査を行い、監査先企業とのコミュニケーションや現物の確認などで監査先企業に訪問することになると考えられます(<図1>参照)。この結果、われわれ監査人だけでなく、監査先企業の監査対応負荷も軽減することが見込まれるため、双方の働き方改革に貢献することになると考えられています。
また監査業務の担い手も公認会計士や専門家などプロフェッショナルとAIやRPAなどデジタル技術が共存するため(<図2>参照)、単価×時間の監査報酬モデルから、システム構築費用、ソフトウェアライセンス、サーバーなどのテクノロジー費用を加味した監査報酬モデルにシフトしていく必要があると考えられますが、監査報酬モデルの変更につき監査先企業への丁寧な説明が必要不可欠となります。
3. 監査業務の使命と破壊的創造
19年1月24日、有限責任 あずさ監査法人、EY新日本有限責任監査法人、有限責任監査法人トーマツ、PwCあらた有限責任監査法人の4監査法人は、グローバル化・デジタル化する経済社会の未来のために監査法人の使命を踏まえた共同声明を発表しました。共同声明の内容は四つのコミットメントである①財務報告と監査の信頼性向上に向けた取り組み②情報技術への積極的な投資③国際感覚を有する会計やデジタル社会に対応する人材への投資④日本経済の健全な発展への貢献で構成され、特に②情報技術への積極的な投資には「私たちは個別の監査法人を超えて、他の監査法人、監査を受ける企業等、そしてその取引先企業等をも含む新しい枠組みの可能性を探求し、監査の有効性および効率性の向上に努めます」という内容も含まれ、監査の変革に向けた会計監査エコシステムにおける新たな取り組みの可能性が示唆されています。
すでに4監査法人共同で、18年11月30日、会計監査確認センター合同会社を設立し、会計監査における確認手続の共同プラットフォームの開発・提供を通じて、確認状の発送・回収業務から生じる監査人・監査先企業・取引先の事務負担の軽減への貢献を図る取り組みを行っていますが、今後は4法人に限らず他の監査法人が共同プラットフォームを利用することも想定しています。将来的には、監査法人間だけでなく、企業開示の信頼性や有用性を確保するために、資本市場や財務報告のサプライチェーンをとりまく多くのステークホルダーと監査法人の有機的な連携が新たにスタートすることを期待しています。
Ⅴ おわりに
デジタル技術は会計監査をどのように変革させるかをテーマに、監査法人だけでなく監査先企業や監査法人に人材を供給する大学にもどのような利点があるかを可能な限り記述しました。今後も新たなデジタル技術が登場し監査への活用が検討されることになると思いますが、監査法人だけの利点を考えるのではなく、資本市場の信頼性確保のため、会計監査のエコシステム全体が有効に機能するような取り組みを行っていくことが最も重要であると考えています。
参考文献
首藤昭信(2019)「会計学研究の展開と非財務情報の重要性」経営財務No.3392
櫻井通晴(2019)「AIの会計、監査、管理会計への適用」企業会計2019 Vol.71
市原直通(2019)「AIを活用したContinuous Auditing(継続的監査)で不正会計は見抜けるか」本誌19年3月号
原誠(2019)「会計監査におけるプロセスマイニングの活用」本誌19年2月号
市原直通・首藤昭信(2017)「Fintech×監査の現状:AIで見抜く不正会計」企業会計2017 Vol.69
加藤信彦(2017)「監査の品質と付加価値向上に向けたイノベーション-AIやRPAを駆使した未来の監査「Smart Audit」の真価とは-」本誌17年4月号
市原直通(2017)「不正会計はAIで見抜けるか」本誌17年新年号



