EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

情報センサー2020年5月号 押さえておきたい会計・税務・法律
公認会計士 太田達也
当法人のフェローとして、法律・会計・税務などの幅広い分野で助言・指導を行っている。また、豊富な知識・経験および情報力を生かし、各種実務セミナー講師、講演等において活躍している。著書は多数あるが、代表的なものとして『会社法決算書作成ハンドブック』(商事法務)、『「純資産の部」完全解説』『「解散・清算の実務」完全解説』『「固定資産の税務・会計」完全解説』(以上、税務研究会出版局)、『例解 金融商品の会計・税務』(清文社)、『減損会計実務のすべて』(税務経理協会)などがある。
Ⅰ はじめに
昨今、不適切な会計や経理の事例を目にする機会が増えているように思われます。(株)東京商工リサーチの調査によれば、2019年1~12月にこうした不適切会計を開示した上場企業は08年の集計開始以降最多となりました。その内訳は「誤り」が最も多く、「粉飾」がこれに続き、3番目にくるのは「着服横領」とのことです(20年1月24日付同社ウェブサイトより)。
この調査結果にもあるとおり、会社が役員や使用人の横領などの不正行為により損害を被る例は後を絶ちません。このような不正行為が生じた場合、被害者であるはずの会社が、特に税務において非常に不利な取扱いを受けるのが一般的です。
今回は、役員や使用人による横領をめぐる会社の取扱いについて、税務を中心に説明します。
Ⅱ 税務上の取扱い
1. 所得計算上の取扱い
会社の役員や使用人が横領する代表的な方法として、仕入や経費を架空または水増し計上して着服する方法が考えられます。ここでは、外注費として帳簿に記載されていた経費100(+消費税等10)が、後日の調査で、外注の事実はなく発注を担当する使用人が横領していたことが判明したという事例で考えてみましょう。
(1) 基本的な考え方
① 横領損失と損害賠償請求権の認識
当初の会社経理と、横領が判明した際の税務上の修正処理は次のようになります。

Ⓐで外注費として処理した経費は、実際は横領による損失であるため、まずはⒷ外注費から横領損失に振り替える処理が行われます。すなわち、外注費を損金不算入として代わりに横領損失を損金算入します。
次に、Ⓒ横領した使用人に対する損害賠償請求権が発生するため、これを収益として益金算入します。
横領は、それが行われた後の事業年度に発覚することが多く、その場合には、Ⓐの処理が行われた事業年度まで遡ってⒷⒸの処理を行わなければなりません。
この結果、当初の確定申告ではⒶの外注費100だけが所得金額に反映されていたところ、ⒷⒸが加わることによってⒶの外注費分の所得が増加することとなります。
従って、増差所得に対して法人税等の仕入税額控除が認められないことに対して、消費税等のそれぞれ修正が必要となります。
② 損害賠償請求権の計上時期
①の税務上の修正処理は、Ⓐの時点に遡ってⒷⒸが同時に行われる「同時両建」によるのが一般的です。
Ⓑ横領損失については損失の発生した事業年度に認識する一方、Ⓒ損害賠償請求権については具体的に金額が確定した事業年度に計上する、すなわちⒷとⒸを別々の事業年度に計上することが許容される場合もあり得ますが、実際に認められる事例はほとんどないのが現状です。
ところで、法人税基本通達2-1-43では、他の者から支払を受ける損害賠償金については、実際に支払いを受けた日の属する事業年度の益金とすることができることとしています。この取扱いが役員や使用人の横領についても適用できれば別々に認識することも可能になりますが、裁判例では、この通達は役員や使用人に対しては適用されないものとされています。
③ 損害賠償請求権の回収可能性
ⅰ 回収可能性の有無の検討
同時両建説によれば、まずは横領のあった事業年度に損害賠償請求権を認識することになりますが、横領した者は使い込んでしまっていることが多く、それを弁済する能力があるかが問題となります。
例えば、横領者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、法人税基本通達9-6-2により、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができます。
ⅱ 回収可能性がないと認められる場合の貸倒損失の計上時期
<図1>を例にとると、横領の時点で横領者に資力がなく全額回収不能であった場合には、X1期において、Ⓑ外注費を横領損失へ振り替え、Ⓒ損害賠償請求権を認識するとともに、Ⓓその損害賠償請求権が貸倒損失とされる結果、増差所得は生じません。
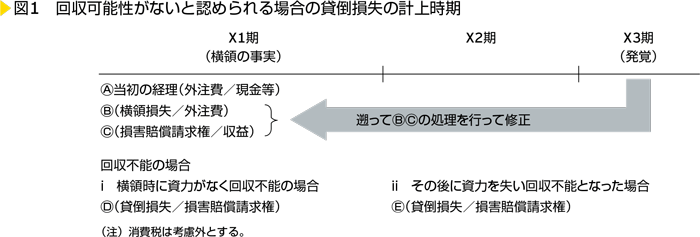
これに対し、横領の時点では資力があり、その後において資力を失い全額回収不能となった場合には、X1期においてはⒷⒸの処理によりいったん増差所得が生じ、その後の全額回収不能となった事業年度にⒺ貸倒損失として損金算入されることとなります。
役員や使用人の横領は後日の税務調査で発覚することも多いのですが、X1期において増差所得(修正申告または更正)が生じないようにするためには、X1期においてすでに資力がなかったと認められる必要があるところ、現実問題としてそれを立証するのは困難です。
(2) 役員の横領の場合
役員の横領の場合には、給与課税が行われることがあります。例えば、オーナー会社の代表取締役が会社の財産を着服したような場合には、被害者(会社)と加害者(代表取締役)が同一であり、横領損失と損害賠償請求権という概念としてではなく、認定賞与として課税される可能性があります。オーナー社長でないいわゆる雇われ社長についても、役員賞与として課税された事例もあります。役員給与と認定された場合、定期同額給与等の要件を満たさないため損金不算入とされる上、源泉徴収義務および不納付加算税が課せられることとなるため、特に注意が必要です。
2. 過少申告加算税・重加算税
(1) 過少申告加算税の適用
役員または使用人による横領が税務調査で発覚し、増差税額が生ずる場合には、原則として、増差税額に対して10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分に対しては15%)の過少申告加算税が課せられます。
(2) 重加算税の適用
(1)の場合において、納税者が課税標準等または税額等の計算の基礎となるべき事実の全部または一部を隠蔽(いんぺい)または仮装し、その隠蔽または仮装に基づき申告していたときは、過少申告加算税に代えて、35%(5年以内に無申告加算税または重加算税が課せられたことがある場合には45%)の重加算税が課せられます。
ここで、納税者の隠蔽または仮装とは、それを行ったのがその法人の代表者本人の場合はもちろん、代表者以外の役員、使用人であっても、その行為が納税者本人(法人)の行為と同視することができる場合には、それを代表者が知らなかったとしても、法人自身が行ったものとして重加算税の対象とされます。
これに対し、職制上の重要な地位を占めていない使用人の横領については、法人の行為と同視することができないものとして、一般的には重加算税の対象とならず、過少申告加算税が課せられます。
(3) 過少申告加算税・重加算税が課せられない場合
過少申告加算税および重加算税は、調査通知前に修正申告する場合には賦課されません。
また、調査通知以後の修正申告であっても、更正があるべきことを予知してされたものでない場合には重加算税は賦課されず、過少申告加算税の税率も軽減されます。
従って、内部通報などを契機として(税務調査とは無関係に)過年度の横領が発覚した場合には、自主的に修正申告書を提出すべきでしょう。
3. その他の課税関係
役員または使用人による横領が税務調査で発覚した場合の課税関係として、青色申告の取消しが考えられます。また、横領が長期間継続していた場合には、更正の期間制限も特例があります。
(1) 青色申告の取消し
法人税法第127条第1項においては、帳簿書類に取引の全部または一部を隠蔽しまたは仮装して記載しまたは記録し、その他その記載または記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があるなどの場合には、税務署長は、その事業年度に遡って青色申告を取り消すことができるものとされています。
すなわち、役員または使用人の横領の場合に、会社の行為と同視され、会社の隠蔽・仮装と認定された場合には、重加算税の賦課とともに、青色申告の取消処分も併せて受ける可能性があるわけです。
(2) 更正の期間制限
更正は、国税通則法第70条第1項において、原則として更正に係る法定申告期限から5年を経過した日以後はすることはできませんが、偽りその他不正の行為によりその全部もしくは一部の税額を免れ、またはその全部もしくは一部の税額の還付を受けた場合の更正は、同条第4項により、7年間することができます。
すなわち、役員や使用人の横領が長期にわたって行われ、その横領が偽りその他不正の行為に該当する場合には、7年間遡って更正されることとなります。
Ⅲ 抑止策・発生した場合の対応策
1. 抑止策
ここまでみてきたように、役員や使用人による横領があった場合、法人は横領されたことによる損害を受ける上に、税務面においても、被害者たる法人の立場からすれば納得し難い非常に厳しい取扱いを受けることとなるため、まずはそのような事態が発生しないような抑止策を講ずることが大切です。
横領などの不正行為は、その行為者に「動機」「機会」、そして不正を行うことへの自分なりの「正当化」の3条件がそろったときに発生する(米国の犯罪学者ドナルド・R・クレッシーによるいわゆる「不正のトライアングル」)といわれ、いかに「機会」を減らすか、が不正行為の抑止のポイントとなります。
そのためには、まずは現金取引をやめて銀行振込とする、相互チェックできるよう担当者を複数置く、定期的に担当替えを行うなどの対策が考えられます。
例えば、コンビニエンスストアを展開する(株)ローソンでは、従業員が取引先と共謀し、業務委託料の水増しにより取引先にプールさせ、これを私的用途に使用するという不正行為が発覚しました。1人の社員に長年同じ業務を単独で担当させたため、社内での監視機能が働かず、定期的な業務チェックでも不正を発見できなかったということで、再発防止策の一つとして特定業務のローテーションの制度化を掲げています(19年8月30日付同社ニュースリリースより)。
また、複数担当や業務のローテーションといった人的な余裕がない中小企業であっても、請求書や納品書等の精査を行う、資産の実査を行う、あるいは得意先に残高照合を行うなど、不定期であっても実施することにより、不正の発見や抑止効果が期待できます。
2. 発生した場合の対応策
抑止策をとったとしても、不正行為をゼロにすることは難しく、不幸にして横領が発覚した場合、懲戒解雇等の処分を検討することとなりますが、事実関係の精査、過去の同様の事例に対する処分とのバランスの考慮、弁明の機会の付与など手続きの遵守、といった点を踏まえて慎重に決定する必要があります。
また、就業規則に懲戒処分に関する規定がないとか、規定があっても労働者に周知していない場合には懲戒処分ができないため、就業規則における懲戒の種類および事由を整備(10人以下で就業規則の作成義務がない事業所では個別の労働契約等で合意)しておくべきでしょう。
ところで、解雇する場合、30日前の解雇予告または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けることによってこの手続きは除外されるものの、手間と時間を要する上、確実に認定を受けられるとは限らないため、あえて解雇予告手当を支払って解雇してしまうことも考えられます。
なお、懲戒解雇が認められる場合であっても、退職金の不支給または減額については、従業員のそれまでの勤続の功をすべて抹消ないし減殺するほどの著しく信義に反する行為が存在することを要するものとされ、認められない場合があります。
さらに、横領者に対する民事責任の追及(損害賠償請求や不当利得返還請求など)や刑事責任の追及(業務上横領や背任など)が考えられます。損害賠償が認められても、横領者はすでにこれを費消してしまって資力がなく回収できないことも多いでしょうし、刑事告訴についても手間と費用がかかりますが、会社の信用や従業員のモラル維持のために、これらについて検討すべき場合が多いものと思われます。



