EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

主に今後新規にデータセンター(以下、DC)市場への参入を目指す企業の皆さまに対し、DC建築に係る供給体制が、足元でどのような環境下に置かれているかをご紹介します。
本稿の執筆者
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 ストラテジー事業部 TCF Lead Advisory 小室 英雄
TMT業界、金融業界、不動産業界を中心にプレM&AフェーズからM&Aの実行、海外PMIハンズオン支援までLifecycle支援に強みを有する。EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 パートナー。
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 ストラテジー事業部 TCF Lead Advisory 七澤 奈緒子
プレM&Aフェーズからの戦略立案からオンディールに係る企業・市場調査、事業計画策定支援を中心に携わる。リサーチ業務に長く従事しており、事業成長性評価、事業計画策定、企業価値評価、市場分析を踏まえた多数の業界・企業レポートを執筆する。EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 ディレクター。
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 ストラテジー事業部 TCF Lead Advisory 西岡 宏祐
データセンター業界のマーケットリサーチなど、同業界に関連する業務に複数従事。EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 スタッフ。
要点
- 建設人材の労働需給がひっ迫していることに加え、DC建築・運営において必要不可欠な電気主任技術者の人材不足はより深刻であり、さらなる労務費高騰につながる可能性が考えられる。
- 資材・設備費の高騰が建設費全体のコスト増の要因となっていたが、地政学リスクなどに伴う世界的なインフレ状況は継続する可能性があり、資材・設備費共に高止まりする可能性が考えられる。
- DC運営に必要不可欠な電力供給網整備のための投資は増える予想にあるものの、電力供給網は当面不足状態が続く見込み。
Ⅰ はじめに
近年、国内のデータセンター※1(以下、DC)需要は、デジタル化やクラウド化の進展に伴い、大幅に増加することが見込まれています。中でも生成AI開発などを支えるGPU※2DCの需要は、急拡大が見込まれていることもあり、同市場への新規参入を検討する企業も、国内外を問わず増加しています。一方で、国内のDC供給体制を見ると、建設コスト高騰や電力送配電網整備※3の必要性などがボトルネックとなり、DC建築計画の見直しが検討されるケースも浮上しており、ITインフラ構築を進めたい政府なども留意している状況です。
本稿の目的は、DC市場への新規参入を目指す企業の皆さまに対し、DC建築に係る供給体制が、足元でどのような環境下に置かれているかを示すことで、実際に参入を図る上での検討材料として活用していただくことです。DC供給体制について、今回ご紹介するのは主に以下の2点となります。
- DC建築費
- 送電網の整備状況
なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添えます。
※1 データの処理を目的とした、コンピューターやデータ通信のための装置を設置及び運用することに特化した建物または室。電気事業法上「特別高圧」と区分される7kVを超える電圧を、一般的にデータセンターでは使用。
※2 Graphics Processing Unit の略称
※3 総務省・経済産業省、「デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合(第7回事務局説明資料)」www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/digital_infrastructure/0007/004_jimukyokusiryou.pdf(2024年10月10日アクセス)
Ⅱ DC建築費
近年、建設費用は2021年から2023年にかけて約15%上昇していますが、DC建築コストについては、同期間において69%上昇※3と、全体の上昇幅を上回る水準となっています。本稿では、DC建築コストの上昇を引き起こした背景について、DC建築コスト全体の約7~9割を構成する資材費と労務費の2つの側面から考察します。
1. インフレ・地政学リスクを背景とした資材・設備費用の高騰
DC建築費の4~5割程度を占める資材費は2013年から2023年にかけて、約50%上昇しています。特にウクライナ情勢などによる世界的なインフレに起因し、鉄鋼などを中心に、大半の資材価格が高騰しています(<図1>参照)。DCは構造躯体としてS造※4のケースが大宗を占めることから、鉄鋼製品などの高騰がDC建築コスト増に影響したとみられます。
加えて、DC建築においては、オフィスビルや倉庫、マンションなどの一般的な建築物と異なり、サーバーなどの機器をはじめとした電気設備や、サーバー冷却のための高性能な冷却設備の完備が求められます。DC建築においては、これらの設備機器関連の費用についても重要要素として着目する必要があると思われます。
近年では、冷却設備機器の高騰が顕著となっており、直近10年で価格が倍近く上昇しており、足元も上昇が継続しています。特に2020年から2023年にかけてのCAGR(年平均成長率)が約9%と大きくなっており、パリ2024オリンピック競技大会に向けた設備投資意欲の拡大、コロナ禍以後の空気環境への意識変容などが冷却設備機器の価格に影響を与えていると考えられます。一方で、電気設備機器の価格については、近年安価な海外製の製品が市場に流入していることから、比較的緩やかな上昇にとどまっていますが、2020年以降は製造に必要な各種素材価格が世界的なインフレを背景に高騰したことを理由に、上昇率がやや高まりつつあります(<図2>参照)。
設備費の高騰分をDC利用者へ価格転嫁する動きが今後予想されますが、競合との価格競争の結果、供給側の利益幅が圧迫されるという状況が起きることも考えられます。
設備費をさらに抑制するために、DC事業者によるサプライチェーンの統合や、設備メーカーとの協業という動きも今後選択肢として検討される可能性も考えられます。
※4 S造:鉄骨(Steelの略)造のこと。建物の骨組みに、各種鋼材を用いた構造。
図1
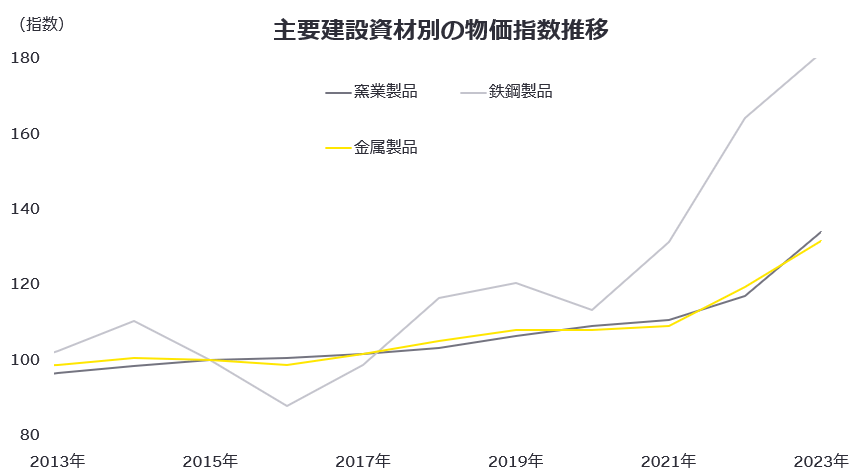
図2
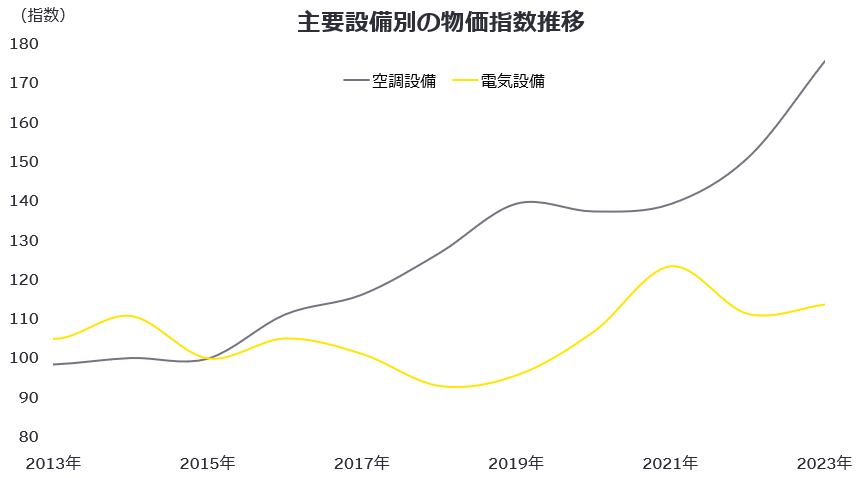
2. 建設労働者不足に起因した労務費の高騰
DC建築費の3~4割程度を占める労務費は、2012年の1,650円/時間を底に急上昇しており、2023年には2012年対比で1.3倍程度の水準となっています(<図3>参照)。労務費上昇の主な要因と考えられる①建設業就業者数の減少に伴う労働需給のひっ迫、②品確法の改正※5に端を発した発注者への適切な価格転嫁の促進、という2つの観点で以下詳細に考察していきます。
まず①の労働需給のひっ迫ですが、背景の1つとして建設業就業者の高齢化が挙げられると考えられます。2022年時点、建設業における55歳以上の労働者が占める割合は35.9%と、国内全産業平均の31.5%を上回っており、高齢化問題がより深刻であることがうかがえます(<図4>参照)。建設事業者各社は新たな人材確保に取り組んでいますが、生産年齢人口がすでに減少基調にある中、建設業従事者の割合は直近10年間で約6%とほぼ横ばいの状況が続いており、人員増の実現に向けたハードルは高いものと思われます。
※5 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の略称。2005年に施行された法律であり、過去3回改正されている(2014年、2019年、2024年)。2014年の改正にて従事する労働者の賃金、労働条件、労働環境等の改善を実施。2024年の改正では、建設業従事者の確保に向け、従事者の休日確保やさらなる処遇改善推進策を導入。
図3
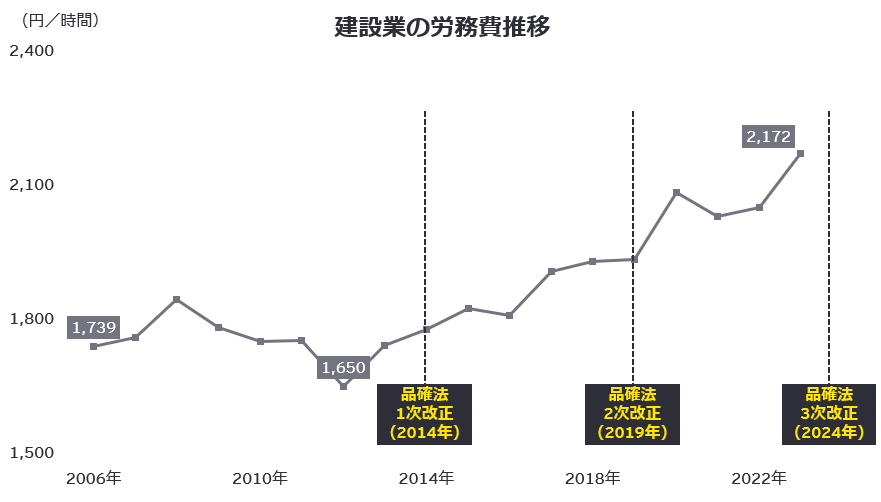
図4
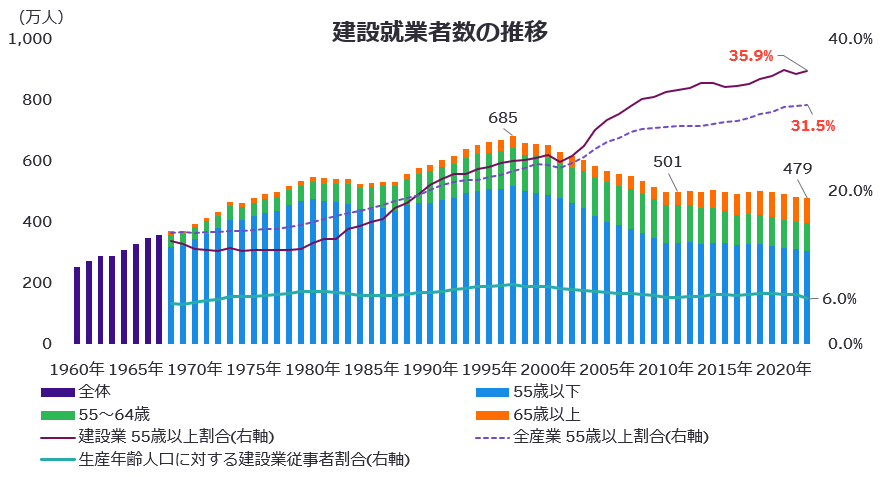
中でも、DCの開発や運用にて、電気事業法で人員配置が必須とされている第二種以上の電気主任技術者においては労働者の高齢化に加えて、以下2つの個別事由を背景に、特に労働需給がひっ迫している可能性が考えられます。
1点目は、免状取得までに時間を要することから、短期間での人員増強が見込みにくい点です。2点目は、DC以外の建築工事においても電気主任技術者の引き合いが強い点です。カーボンニュートラル対応の必要性の高まりなどから、再エネ設備関連の工事が増加しているとみられ、それに応じて第二種以上の電気主任技術者確保へのニーズも高まっているとみられます(<表1>参照)。
以上から、第二種以上の電気主任技術者の確保は特に難しい状況とみられ、当該職種の確保が必須となるDCの供給においては、ボトルネック要因の1つとなっていると考えられます。
表1 電気主任技術者について
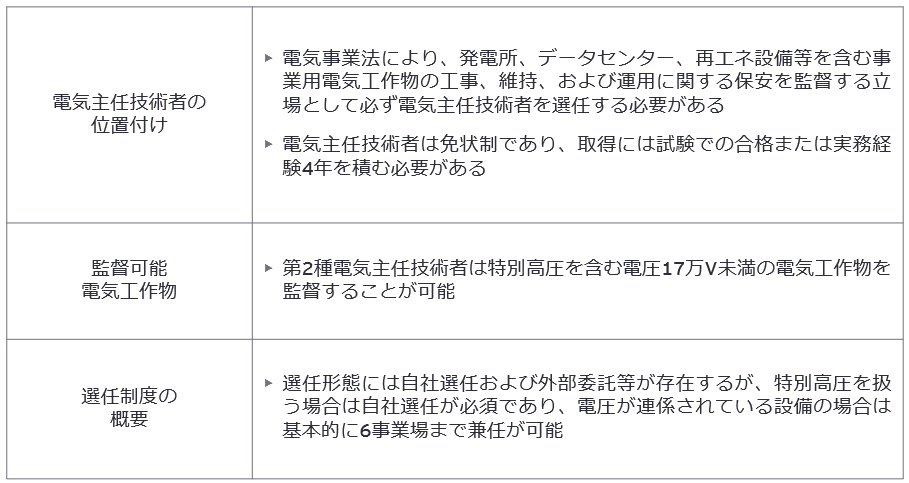
次に、②の適切な価格転嫁の促進について考察します。①の通り建設業における労働需給はひっ迫し、人材の確保が急がれる状況の中、政府による品確法の改正が複数回実施されました。品確法の改正は建設業従事者の処遇改善などにより、建設業従事者を増加させることが目的とされた法改正であり、労務費の上昇要因になっていると考えられます。
Ⅲ 送電網の整備状況
DCは電圧が7kVを超える特別高圧電気を消費します。特別高圧電気はDC運営に必要不可欠なものでありますが、当該電気を送る送電網の整備が行き届いていないのが実態です。千葉県印西市や東京の多摩エリアなど、DCが密集している地域でも特別高圧電気の送電網が不足しており、新たに特別高圧電気を引き込むには相応の時間を要す状況となっています。
こうした状況に至った背景の1つとして、各送配電事業者が計画していた特別高圧電気に係る送電網への新規投資以上に、DC需要が拡大した点が考えられます。
電力広域的運営推進機関※6が発表している「全国及び供給区域ごとの需要想定について」によると、2023年1月時点では、東京の将来の電力需要想定がCAGR▲0.1%、全国の将来の電力需要想定がCAGR▲0.2%(共に2023年~32年の期間)と微減推移想定となっており、各送配電事業者が送配電網への新規投資を抑制していた可能性が考えられます。しかし、近年のDC関連の電力消費量の増加などを背景に、2024年1月時点の電力需要想定値では、増加見通しへと上方修正されました(<図5><図6>参照)。電力需要想定値の上方修正を受け、今後、各送配電事業者による送配電網整備に向けた投資が増加する可能性が考えられるものの、当面は送配電網が不足する状況は継続するとみられます。
※6 電源の広域的な活用に必要な送配電網の整備を進め、全国規模で平常時・緊急時の需給調整機能を強化することを目的に2015年4月に設立。電気事業法に基づき、認可法人として業務運営を行っている。電力広域的運営推進機関はすべての電気事業者に加入義務あり。加入している事業者を対象に調査を実施し、「全国及び供給区域ごとの需要想定について」など、各種報告書を公表。
図5
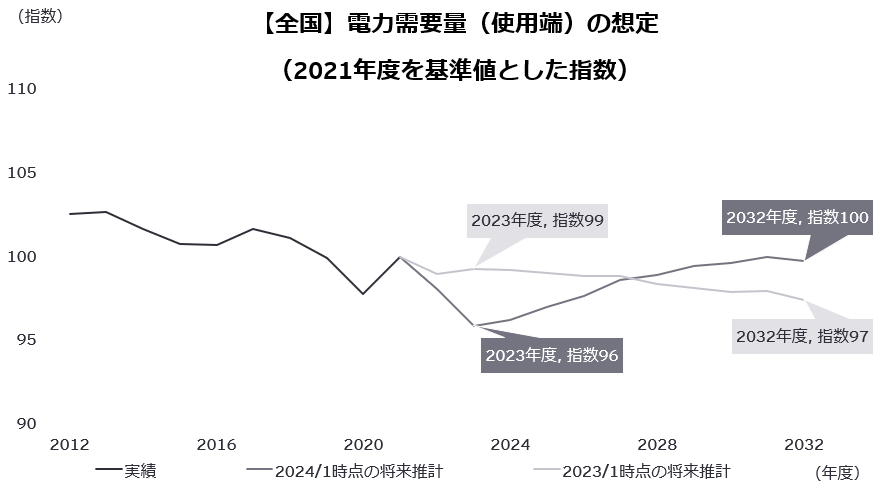
図6
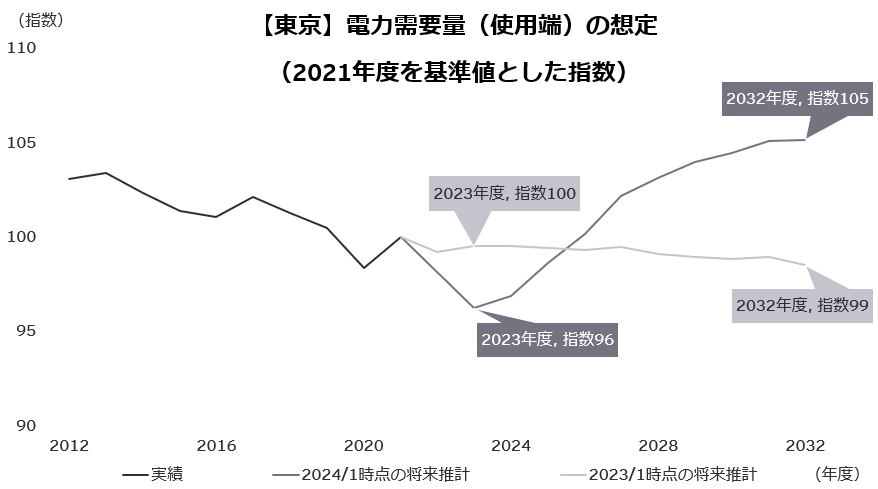
Ⅳ おわりに
ここまで述べてきた内容のポイントをまとめると次の通りとなります。
- 建設人材の労働需給がひっ迫していることに加え、DC建築・運営において必要不可欠な電気主任技術者の人材不足はより深刻であり、さらなる労務費高騰につながる可能性が考えられます。
- 資材・設備費の高騰が建設費全体のコスト増の要因となっていましたが、地政学リスクなどに伴う世界的なインフレ状況は継続する可能性があり、資材・設備費共に高止まりする可能性が考えられます。
- DC運営に必要不可欠な電力供給網整備のための投資は増える予想にあるものの、電力供給網は当面不足状態が続く見込みです。
引き続きDCの需要増が見込まれる中、その需要を捕捉する供給体制がどのような環境下に置かれているのかを理解することで、新規参入や既存の能力増強において、より事業機会創出につながるような判断を導き出せると考えています。
本稿が皆さまのDC建築に係る供給体制に対する理解を深める一助になれば幸いです。
サマリー
主に今後新規にデータセンター(以下、DC)市場への参入を目指す企業の皆さまに対し、DC建築に係る供給体制が、足元でどのような環境下に置かれているかをご紹介します。
関連コンテンツのご紹介
主にデータセンター(以下、DC)関連のビジネスに携わる方々に対し、①GPUサーバー/CPUサーバーが有す主な特徴の違い、➁各サーバーを設置するDCに求められる要件の違いという、大きく2つの情報を提示することで、需要が拡大するGPUサーバー向けDC関連ビジネスへの進出の際に留意する必要のある点を示します。
半導体の微細化鈍化こそがデータセンターの需要拡大のドライバー
半導体の微細化技術はムーアの法則に従って進化してきましたが、2010年ころを境に微細化ペースの鈍化が顕著になっています。この技術の制約と、その制約を乗り越えるコンピューティング技術の進化が昨今のデータセンター需要拡大をけん引しています。本稿ではそれらの関係性を明らかにします。
戦略(EYパルテノン)、買収・合併(統合)・セパレーション、パフォーマンスの再構築、コーポレート・ファイナンスに関連した経営課題を独自のソリューションを活用し、企業成長を支援します。
全国に拠点を持ち、日本最大規模の人員を擁する監査法人が、監査および保証業務をはじめ、各種財務関連アドバイザリーサービスなどを提供しています。
情報センサー
EYのプロフェッショナルが、国内外の会計、税務、アドバイザリーなど企業の経営や実務に役立つトピックを解説します。



