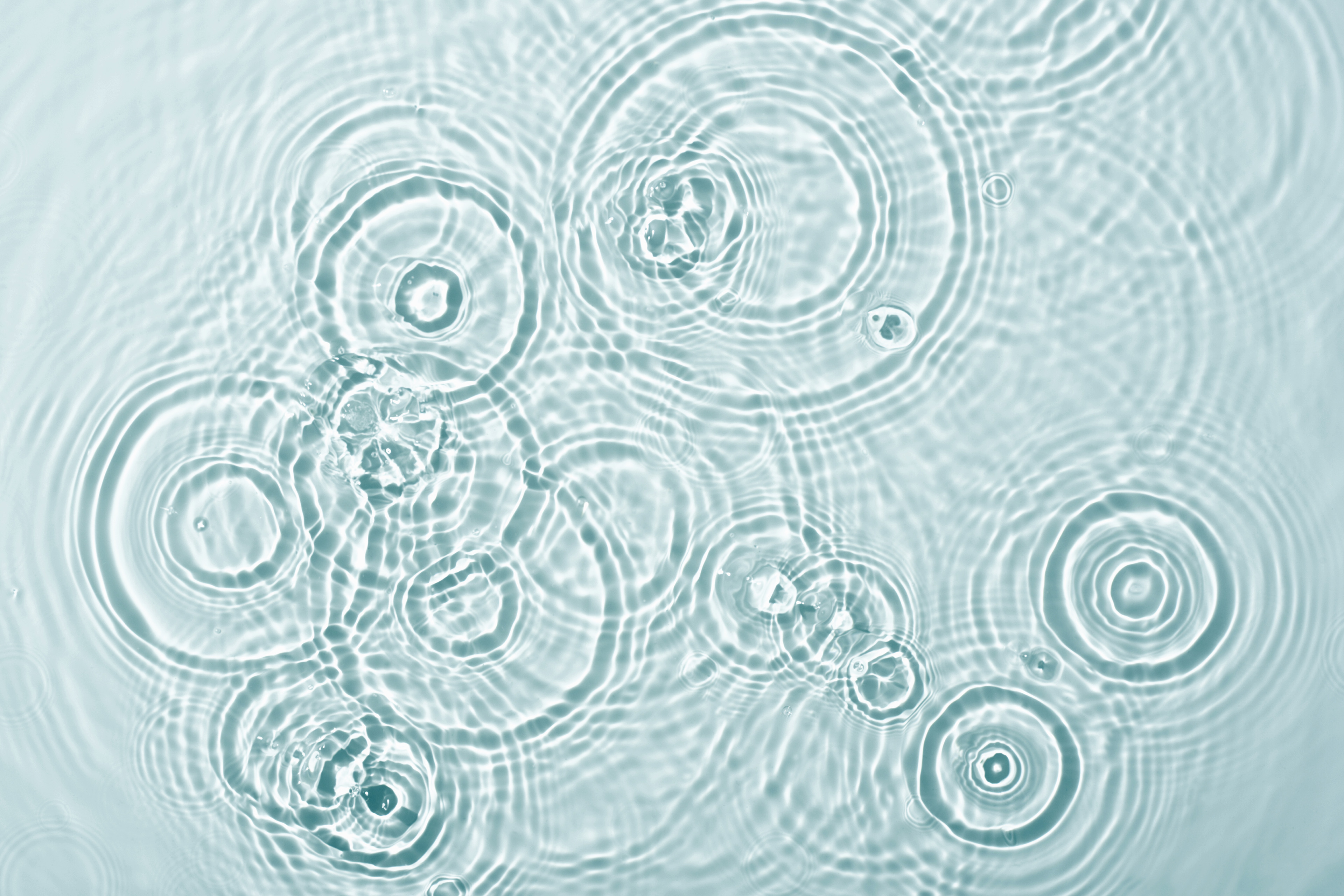EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

人口減少に伴う収入減、施設の老朽化、自然災害や脱炭素化への対応、そして深刻化する担い手不足。課題が山積する上下水道事業において、解決の切り札として期待を集めるDXを成功に導くには──。EY主催セミナーで語られた知見をまとめました。
要点
- 持続可能な上下水道事業の実現に向け、DXを起爆剤とする業務の飛躍的な効率化と、広域連携による組織力の強化が求められている。
- 自治体におけるDX導入の初期段階においては明確な戦略・ビジョンの策定と、トップダウン/ボトムアップ両面からの推進体制強化が必要。
- 上下水道DXの導入手法として官民連携事業は有効であり、官民連携事業によるアセットマネジメントの導入が、維持管理データの構築や施設劣化の予測・見える化などを可能にする。

Section 1
上下水道事業におけるDX導入の最新動向
「上下水道DX」への期待が高まる中、折しも国土交通省では2024年12月に「上下水道DX推進検討会」を設置。上下水道サービスの持続性確保に向け、DXの推進方策について検討する議論を開始しました。同時に、政府のデジタル行財政改革会議においても上下水道を新たなテーマに設定。従来のような供給者視点ではなく、サービスの利用者視点から課題に迫る関係者との対話を始めています。
「このように上下水道へのデジタル活用は政府全体の取り組みにも波及しています。政府は地方財政法の改正案を策定し、自治体が公共事業などにデジタルソリューションを導入する際に地方債の発行を可能にするとしています。実現すれば、イニシャルコストの負担軽減にもつながるでしょう」
EYストラテジー・アンド・コンサルティングの福田健一郎(インフラストラクチャー・アドバイザリー)はセミナーの冒頭でそう述べて、上下水道業界を取り巻く数々の課題を解くDX効果に期待を寄せました。
「収入源・老朽化・職員減」の三大課題を解く挑戦
重要な生活基盤である上下水道の持続にDXを最大限に活用する。そのためのポイントと課題は何か──。この命題を受け、次に登壇したEYストラテジー・アンド・コンサルティングの松村隆司が、「上下水道分野におけるDX・新技術の導入に関する動向」について発表しました。
松村はまず、上下水道事業を取り巻く課題として、①収入源(約3割の事業が原価割れ)、②老朽化(4分の1の管路が法定耐用年数超え)、③職員減(職員数10名以下の事業が約半数)の3つを挙げ、いずれも看過できないレベルにあることを確認。これらの解決策として、「広域化による規模の経済と施設統廃合」「官民連携による事業効率化・事業推進」「エネルギー事業等との複合化」と並んで期待されるのが、「デジタルによる事業改善、効率化、災害対策」であるとしました。
「ひと口にDXと言っても、その要素技術はロボティクス、AI、デジタルツイン、センサーなどと幅広く、機能面においても、これらを駆使した情報の連携・収集や、支援・自動化、予測・検知と多岐にわたります。またDXの目的も、アセットマネジメントの高度化、危機管理の向上、技術継承、業務効率化、サービス水準向上などいくつもあり、ここ1~2年で実証段階から実装へと進んだ事例も数多く見られます」(松村)
その一方、DXや新技術の導入には、国、自治体、民間事業者、スタートアップ企業それぞれの立場で直面する課題があるのも事実です。例えば、国・規制当局においては、規制・規格・ガイドラインなどが新技術に追いつかない場合があり、自治体では、先行事例がないため新しい技術を導入しづらい、人材難のため導入に向けた企画立案が進まない、といった問題が指摘されています。
また、民間事業者の場合、参入・実証・実導入の3段階において、資金・情報・場の各面での課題が確認できます。例えば、参入段階では自治体がどんな技術を求めているかわからない(情報面)、実証段階では、試験にかかる費用が民間の持ち出しとなるケースが多い(資金面)、実導入の段階では、自治体への一括営業の機会がなく、個別営業に時間がかかる(場)などが挙げられます。
これらの課題解決の実践例として、本セミナーに登壇する国土交通省、阪神水道企業団、静岡県富士市での取り組みへと話をつないだ上、民間事業者による上下水道DX市場へのアプローチに際して特に重要となる視点を以下のように挙げ、松村は話を終えました。
「上下水道事業体へ提供可能なコア技術などのソリューション、すなわち『武器』と、営業先や実証の場といった事業展開のための『フィールド』。この2つを掛け合わせることが極めて重要であると、われわれEYでは考えています。異業種やスタートアップとの連携による迅速なソリューション開発も検討する必要があるでしょう。いかに素早く実装まで進め、ブラッシュアップしていくかが問われます」(松村)
Section 2
上下水道DXを推進するための原動力
「広域連携」で実現する業務効率化と組織体制強化
続いて発表に立った国土交通省上下水道審議官グループの茨木誠氏(上下水道技術企画官)は、上下水道DXの必要性と、その推進に向けた国の施策について説明。上下水道をめぐる事業環境が厳しさを増す中で、将来にわたってサービスを提供し続けるには、「データ・情報・知識などの資源をデジタル技術によって活用し、業務の飛躍的な効率化を図ること。また、広域連携の加速によって組織力を強めることが必要」と述べました。その推進力として求められるのが、官民連携や異業種間の連携です。
茨木氏によれば、日本の水道事業の特徴は、電気やガスといったほかのライフラインに比べて小規模の事業者数が格段に多く、上下水道を合わせて5,000を超えるといいます。それだけに事業は地域に根差し、人材、資金、情報、経験、ノウハウなどあらゆる面で経営資源が各地に分散しているのが実情です。
「こうした中で規模の経済を効かせて効率化を図るため、また管理体制を強めるために求められているのが、広域連携の推進です。このため、すでに全都道府県において水道広域化推進プラン、および汚水処理の広域化・共同化計画が策定済みですが、これをさらに推し進めるため、国交省としてもモデル地域の検討支援や事例集の水平展開、また財政支援措置などを実施しています」(茨木氏)
広域連携のカギを握るDXの推進に向け、国土交通省では「上下水道DX技術カタログ」の策定や、今後5年程度で全国の事業体にデジタル技術を標準装備するための支援、また水処理運転操作等へのAI導入に向けた環境整備などを進めています。政府の活動もこれに歩調を合わせ、前述のデジタル行財政改革会議や上下水道DX推進検討会での議論が進展中。検討テーマとしては、①優れた業務事例の分析・共通化・横展開、②情報整備や管理の在り方の標準化、③DX技術実装に向けたカタログ策定、④経営状況や耐震化といった現状の可視化、の4点が挙がっています。
「上下水道DXの推進は令和7年度政府予算案にも盛り込まれ、上下水道に関する台帳情報のクラウド化や、広域的に実施するデジタル技術による水道施設の点検・調査などが、支援対象に加わりました。これらの予算も活用して、広域連携の取り組みを加速してください」(茨木氏)
DX戦略の策定から始まる実導入へのステップ
では、実際にDXを進めて広域連携へと至るまで、どのようなステップを踏めばよいのでしょう。兵庫県内6市への水道用水供給事業を担う阪神水道企業団の事例について、同企業団経営企画課の海戸深幸氏による紹介がありました。
阪神水道企業団では「水道用水供給ビジョン」を踏まえた経営戦略の一環として、2023年にDX戦略を策定。DXの目的や方向性を明確にした上で、2024年から戦略に基づくプロジェクトを実行しています。背景には人口減少や人材高齢化などの複合的課題があり、それらの解決に向けて以下6つのアプローチを定めたと言います。
「① 施設の適切な維持管理と着実な更新、②施設規模の適正化と費用負担の見直し、③組織体制の強化、④経営努力の継続、⑤官民連携、⑥阪神地域を俯瞰(ふかん)した広域連携。これらを解決する手段として選択したのが、DXです」(海戸氏)
同企業団ではまず、曖昧になりがちなDXの定義や意義を明確にし、組織内部のコンセンサスを得た上で、「構成市水道事業との一体的で効率的な事業運営」を目的とすることに決定。すなわち、広域連携の実現ですが、それには業務の効率化など内部の取り組みが不十分であると判断し、既存事業へのテコ入れから着手します。その過程で得られた知見を外部との新しい取り組みへ、つまり地域一体の効率化・変革へと振り向ける戦略です。
こうした方針に基づき、事務系・技術系それぞれについて業務の棚卸しと可視化を進め、デジタル化に向けた現状把握を実施。同時に、トップダウンとボトムアップの両面から組織全体の推進体制を固めていきました。「DXのような新しい取り組みを始めるには、トップによる明確な方針提示、組織的な支援体制の構築、予算確保への理解が不可欠でした」と、海戸氏は振り返ります。また、ボトムアップについては、職員による課題発掘ワークショップや業務アプリの作成体験などを通じて、DXへの理解と参加を促しました。さらに、各部署の職員によって構成されるDX推進委員会を立ち上げ、DX戦略の全体的な方針を決める役割を持たせたと言います。
海戸氏はまた、DXを進める上で避けては通れない重要なポイントとして、変化への不安や情報不足などに起因する「保守的な意見」との向き合い方に言及。①情報発信による透明性確保や成果の共有、②やる気のある職員や部署を支援して成功事例を増やす、③現状業務の大幅カット、④継続的なマインドセット研修、の4点を対策として挙げました。
戦略策定から1年を経て、阪神水道企業団のDXは予定より早いペースで進行中。既存業務の効率化や自動化に取り組みつつ、広域連携に向けた構成6市との協議を進めています。「内部での取り組みを地域一体のDX施策へと発展させていく」(海戸氏)構えです。
Section 3
官民連携事業を起点としたDXの実現
包括的民間委託を活用したストックマネジメント
DX効果の確かな見込みが立てにくい状況下では、いざ計画から実導入へと至る段階で足踏みを余儀なくされるケースも見られます。そうした課題に対する一つの策として、「官民連携事業を起点としたDXの実現」に取り組んでいるのが、静岡県富士市です。同市上下水道部下水道施設維持課の佐野和史氏が、「包括的民間委託による管路施設ストックマネジメントの構築」をテーマに発表しました。
人口約25万人のまち、富士市。ここでも多くの自治体と同様、下水道事業にまつわる課題として、①インフラ老朽化、②下水道財政逼迫(ひっぱく)、③災害激甚化・頻発化、④技術継承問題、⑤温室効果ガス削減、が重視されています。これに対して「官民連携の拡大・レベルアップ」で対応することが富士市の方針であり、その手段となるのがDXおよびGX(グリーン・トランスフォーメーション)であると、佐野氏は言います。
「その先に、私たちが見ている最終パーパスが、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)による持続可能な下水道経営の実現です」(佐野氏)
富士市では現在、下水汚泥燃料化実証事業など8つの官民連携事業によってDX・GXの取り組みを推進中で、その基軸となっているのが「処理場・管路管理」を目的とする包括的民間委託事業です。ここには管路施設の巡視・点検をはじめ、省エネ・DR(デマンドレスポンス)、下水処理自動運転などの施策が含まれ、これらを踏まえて近い将来、包括的民間委託からウォーターPPPへのレベルアップが計画されています。
佐野氏によれば、富士市では2015年から管路施設の点検業務を重視してきたものの、机上分析や経験値判断に起因する劣化施設の発見率の低さなどが問題視されてきました。そこで、包括的民間委託を活用した巡視・点検の追加により、実態に即した予防保全型維持管理へと転換。また、既存施設の長寿命化を図るストックマネジメントの導入により、維持管理データの構築から劣化予測までを可能にする仕組みを整えることになりました。
その際、官民連携事業の発注基本方針として重視したのが、①リスク評価に基づく点検優先度の設定(対象管路の選択と集中)、②従来の包括的民間委託業務に巡視・点検を追加(官民連携の強化)、です。また、包括的民間委託事業者が開発した高解像度管口カメラとタブレットシステムにより、現場の作業手順を一元管理。下水道管路施設管理システムとの連携による調査・チェック漏れの解消や、写真撮影の遠隔操作による省力化・効率化などを可能にしました。
「これらによって得られた巡視・点検データは、管路施設劣化の見える化に活用。経年劣化分析に基づくハザードマップを作成し、それをストックマネジメントのリスク評価の発生確率に反映させるなど、机上から実態への転換に努めています」(佐野氏)
このほか、データを活用した劣化予測や、設備台帳システムの整備などが進展。今後は、使用量データを自動で取得する水道スマートメーターの導入を目指し、複数事業者と検討を重ねているとして、佐野氏は壇を降りました。
続く第2部では、上下水道DXにおける課題や諸外国での取り組み事例についての発表、また5名のパネリストによるディスカッションが行われました。詳しくはレポート後編をご覧ください。
サマリー
「持続可能な上下水道事業」をDXのチカラで実現させるため、多くの自治体で計画策定や官民連携などの取り組みが進められています。そのカギとなるのは民間事業者における技術と事業フィールドの整備、そして自治体におけるゴールを据えた明確な戦略と多様なスキームの活用です。
メールで受け取る
メールマガジンで最新情報をご覧ください。
関連記事
【後編】DXで変える水の流れ 〜上下水道におけるDX、イノベーションの方向性を考える〜
人口減少に伴う収入減、施設の老朽化、自然災害や脱炭素化への対応、そDXの積極的な導入により、上下水道事業の未来にはどんな可能性が開かれるのでしょう。官民協働の広域連携により数々の課題を乗り越え、人々の幸せを支える存在へ。その理想に向けて望まれることを語り合うセミナーのレポート後編です。
人口減少社会において、水道インフラの経営が危機に立たされています。「安全で安価な飲料水」の持続可能性を巡る課題と解決に向けたアプローチとは。EY Japanと一般社団法人 水の安全保障戦略機構の共同研究「人口減少時代の水道料金はどうなるのか?(2024年版)」を基にひもときます。
EY Japan(チェアパーソン 兼 CEO 貴田 守亮)と一般社団法人 水の安全保障戦略機構(代表理事:竹村 公太郎) は、3年ぶり4回目の共同研究結果である「人口減少時代の水道料金はどうなるのか?」(2024版)を発表します。