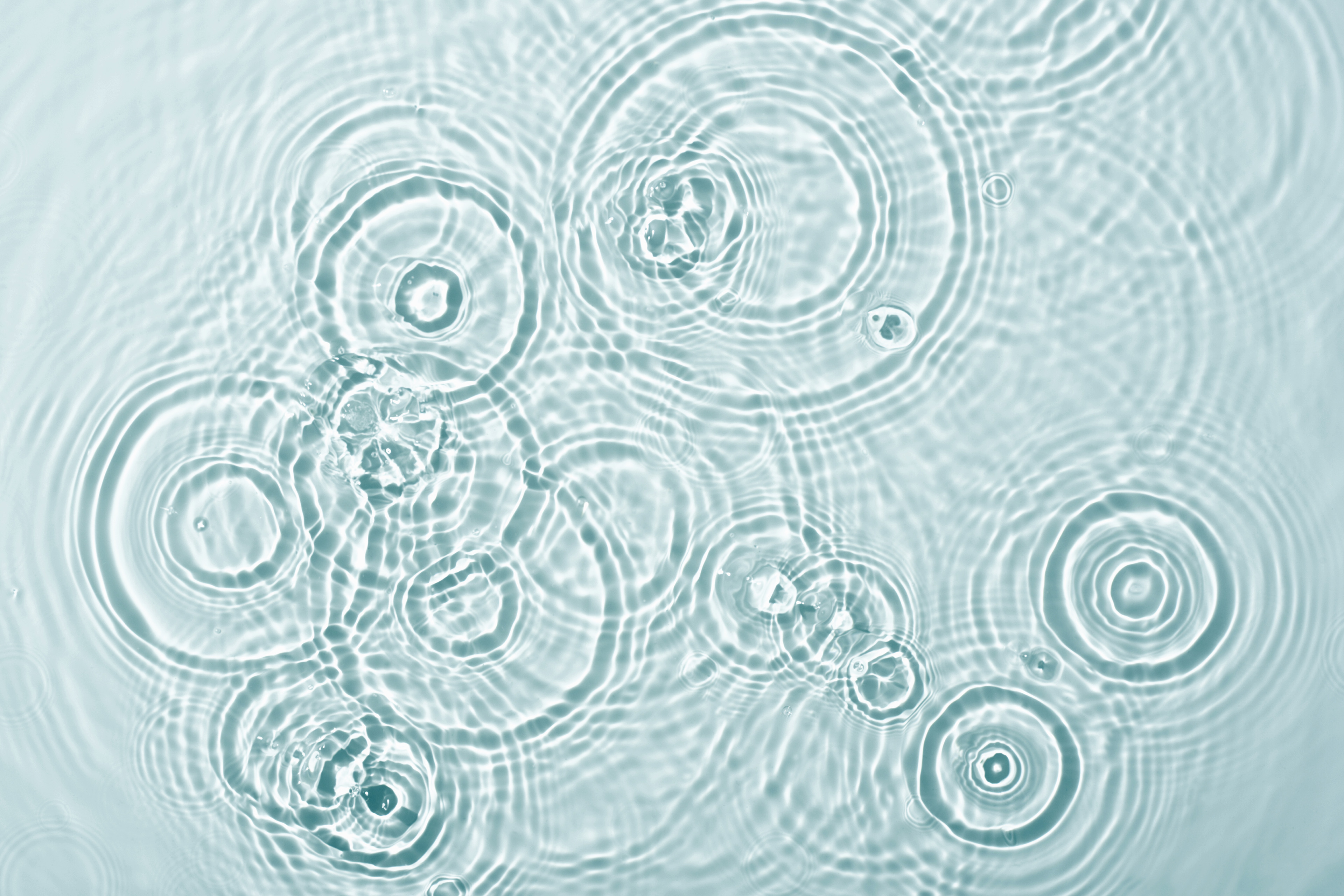EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

DXの積極的な導入により、上下水道事業の未来にはどんな可能性が開かれるのでしょう。官民協働の広域連携により数々の課題を乗り越え、人々の幸せを支える存在へ。その理想に向けて望まれることを語り合うセミナーのレポート後編です。
要点
- 明確な目的とビジョン、具体的な政策、個別のDX施策、この3つが織りなす重層的な戦略が、DX推進の原動力となる。
- 広域連携を実践する海外の先進事例に学び、リアルタイムのデータ管理を可能にする仕組みづくりを進めたい。
- 持続可能な上下水道事業とは人々の幸せに貢献する事業であることを念頭に、DXの在り方、考え方を検討する姿勢が大切。
Section 1
上下水道DXをめぐる課題と海外でのソリューション
上下水道事業におけるDX導入の最新動向と取り組み事例について紹介した本セミナー第1部に続き、第2部では「上下水道事業でDXを実現していくには」をテーマにパネルディスカッションを開催しました。パネリストには第1部で登壇した茨木氏、海戸氏、佐野氏に加え、東京大学特任准教授の加藤裕之氏(大学院工学系研究科)、ヴェオリア・ジェネッツ株式会社の伊藤万葉氏(官需事業開発本部)を招請。討論に先立ち行われたお二人の講演により、DX導入に関する課題、諸外国での導入事例について理解を深めました。
DXを成長エンジンとするために望まれること
下水道行政官の経験も有する立場から下水道システムイノベーションについて研究する加藤氏はまず、DXが「上下水道事業の進化を加速させるエンジン」となるための基本について以下のように述べました。
「よく言われるようにDXはあくまで手段であることを前提に、目的とビジョン、それに基づく具体の政策、そして個別のDX技術からなる重層的な戦略をベースとする必要があります。それを透明性のあるオープンな体質で進めていく。また、そのための中心となる組織をつくり、誰がどんな情報を集めてどう発信するかを明確に、初めから完璧を目指さず試行錯誤型の改善システムとすることが大切です」
実際、横浜市の取り組みではこうした重層的な戦略が構築されており、全体ビジョンの下に「ストックマネジメントDX」「防災・減災DX」「循環・脱炭素DX」といった個別政策があり、それらを支える基盤として官民共同研究などを含む「下水道プラットフォーム」が整備されています。
こうした事例を見ると、「広域化・インフラ統合」「省エネ・資源利用」「官民連携(PPP)」の3つの要素を、「DXによる効率化・統合」によって結び付ける三位一体の政策が重要であることが分かると、加藤氏は指摘します。また、本セミナー第1部の紹介事例にもあったように、データ化された維持管理情報を「ものづくり」につなげ、企業と自治体との対話も交えながら新たなニーズやアイデアを生み出すような、マネジメントサイクルの構築も重要だと言います。
「そのためには、オープン化によって競争性を高め、普及を促す政策も欠かせません。国が進める水道維持管理データの標準化と公表、そしてベンダーロックインの解消がカギとなるでしょう」(加藤氏)
ベンダーロックインとは、自治体などが新たなシステムを構築する際に既存システムのベンダーが有する独自の仕様が障壁となって他社の参入が阻まれることです。これを崩して公平な入札を実現しない限り、広域化・効率化は進まないと加藤氏は見ています。
加藤氏はまた、取り組みを普及させるには「人の本質」にフォーカスするアプローチが必要だとして、DXによって超過勤務時間の大幅削減を果たした苫小牧市の実例などに触れ、人々に「うまい・楽しい・つながる」をもたらすDXの在り方を推奨しました。結論は、「上下水道業界全体で情報を共有するエコシステムの実現に向け、知識と信頼を得て評価できる組織」をつくることの重要性です。
ヨーロッパに見る上下水道DXの先進性
続いて発表に立ったヴェオリア・ジェネッツの伊藤氏からは、ヨーロッパにおける3つの取り組み事例を通じて海外における上下水道DXの実情が紹介されました。ヴェオリアは、フランスを中心に世界58カ国で水・廃棄物処理・エネルギー事業を展開する企業グループで、水部門では2,300を超える浄水場、3,000を超える下水処理場の運営を通じて1億人以上に上下水道サービスを提供しています。以下、3つの事例の概要をまとめます。
パリ近郊─水道PPPにおけるDX
パリ市近郊151の市町村をカバーするフランス最大の水道事業体イル・ド・フランス水道組合(SEDIF)とのPPP契約に基づき、SEDIFが有する全施設の運営と一部の設備更新、顧客サービスに関する事業をSPCとしてヴェオリア社が受託しています。SEDIFでは行政の戦略に基づき管区全戸をスマートメーターに変更してあり、その設置およびデータの利活用をSPCが担っています。スマートメーターから得られるデータは料金算定などの顧客管理はもとより、漏水検知・補修などのアセットマネジメントや、浄水量コントロールなどの運転管理に活用されます。また、メーター情報に加え、水道施設や管路に置かれた計測器からの情報を集約してビッグデータを管理しています。災害・緊急時における近隣自治体との相互支援などにも生かされています。
日本では顧客、管路、施設などで縦割りにされた管理体制が目立ち、業務委託も個別になされるなど、データの横連携や複数領域への活用面で課題があります。コストの問題などからスマートメーターの普及も進んでいませんが、この事例のように運転管理や資産管理などを一元化する官民連携事業の推進により、投資価値も見いだせるものと思われます。
ボルドー─下水道PPPにおけるDX
同じくフランスの28の自治体をまたぐ広域下水道事業体ボルドーメトロポールとの間で、下水処理場6カ所、ポンプ場49カ所など全施設の運転維持管理・一部の設備更新を担うPPP契約を締結しています。メインの下水処理場内に置かれたコントロールセンターからの遠隔制御により、管路1,980kmにおよぶ流域内主要施設の広域管理と夜間集中監視を実施しています。日中は監視員を場内に配置しますが、夜間は場外から遠隔にて監視しております。緊急時には近隣から待機職員が駆けつける体制です。
日本では複数の処理場を持つ自治体が施設ごとに業務委託をするケースが多く、夜間も監視員を常駐させるのが一般的です。広域管理を可能にすれば、デジタル技術による夜間の運転体制の最適化や、従業員の働き方改革、担い手不足解消につながるのではないでしょうか。
ミラノ─AI活用による下水処理場の運転支援
ヴェオリア社のグループ企業がデンマークで開発した下水処理場運転支援システムにより、水質シミュレーションと運転制御のオンラインチューニングを実現しました。ヨーロッパ各地の自治体で数多く採用されております。リアルタイムの流入状況に応じて、デジタルツイン技術を用いたアルゴリズムが設備の最適な運転制御値を導出します。現場の自動制御技術であるPLC(プログラマブル ロジック コントローラー)を介して運転に反映させる仕組みを整えました。また消費電力の削減により、温室効果ガスの排出量を最小限に抑える効果も得られます。
このシステムを導入したイタリア・ミラノの下水処理場では、導入初年度からCO2換算で約1200トンの排出量削減を達成するなど環境負荷軽減に貢献するほか、処理水の100%農業利用の安定化、雨天時の処理能力増強などにも寄与しています。
こうしたリアルタイムのデータ管理を可能にするには、中央監視制御システムとクラウドの連携が不可欠であり、計画段階からそれを前提とした検討を要することを補足して、伊藤氏は話を終えました。
Section 2
上下水道業界に「夢のある未来」を開くために
続いてセミナーはパネルディスカッションへ。第1部の講演や加藤氏、伊藤氏による発表を踏まえ、DX実現に向けた課題やポイント、求められる支援、期待される未来像などをテーマに活発な意見交換が行われました。以下、各氏の発言要旨をまとめます。
計画・実証・実導入を進める上での課題と大事なポイント
佐野氏(静岡県富士市):加藤先生のご指摘にもあったように、DXは課題解決の手段に過ぎないことを肝に銘じ、市民のニーズと自治体の課題を見据え、しっかり目的を定めることが重要となります。同時に、人材難が深刻化する中で職員のやるべき業務を明確にし、その効率化に向けてDXをどう生かすかを考えること。そのためには官民連携が不可欠ですが、初期段階で発注要件を細かく設定しすぎると逆効果を招きかねません。長期にわたる契約期間において、段階的に提案を受けられる仕組みがあると良いと思います。
海戸氏(阪神水道企業団):明確なビジョンを共有すること、DXに必要な思考と能力を備えること、目の前にある業務の効率化から始めること。この3つが大切なポイントになります。実際、当企業団でも、いきなり大胆な変革を現場に課すのは無理があり、アナログ作業からデジタルへと少しずつ移行したり、単純作業の効率化から始めて現場の受け入れ体制を整えたりしました(前編参照)。地道なアプローチと小さな成功体験の積み重ねが、大きな改革への足掛かりとなります。
伊藤氏(ヴェオリア・ジェネッツ):DXを推進するには、まずデータの流動性を高めることが必要です。台帳や維持管理のデータを電子化する、オンプレミスの端末に蓄積されたデータをクラウドに上げるなど、必要なデータを必要なタイミングで使えるようにすべきでしょう。そうすることで、日常的な事業運営の効率化が進みます。縦割りになりがちな行政のシステムをつなぐことにもなり、災害などの緊急時対応に役立つなど、広域連携へのステップとなります。
茨木氏(国土交通省):皆さんのお話を聞き、明確な目的を持って施策をつくることの重要性を再確認しました。目的が違えば、使うデータも異なり、用いるデジタル技術も変わってきます。また、DXの過程においては失敗や停滞を許容する文化も重要な意味を持ちます。初期段階では変化に対する心理的抵抗や、業務過多による足かせも当然あり得ます。それらを包み込む組織の在り方が、逆に小さな成功につながり、挑戦する文化を育むのではないでしょうか。
加藤氏(東京大学大学院工学系研究科):他の自治体が取り組む優れた事例を見つけ、分析することをお勧めします。DXによってどのようなベネフィットが得られているか、思っていた以上の価値を見いだせる可能性もあります。実際に使っている人のナマの声にも耳を傾けたいです。実際、現場の人にとって使い勝手はどうか、どう感じているのでしょうか。現場に立つ人が持つ知識やノウハウへのリスペクトを忘れずに、それをしっかり引き継ぐためのDXであることを現場に伝えたいです。
官民連携を進める上で求められる支援と考え方
佐野氏:まさに、新しい挑戦には失敗がつきものだと思います。それを前提に官民の関係性について言えば、リスクを互いにどう分担するかを詰めておくことが重要です。民間に委託する以上、責任も全て民間に取ってもらうという姿勢では物事は進まないでしょう。また、手の届く身近な技術の導入から進めるほうが、結果的に自治体側の技術水準も上がっていくと思われます。
伊藤氏:富士市の取り組みにも見られるように(前編参照)、民間が参入できる事業なりフィールドなりを提供してもらえることを望みます。当社で言えば、上下水道施設の運転管理や事業運営などです。また、スタートアップの技術やサブスクリプション制度の導入も調達可能な選択肢に加えていただくと、異業種との接点が増え、官民連携の機会が広がるのではないでしょうか。
加藤氏:同感です。接点を広げることで、思いもよらない企業が上下水道DXを支える存在になるかもしれません。IT系の進路を希望する学生にとっても選択肢が増え、新たな活躍の場が開けるでしょう。また、DXで業務改善を目指す場合、そもそもの目的が業務改善にあることを忘れず、DXの必然性にまでさかのぼって検証することも大事です。民間がその手順を示すことで、自治体の認識も明確になり、日常業務を見直すきっかけにもなります。
海戸氏:国への要望として、水道分野に特化したDX推進の基本方針を示していただきたいです。具体的な変革イメージを共有できれば、自治体内外に施策を説明する際の説得力が増し、理解や共通認識が得られやすくなります。その意味でも国土交通省が進める「上下水道DX技術カタログ」に期待しています。そこにDX効果の定量的側面だけでなく、現場感覚を踏まえた定性的側面も含めてもらえれば、さらに理解が進むと思われます。
茨木氏:示唆に富むアドバイスをいただけたと思います。カタログにただ技術を並べるだけでなく、「課題とそれに対応する技術」のような形で見せる必要がありそうですね。そうすれば、異業種の方にも気付きが生まれ、新たな広がりにつながると思います。DX効果についても、マインドセットの変化や異業種との出会いなど、定性的な評価の大切さを改めて感じました。むしろデジタルだからこそ、そうした指標が必要かもしれないと感じました。
上下水道DXが進展した先に、どんな未来を見るか
佐野氏:今まで考えもしなかった新しい分野に上下水道の世界が広がる可能性があります。例えば、スマートメーターの蓄積データを、高齢者の見守りサービスや加齢によるフレイル(虚弱)対策に生かすなどのケースです。そうした未来が見えれば、スマートメーターの導入障壁となるコスト問題にも風穴が空くかもしれません。
海戸氏:当企業団が描く近未来の姿は、DXで給水地域全体の最適化を果たすことです。そのために組織の縦割り構造を崩し、シームレスな連携を実現させたいと願っています。職員アンケートに見る直近の期待値としては、運転・点検業務の省人化により、来たるべき施設更新の増加に備えることが挙げられます。
伊藤氏:期待されるDX効果を挙げるとすれば、事業運営の効率化、広域連携、働き方改革、脱炭素といったところになります。さらに本日のセミナーで、DXに取り組むことで得られる業界の魅力向上や、人材を引き寄せる効果があることも認識できました。熱意ある有能なタレントが集まる場としての、上下水道フィールドの可能性を感じています。
茨木氏:国としては「上下水道事業の持続性確保と新たな価値創出」が、上下水道DXがもたらす未来像と捉えています。広域連携の実現がその一歩手前にある目標で、そこに向けて官民連携や異業種連携を進めていきたいです。その一方、加藤先生が指摘されたように、人々の幸せのためのDXであることを忘れてはいけません。DXで効率化を進めつつ、創造力や発想力を要する役割を人が果たします。そうした観点から、次の世代に安心して使ってもらえる上下水道インフラを引き継ぎたいです。
加藤氏:民間企業が中心となってこの業界に再編の渦を巻き起こす、そんな絵が描けたらいいと思います。企業だけでなく、市民自身が家庭から上下水道管理に関われるような展開もあったら面白いでしょう。佐野さんもおっしゃるように、上下水道業界が健康業界や福祉業界に姿を変えていくような、刺激的なトランスフォーメーションが起きる未来に期待しています。
「これまで縦割り型の整備が進められてきた上下水道業界が、管路や処理場の場を超えて複合化し、あるいは異業種と融合して世界を広げていく。皆様のお話から、そんなDXの可能性を感じることができました」。最後に登壇したEYストラテジー・アンド・コンサルティングの福田がそう述べて、今回のEY LIVEウェブキャストは終演しました
サマリー
データの流動性を高めること、失敗を恐れず試行錯誤すること、小さな成功体験を重ねること、異業種との接点をつくること──。「持続可能な上下水道事業」を実現するための手段としてDXを捉えるために大切なことは何か。根本的な姿勢が問われています。
メールで受け取る
メールマガジンで最新情報をご覧ください。
関連記事
【前編】DXで変える水の流れ 〜上下水道におけるDX、イノベーションの方向性を考える〜
人口減少に伴う収入減、施設の老朽化、自然災害や脱炭素化への対応、そして深刻化する担い手不足。課題が山積する上下水道事業において、解決の切り札として期待を集めるDXを成功に導くには──。EY主催セミナーで語られた知見をまとめました。
人口減少社会において、水道インフラの経営が危機に立たされています。「安全で安価な飲料水」の持続可能性を巡る課題と解決に向けたアプローチとは。EY Japanと一般社団法人 水の安全保障戦略機構の共同研究「人口減少時代の水道料金はどうなるのか?(2024年版)」を基にひもときます。
EY Japan(チェアパーソン 兼 CEO 貴田 守亮)と一般社団法人 水の安全保障戦略機構(代表理事:竹村 公太郎) は、3年ぶり4回目の共同研究結果である「人口減少時代の水道料金はどうなるのか?」(2024版)を発表します。