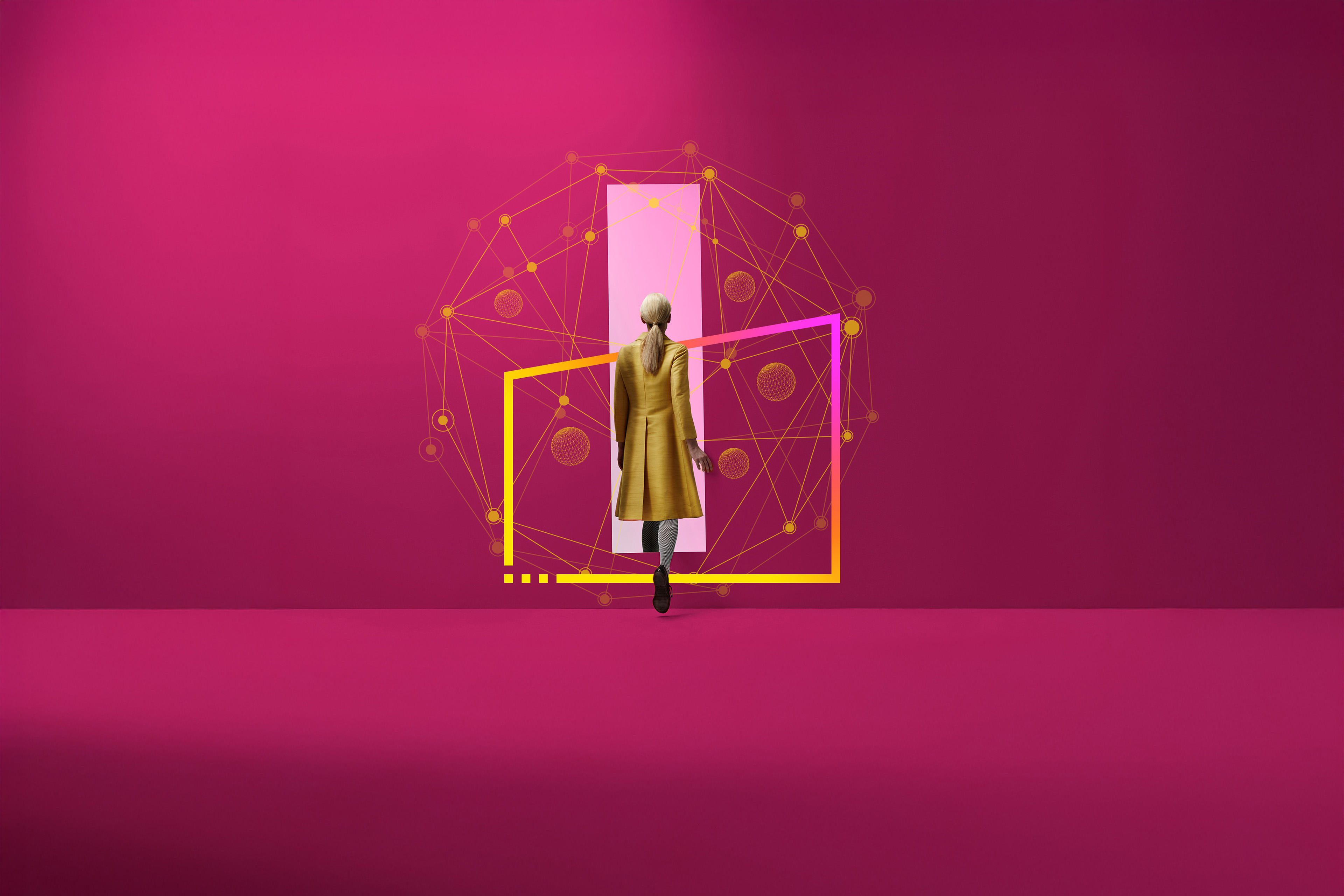EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

「Work Reimagined 2024 in Japan 未来の人材力を形づくる人材ダイナミクスと人材フローにどう向き合うべきか」 セミナーレポート(2024年12月19日開催)
EYが毎年実施している働き方に関する意識調査「Work Reimagined Survey 2024」の結果を基に、目まぐるしく変化する「future of work(未来の働き方)」について、先進的な人材マネジメント改革に取り組むMars社やパナソニック コネクト株式会社の事例を交えて解説しました。
要点
- 日本でも世界でも働き方は大きく変革しており、人材優位性を確保するには5つの要素が重要となる。
- 日本国内でもグローバル水準並みに人材流動性が高まり、キャリア自律や従業員体験が重要に。
- 米Mars社ではカルチャーを軸に人材優位性、競争優位性を獲得している。
- パナソニック コネクト社は、一人一人がキャリアオーナーシップを持ち、責任と権限を明確にする人材マネジメントを推進している。
パンデミックはあらゆる物事に大きなインパクトを与えました。「働き方」も例外ではなく、グローバルでさまざまな変化が見受けられます。加えて日本社会は、世界に先駆けて少子高齢化社会に突入し、新たな課題に直面しています。こうした中、企業はどのように働き方や人材マネジメントの改革に取り組み、人材優位性を確立していけばいいのでしょうか。
そのヒントを示したのが、2024年12月19日に開催されたセミナー「Work Reimagined 2024 in Japan 未来の人材力を形づくる人材ダイナミクスと人材フローにどう向き合うべきか」です。EYが実施している働き方に関する意識調査「Work Reimagined Survey 2024」の結果を基に、EYストラテジー・アンド・コンサルティングのピープル・コンサルティング パートナーの水野昭徳と、EY Japan ピープル・アドバイザリー・サービス/グローバルモビリティリーダー EY税理士法人 パートナーの藤井恵が働き方に関する最新動向を解説したほか、一足早く人材マネジメント改革に取り組み、成果を出しているMars社やパナソニック コネクト社の取り組みが紹介されました。

Section1
「Work Reimagined Survey」が示す、働き方の激変
EYの働き方再考に関するグローバル意識調査「Work Reimagined Survey 2024」からは、キャリアの築き方やトータルリワードの考え方が大きく変容していることが明らかになりました。その中で人材優位性を確保するには、5つの要素に留意する必要があります。
EYはこれまで5回にわたって、働き方再考に関するグローバル意識調査「Work Reimagined Survey」を実施してきました。これは2020年のパンデミックをきっかけに、世界的な健康危機が仕事の進め方や働き方に影響していることに着目して開始された調査です。
最新の「Work Reimagined Survey 2024」では、仕事の在り方は、ますます従来の価値観と乖離(かいり)したものになっていることが明らかになりました。
水野「キャリアの築き方やトータルリワードの考え方、働く場所などについて、従来の概念や価値観が大きく変容しています」

ピープル・コンサルティング パートナー 水野 昭徳
人材優位性を形づくる5つの要素
一部のビジネスリーダーは新しい局面を乗り切る方法を見いだし、「人材優位性」を獲得しつつあります。この人材優位性、ひいてはビジネスの優位性を形づくるドライバーとして、EYでは「人材の健全性とフロー」「生成AIなどの職場テクノロジー」「トータルリワードの優先事項」「学習・スキル・キャリア成長」、そして「組織文化と働く場所」という5つの要素を定義しています。
一方サーベイでは、人材優位性は非常に重要なファクターですが、70%近くの企業が標準的、あるいは苦戦を強いられている――つまり、優位性を十分に確立できているとは言えない状況が明らかになりました。このまま手を打たなければ、さまざまなリスクに直面する恐れがあります。
水野「高いモチベーションを維持できなかったり、AIテクノロジーをうまく使うことができず、人材健全性が低下していく可能性があります。また、トータルリワードの優先順位を理解していない場合、応用が利かない偏ったスキル開発アプローチに陥り、従業員の経験と投資収益率にギャップが生じてしまいます。そして、分散した働き方の中で、文化を守り、発展させることが難しくなります」
5つの要素について掘り下げて見ていくと、さまざまな示唆が得られます。
まず人材の健全性とフローでは、人材の流入・流出が当然の前提となった今、もはや「離職率」は指標たり得ません。人材の健全性は、リワードや育成、文化、従業員が友人や家族に勤務先を推奨できるかどうかを数値化した「ネットプロモータースコア」が指標となりますが、業界によってばらつきが見えてきています。また、職場テクノロジーの活用やトータルリワードの設計に関しては、ビジネスリーダーと従業員との間で、意識に乖離が生じていることも見えてきました。
5つの要素を取り入れる鍵
では、こうした人材優位性を決定づける5つの要素をどのように確立し、自組織に適用していけばいいのでしょうか。
水野「人材健全性については、離職率だけに注目すべきではないことが挙げられます。またAIなどのテクノロジー活用においては、役割に応じた最適な導入の在り方を考えていく必要があります。トータルリワードに関しては、多様なニーズを踏まえて従業員の声に耳を傾けていく必要があり、学習・スキルアップや働く場所に関しても同様です」
そして何より、従業員とビジネスリーダーとの間にギャップがあることを意識した上で、変革が求められるとしました。

Section2
人手不足が深刻化する日本、キャリア自律や従業員体験が鍵に
サーベイからは、日本国内でもいよいよグローバル水準並みに人材流動性が高まり、従業員と雇用主のパワーバランスが変化していることが見えてきました。「キャリア自律」の推進や、従業員体験を通したネットプロモータースコアの向上といった取り組みが求められます。
日本では人手不足が深刻化
「Work Reimagined Survey 2024」では働き方に関するグローバルの動向が把握できますが、日本国内ではどんな特徴が見られるでしょうか。
水野「日本国内では人手不足が非常に深刻で、しかも慢性的に続いている状況です。失業率は2025年に2.4%へとさらに低下する見込みで、女性の就業率やシニア世代の転職希望者の割合は増加するなど、人材のフローは活発になっています」
事実、サーベイでは、従業員と雇用主との関係についてもグローバルの動向とは少し異なり、パワーバランスが従業員寄りとなっており、従業員がより良い労働環境を求めやすい状況にあることがわかりました。また、過去数年は低い傾向にあった「退職の可能性」も、最新のサーベイではグローバル水準にまで高まってきています。
多様な従業員ニーズと企業に求められる学びの環境整備
人材優位性を確保する5つのポイントについても、いくつか留意すべき差異が見られました。
まず注目したいのは、人材健全性を示すスコアの差です。グローバルでは従業員の50%以上がスコア8以上と回答した一方、日本ではスコア8以上はわずか19%にとどまり、グローバルに比べ後塵(こうじん)を拝している状況が明らかになりました。
またトータルリワードについては、多様なニーズの存在が明らかになりました。報酬にはいわゆる基本報酬やストックオプションの他、福利厚生などさまざまな形がありますが、日本では特に「物価を反映した総報酬」が重視される傾向があり、賃上げへの期待が高いことが明らかになっています。
そして学習・スキル・キャリア成長については、従業員が、自分が取り組みたい業務をベースに会社を選び、チャレンジしていく「キャリア自律」というキーワードが着目されています。しかしサーベイからは、それを支えるリスキリング環境がまだまだ進んでいない状況が見えてきました。
水野「従業員自ら、キャリア目標に対して必要なスキルを習得したいというニーズは確実にある一方で、企業としては対応が十分にできていないといった問題がありそうです」
活発化する海外リモートワーク活用の動き

グローバルモビリティリーダー EY税理士法人 パートナー 藤井 恵
組織文化と働く場所に関しても興味深い結果が見られました。
藤井「日本企業の66%がリモートワークをサポートしたいと考えています。それも、国内でのリモートワークに加え、勤務先の会社の所在する国と働く人の所在する国が異なる『海外リモートワーク』への関心も高まっています」
国をまたいだリモートワークに関しては、税務、そして労務問題や就労許可など、コンプライアンスの観点で検討すべき点が存在しますが、EY税理士法人の調査によると、国をまたいだリモートワーク、いわゆる「バーチャルアサインメント」について、ケース・バイ・ケースで検討していきたいと回答した企業も50%に上りました。しがたって、リスクをコントロールしながら、できる範囲で海外リモートワークを活用する動きは徐々に広がっていくものと見られます。
高まる転職意欲、日本企業に必要な施策は?
そして「自社が、リーダーシップや競争力のある報酬、高い従業員エンゲージメントといった豊かな企業文化を有している」と認識している割合は、日本は39%にとどまり、グローバルに比べて20%も低い結果となりました。
このように日本でも転職意欲が高まり、人の出入りがグローバル並みに活発化している中では、あらためて人材の健全性を示す指標としてのネットプロモータースコアが重要になると言えるでしょう。
水野「従業員自身が自社のネットプロモータースコアを上げる役割を果たしてもらうために、どのような従業員体験を提供していくのかを戦略的に考え、意図的に仕掛けていくことがこれから必要になっていくでしょう」

Section3
カルチャーを軸に、従業員体験を高め人材優位性を高めるMars
米国の大手消費財メーカー、Marsは、スナックやペットケア、小売など幅広い事業を展開していますが、「カルチャー」を軸に人材優位性、競争優位性を獲得しています。アソシエイト(従業員)のニーズも踏まえながら、「経験ファースト」という考え方で採用・オンボーディングプロセスを設計しています。
先ほど紹介した5つの要素を考慮しながら人材優位性を獲得している企業は、どんなことを意識しながら取り組んでいるのでしょうか。動画を通して、米国と日本を代表して2社の人事担当者が登場しました。
1人目は、米国の大手消費財メーカー、MarsのGlobal Talent Programs Director、Kelly Bartkiewicz氏です。

「カルチャー」を要に急成長
MarsはMars家がオーナーの非上場企業です。M&M’S、スニッカーズといったスナック類だけでなく、ペットケアサービスや小売業にも進出するなど事業の幅を広げ、同時にグローバル展開も図ってきました。Bartkiewicz氏が入社した1990年代前半には2万5,000人程度だったアソシエイト(従業員)は、今や全世界で15万人を超えるまでに成長しています。
こうした大企業で人材優位性を獲得し、成長を遂げる要は、まず「カルチャー」だとBartkiewicz氏は強調しました。
Bartkiewicz氏「5代目のJonathan Marsが『カルチャーとは、Marsのユニークな競争優位性を位置付けるものです』という言葉を残した通り、カルチャーはMarsそのものです」
幅広い事業ポートフォリオはすべて、1つのカルチャーという「同じ屋根の下」にいるというわけです。
多様な人材のオンボーディングは「経験ファースト」を重視
その上で、サプライ担当者やセールス担当者など多様な人材の採用・人材育成活動に取り組んできました。事業も業務内容も異なれば、地域も異なるため、Marsのオンボーディングは複雑なマトリックスになっていましたが、EYの協力を得ながら、アソシエイトを理解すること、そして「経験」を重視しながらプロセス自体を変革していきました。
Bartkiewicz氏「新入社員だけでなく、他の部門から移動してきた人も含め、どのような経験をしてほしいかという『経験ファースト』(Experience First)の考え方を重視しました」
誰にとっても入社時のオンボーディング体験は記憶に残るものです。このプロセスを通して互いを知り、人のつながりを構築していく経験が、Marsという企業の仲間意識や文化を熟成させてきました。さらに、以前からのレガシーを受け継ぎつつ情報共有やコラボレーションの方法などを改善し、ワークプレースとワークスペースをともに進化させています。
Bartkiewicz氏「大事にしているのは、初心に立ち返ることです。アソシエイトの住む地域や働き方に合わせ、どのようなオンボーディング経験やスキル開発経験をしてもらいたいかをデザインし、人材戦略を推し進めていくのです」
こうした取り組みを通して、「Marsで働くとはどういうことか」というナラティブを共有し、レピュテーションを高め、どんな成長やチャンスが得られるのかを伝えているそうです。

Section4
キャリアオーナーシップにこだわり人材マネジメント変革を進めるパナソニック コネクト
パナソニック コネクトは生産性や人材流動性の向上を目指し、責任と権限を明確にするポジションベースの人材マネジメント変革を、カルチャー&マインド改革の一環として推進しています。一人一人が自分のキャリアを考え、知識を身につけ、会社に依存することなく貢献していく仕組みを整備しています。

執行役員 ヴァイス・プレジデント CHRO 新家 伸浩 氏
旧体質からの脱却、イノベーション体質への変革
パナソニック コネクトでは数年かけて、人材マネジメント変革に取り組んできました。風土改革(カルチャー&マインドの変革)の一環として進めてきた同社の人事制度改革は、「キャリアオーナーシップ経営AWARD 2024」の最高賞であるグランプリを受賞しています。
パナソニック コネクトで執行役員 ヴァイス・プレジデント CHROを務める新家伸浩氏によると、同社の人材マネジメント改革は、生産性向上と人材流動性の向上を目指して始まりました。
新家氏「日本企業はどうしても、改善の積み重ねによる小さな差別化を重視しがちです。この結果、責任と権限の所在が曖昧になり、マネジメント体制も脆弱(ぜいじゃく)になります。結果として報酬も上がらず、生産性も上げなくていいのではないかという文化がはびこる負のスパイラルが回ってしまいます」
加えて、長期雇用・年功序列を前提とした人事制度の下では、イノベーションを引き起こして高い生産性を目指すというモチベーションが働きにくいのも事実です。パナソニック コネクトではこうした状態からの脱却を目指し、人材マネジメントの改革に取り組み始めました。
当事者意識を育む自律的キャリア支援
ただ、この取り組みは一朝一夕でなされたものではありません。2017年からEYの支援も得ながらまず着手したのが、カルチャー&マインド改革でした。その上で、責任と権限を明確にするポジションベースの人材マネジメントを2023年からスタートしました。
新家氏「一人一人が自分事として業務を捉え、自分のキャリアをしっかり考えながら取り組むため、ラーニングカルチャーやキャリアオーナーシップにこだわってマネジメントしています」
人材マネジメント改革を通して組織の中にさまざまな機会があることを示し、人事部門の伴走を受けながら、社員それぞれが一人の人間として知識を身につけ、会社に依存することなく貢献していく仕組みを整備しています。
今後はスキルベースの人材マネジメントへ
並行して、魅力あるマネージャーの育成や人事部門自体の改革、ギグワーカーやフリーランスとのコラボレーション、そして世界中から人を集めていくために必要な人事制度の整備などにも取り組み、企業としての成長を加速させていく方針です。
新家氏「人をどう組み合わせるかというよりも、スキルに着目し、そこを組み合わせながら価値に貢献していくようなスキルベースの人材マネジメントへの切り替えに着手していかなければと考えています」
一連の取り組みに終わりはないと新家氏は言います。AIをはじめとするテクノロジーを活用したHRの変革にも着手しつつ、パナソニック コネクトでは引き続き、グローバライゼーション、そしてスキルベースの変革を推進し、世界で戦うために最適な人材、最適なスキルを育成し、世界に存在感を示す企業を目指していきます。

本セミナーのアーカイブを配信中です。ぜひご覧ください。
Work Reimagined 2024 in Japan 未来の人材力を形づくる人材ダイナミクスと人材フローにどう向き合うべきか
(配信期間:2025年12月18日まで)
サマリー
「Work Reimagined Survey 2024」によって、キャリアの築き方やトータルリワードの考え方、働く場所など多くの面で働き方が変化していることが明らかになりました。人材優位性を獲得するには、5つのドライバーに留意しながらの人材マネジメント変革が必要となり、事実、Mars社やパナソニック コネクト社のように、先進的に取り組んでいる企業も存在します。
関連コンテンツのご紹介
従業員の間に不安や抵抗感が残る中、AIは価値創出へ前進できるのか?
EY 2025 Work Reimagined surveyの結果から、AI導入を変革的な成果につなげるには、テクノロジーと人材の両面が不可欠であることが明らかになりました。
場所に縛られない働き方の増加は未来の人材の在り方をどう塗り替えるか?
仕事の在り方は、キャリア、リワード(報酬)、働く場所などにおいて従来の価値観とは異なるものへと変化しています。人材の優位性について詳しくは、EY 2024 Work Reimagined Surveyをご覧ください。
EYの関連サービス
-
EYのトータルリワード(人事制度・福利厚生・働き方)のプロフェッショナルは、人材に関する戦略の一環として、総合的な報酬の評価、またはその再構築や再設計の支援を行います。詳しい内容を知る
続きを読む -
日本でもDX(デジタルトランスフォーメーション)ブームに加え、「新しい資本主義の実現」構想で人・技術・スタートアップへの投資が示され、リスキリングの重要性が高まっています。一方で、業種・業界やその企業の置かれた状況により、DX人材の獲得や育成が加速しない、または着手できないなどの困難に直面しているケースが増えています。私たちの考える講ずべき手段、および効果的なアプローチについてご紹介します。
続きを読む -
EYでは、ビザや労働許可の取得をはじめとした入国管理におけるコンプライアンス対応から、入国管理局との折衝やスポンサーシップの支援、書類認証代行サービスまで、海外赴任など国際的な人材移動に関する包括的なソリューションを提供しています。
続きを読む