EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
グループ法人税制に関する税効果会計 第2回:グループ内資産譲渡についての税効果
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 七海 健太郎
EY税理士法人 アシスタントマネージャー 發知 謙次
1. 税務上の取扱い(設例)
100%グループ内の譲渡損益調整資産の譲渡により発生した損益は譲渡法人において、税務上、繰り延べられます。【設例2】においては、×1年にA社がB社に資産を譲渡した時点で、会計上は売却益600が計上されますが税務上は益金として認識せず(減算・留保)、A社において課税の繰り延べを行います。その後、B社からC社に資産が譲渡された時点(【設例2】においては×2年)で、A社において600が課税されることになります。
ここで【設例2】ではC社が100%グループ内の法人ではないという前提があるため、×2年にB社で計上される会計上の売却益400は同時に税務上も益金として認識されますが、仮に譲受法人であるC社が100%グループ内の法人であるとした場合には、今度はB社が譲渡法人として売却益400を税務上繰り延べることとなります。なお、C社が100%グループ内法人であるか否かに係わらず、×1年に繰り延べられたA社の売却益600は、B社からC社に資産が譲渡された時点で税務上益金として認識されます。
【設例2】
<前提>
- A社、B社は100%グループ内。C社は100%グループ内の会社ではない。
- ×1年に、A社からB社へ土地を譲渡。A社では会計上売却益を600 計上。
- ×2年に、B社からC社へ土地を譲渡。B社では会計上売却益を400 計上。
- 譲渡された土地(A社での簿価2,000)は譲渡損益調整資産である。
- 法定実効税率は35%とする。
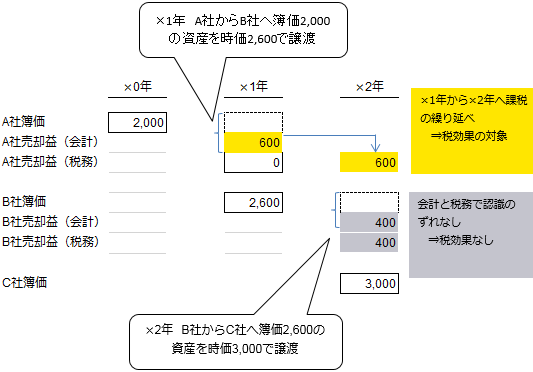
2. 会計上(個別)の取扱い
個別財務諸表上は、100%グループ内の資産譲渡に伴い、売却損が繰り延べられる場合には、課税所得の計算上加算され、将来の課税所得計算上で減算効果が生じることになるので、将来減算一時差異として税効果の対象になり、売却益が繰り延べられる場合には将来加算一時差異として、税効果の対象となります(個別税効果実務指針第8項、第10項、第33-2項)。
【設例2】においては、A社の会計処理は以下のとおりです(なおB社については、会計と税務の認識にずれがないため、税効果の認識はありません)。
①×1年
A社において税務上は売却益600が繰り延べられているため(税務上の簿価が売却前の2,000のまま)、A社の個別財務諸表上、将来加算一時差異600に対して、繰延税金負債210(600×35%)を計上します(法人税等調整額は費用側)。
②×2年
A社において税務上繰り延べられていた売却益600が認識されることによって、A社の個別財務諸表上、×1年に発生した将来加算一時差異600が解消するため、繰延税金負債210を取り崩します(法人税等調整額は利益側)。
【設例2】での損益計算書抜粋(単体)
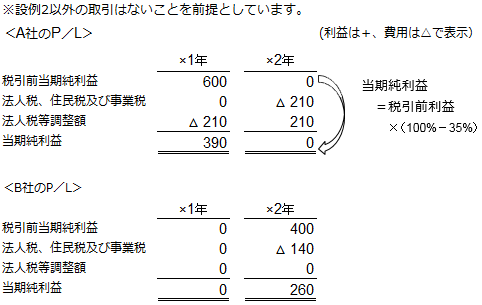
なお100%グループ内の資産譲渡に係る税務上の損益繰り延べは、税効果の対象となる点で、連結上の未実現損益の調整と類似していますが、以下のとおり相違があります。
|
100%グループ内の資産譲渡に係る税務上の損益繰り延べ |
連結グループ内の資産譲渡に係る未実現損益の調整 |
||
|---|---|---|---|
|
一時差異の種類 |
個別財務諸表の一時差異 |
連結財務諸表固有の一時差異 |
|
|
考え方 |
資産負債法 |
繰延法 |
|
|
税率 |
売手側の、将来回収・支払が行われると見込まれる時点の税率 |
売手側の、譲渡時点の税率 |
|
|
回収可能性の検討 |
|
回収可能性の検討は不要(※) |
(※) ただし、次の制限があります。
- 未実現利益の消去に係る将来減算一時差異の額は、売手側の売却年度における課税所得額を超えることは出来ません。
- 未実現損失の消去に係る将来加算一時差異の額は、売手側の当該未実現損失に係る損金を計上する前の課税所得額を超えることは出来ません。
3. 会計上(連結)の取扱い
税務上繰り延べられた損益は、基本的には、連結財務諸表上においても消去されることになりますので、繰延税金資産及び繰延税金負債は認識しません(連結税効果実務指針第12-2項)。
【設例2】においてA社とB社の連結財務諸表を作成するとします。A社の繰り延べられた売却益600を将来加算一時差異と認識し、繰延税金負債を計上します。しかし、連結財務諸表では売却益600は未実現利益として消去されることになりますので、個別財務諸表上で計上した繰延税金負債を取り崩します。結果として、税効果は認識されないこととなります。
<それぞれの簿価の関連イメージ図>
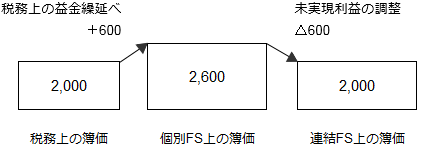
ここでは譲渡損益対象資産のA社での簿価2,000(B社での簿価2,600とA社における調整資産△600の合計)を税務上の簿価と称しています。
<損益計算書抜粋(連結)>
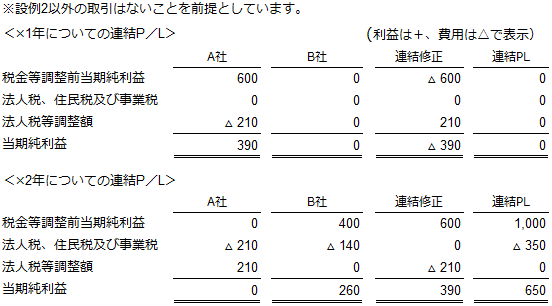
4. 減価償却資産の取扱い
100%グループ内での譲渡資産が建物などの減価償却資産である場合、譲渡会社で繰り延べた譲渡益・譲渡損の分だけ、譲受会社での減価償却の基礎となる取得原価が税務上過大・過小になっていることになります。よって、譲受会社で実施する減価償却の金額も過大・過小になっており、その譲受会社の減価償却に伴い、譲渡会社が税務上繰り延べている譲渡損益を戻入れることとなります。
譲受会社の減価償却に伴う譲渡会社での戻入額の計算方法には、以下の二つの方法があります(国税庁ウェブサイト「平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)」を参照)。
① 原則法
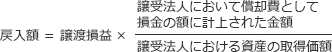
② 簡便法
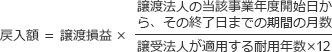
【設例3】
<前提>
- ×1年期首に、P社は100%連結子会社のS社へ機械(会計及び税務上の簿価2,000の譲渡損益調整資産)を時価3,000で売却。
- S社は機械を×1年期首から5年(中古資産に係る税務上の耐用年数)で使用。
- それ以外の取引はなし。
- 税務上、以下の表("P社・売却益・税務"欄)のとおり、売却益1,000は簡便法で戻入れ計算を行う。
- S社は 、耐用年数5年・残存価格ゼロで定額法の減価償却を行う。
- 法定実効税率は35%とする。
- S社の欠損金について、繰延税金資産は計上可能なものとする。
|
P社 |
S社 |
連結調整 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
売却益
|
会計と税務の |
税効果 |
減価償却 |
未実現利益の調整 |
税効果の調整 |
|||
|
×1年期首 |
|
1,000 |
350 |
0 |
△1,000 |
△350 |
||
|
×1年末 |
|
(B)800 |
280 |
△600 |
200 |
△280 |
||
|
×2年末 |
|
600 |
210 |
△600 |
200 |
△210 |
||
|
×3年末 |
|
400 |
140 |
△600 |
200 |
△140 |
||
|
×4年末 |
|
200 |
70 |
△600 |
200 |
△70 |
||
|
×5年末 |
|
0 |
0 |
△600 |
200 |
0 |
<会計上の仕訳>
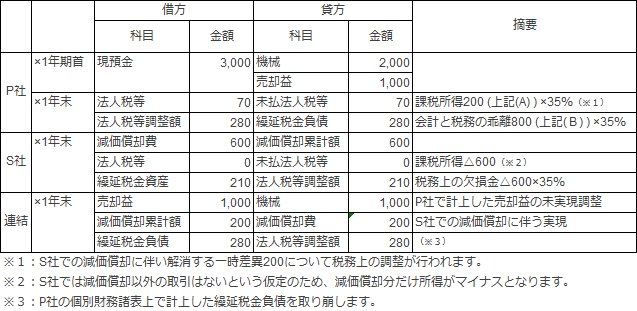
<損益計算書抜粋>
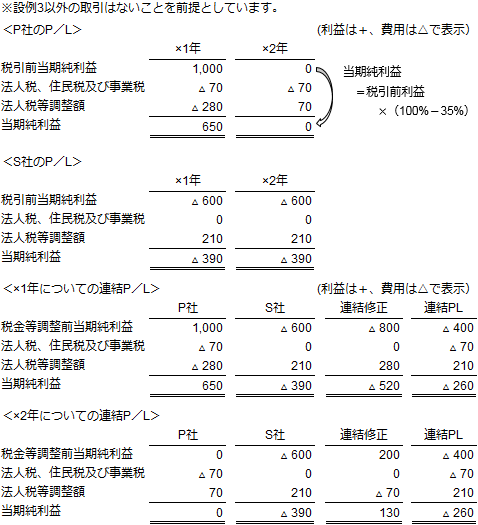
5. グループ内投資(子会社株式など)の取扱い
100%グループ内での譲渡対象資産が子会社株式などの有価証券である場合も、譲渡損益調整の対象となります。つまり、個別財務諸表では、会計上、売却損益が計上されるのに対し、税務上は益金・損金に含まれず、課税の繰り延べが行われます。この一時差異について、子会社への投資に係る一時差異のような特則(予測可能な将来、売却の意思決定が明確な場合等を除き、税効果を認識しない)はありませんので、税効果を認識します。
この個別財務諸表上の一時差異について、連結財務諸表上も修正されないことから、個別財務諸表において認識された税効果についても、特に調整せず、引き続き計上されることとなります(連結税効果実務指針第30-2項)。
【設例4】
<前提>
- P社、A社、B社は100%グループ内の会社であり、連結会社。
- ×1年に、A社からP社へB社株式を譲渡することを意思決定。
- ×2年に、A社からP社へB社株式(簿価1,000)を1,600で譲渡。A社では会計上売却益を600 計上。
- B社の連結上の簿価は1,200とする。
- P社にてB社株式を売却する予定はないものとする。
- 法定実効税率は35%とする。
<会計上の仕訳>
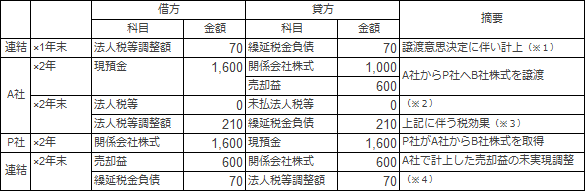
※1: 連結上の簿価1,200と個別FS上の簿価1,000との差額 200×35%
(投資についての単体での簿価と連結上の簿価とに差額がある場合、一時差異となり、売却の意思決定によって税効果を認識します)
※2: グループ内法人間の資産譲渡による損益の繰延べにより所得ゼロ
※3: 譲渡益の繰り延べに係る税務上の調整負債に係わる繰延税金負債 600×35%
(譲渡益の繰り延べに係わる税務上の調整負債に係わるA社個別財務諸表上の税効果です、これは連結上も、特に調整されません)
※4: ×1年に譲渡が意思決定されたことによるC社留保利益に係る税効果の戻し
なお、P社においてB社株式を売却する予定がないことから、P社の取得価額1,600と連結上の簿価1,200の差額に係わる一時差異については、税効果を認識しません。
この記事に関連するテーマ別一覧
グループ法人税制に関する税効果会計
- 第1回:グループ内寄付に係る税効果、グループ内資産譲渡についての税務上の取扱い (2019.09.06)
- 第2回:グループ内資産譲渡についての税効果 (2019.09.06)




