EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

情報センサー 2017年5月号 EY Institute
EY総合研究所(株) 未来経営研究部 上席主任研究員 深澤寛晴
一橋大学経済学部卒業後、大手日系シンクタンクに入社。エコノミスト、通商産業省(現経済産業省)出向などを経て、2001年より外資系投資顧問会社にて年金営業支援業務。04年より大手日系シンクタンクにて企業財務戦略部フィナンシャル・アナリストなどを歴任。14年9月EY総合研究所(株)入社。コーポレートガバナンスなど、資本市場対応全般を専門分野とする。
Ⅰ なぜ今、敵対的買収か
近年、日本再興戦略に沿ったコーポレートガバナンス(CG)改革が進められており、2015年6月にはCGコードがスタートしています。日本ではCGを敵対的買収と結び付けて議論するケースは少なく、CGコードも買収防衛策および株式の公開買い付け(TOB)に言及するにとどめています。しかし、現実にCGが最も端的に問われるのは株主と経営陣が対立する局面であり、敵対的買収はその典型です。実際、米国ではCGを担う筆頭独立取締役が敵対的な買収者と直接交渉することも珍しくありません。CGコードへの初期対応が一巡した今日、独立社外取締役の人数や比率が従前とは大幅に異なる水準に達するなど、日本企業は新たな「CGコード時代」とも言えるステージに入っています。敵対的買収およびそれに対する備えを再考するとともに、CGの実効性向上に対する示唆を得る好機と言えるでしょう。
以下、敵対的買収について、これまでの経緯や現状を概観した上で、CGとの関係を含めて解説し、今日の日本企業に求められるものについて解説します。なお、本稿では、経営陣の賛同を得ずに株式(議決権)の過半数を取得する行為だけでなく、いわゆるアクティビストを含む非友好的な株主と経営陣が対立するケース全般を敵対的買収とし、株主側の要求が実現されることをもってその成立とします。
Ⅱ これまでの経緯と現状
1. これまでの経緯
従前、日本企業は株式持合いに代表される安定的な株主構成に守られ、経営陣と株主が対立するケースは稀(まれ)でした。しかし、1990年代以降、持合い解消と外国人株主の増加が進むと、徐々に状況は変わります。2000年前後から00年代半ばにかけて、主に金融資産や不動産を多く保有する企業がアクティビストのターゲットになり、中には敵対的TOBが行われたり、株主と経営陣の対立が裁判に持ち込まれたり、といった事例も見られました。加えて、欧米で大型のM&Aが相次いだため、これにより誕生した巨大企業が日本企業の買収に動くのではないか、といった危機感も高まりました。そこで注目されたのが買収防衛策です。特に06年以降は買収防衛策を導入する企業が相次ぎ、08年末時点では569社※1にまで達しました。
しかし、金融危機を受けて外国人株主比率が低下に転じ、アクティビストを含むM&A活動全般が停滞すると、敵対的買収に対する日本企業の危機感は急速に薄れます。買収防衛策の新規導入はピークアウトし、逆に廃止(非継続)するケースが目立つようになりました。
このようなトレンドを変えるきっかけとなったのが、12年12月の安倍晋三政権の誕生です。直後から為替が円安に振れたこともあって、低迷を続けていた株価は急回復、外国人株主は増加に転じます。大手公的年金が国内株式の資産配分を大幅に引き上げたこともあり、安定株主から機関投資家の株主へという流れが加速しています。
特に注目すべきは、同政権によるスチュワードシップ(SS)・コードおよびCGコードという「2つのコード」の導入です。SSコードは機関投資家に対してエンゲージメント(目的を持った対話)や議決権行使を要求しており、今日では日本で活動する機関投資家(運用機関)の大半が同コードの受入れを表明しています。CGコードは企業に対して株主と対話することを要求しており、この「2つのコード」が両者の関係を大きく変える可能性があります。
2. 敵対的買収リスクの現状
近年、再びアクティビストの活動が活発化していますが、00年代とは異なり、敵対的なTOBのような強行策は避ける傾向があるようです。典型的なのが、株式の保有比率を低めに抑えて高圧的な印象を与えないようにした上で、企業価値向上のためのストーリーを策定・公表し、その一環として企業に対する要求を行うといったパターンです。他の機関投資家が同調すれば、保有比率は低くても企業に対する影響力は軽視し難いものになります。このストーリーが合理的であれば、SSコードを受け入れている機関投資家がエンゲージメントや議決権行使を通じて同調する可能性は十分にあります。ストーリーに基づいた具体的な要求の内容としては、増配や自己株式の取得に加え、事業構造が複雑化している企業に対して事業の切り離しなどの対応を求めるといったものも散見されます。
一方、業種によっては、いわゆるストラテジック・バイヤー※2による敵対的買収リスクの高まりも見られます。欧米において事業の成熟化や第4次産業革命のような新しいトレンドに対応するため、大規模なM&Aによる再編が進んでいるケースが典型的です。規模の大きい欧米企業が買収後の明確な成長戦略を携え、日本企業に対して敵対的買収を仕掛けてきた場合には、アクティビスト以上に対応が困難になる可能性があります。
Ⅲ 敵対的買収とは
1. (敵対的)買収のプロセス
(敵対的)買収のプロセスを<図1>に沿って確認しましょう。買収防衛策を導入する企業でも導入しない企業でも同様です。まずは買収者による(1)買収提案です。買収者からのアプローチはさまざまで、見ず知らずの買収者から唐突に買収提案を含む書簡が送られてくることもあれば、事前に水面下での打診があることもあります。これに基づき買収者との(2)交渉が始まりますが、その過程で(1)'買収提案が修正されることもあるでしょう。交渉が(3)決裂し、かつ買収者が断念しない場合には(4)強行策に移行します。最も分かりやすいのが、買収者側が敵対的なTOBに踏み切り、企業側が株式の第三者割当てや新株予約権の無償割当てといった対抗措置を発動する、といったパターンです。買収者が対抗措置について差し止め請求を行って法廷闘争に発展する、あるいは株主総会での議決権を巡り委任状争奪戦が行われる、といった展開も想定されます。最終的には、敵対的買収の成立あるいは買収の断念といった「勝ち負け」に帰着します。
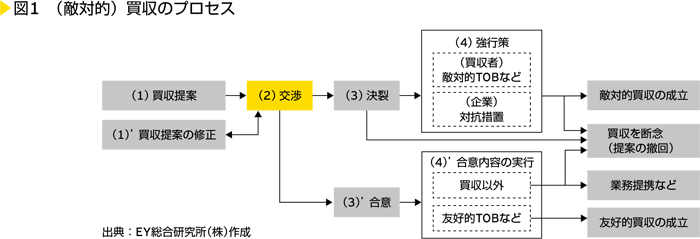
一方、交渉を経て(3)'合意に至れば、Win-Winの決着となります。最も分かりやすいのは友好的買収の成立ですが、その他にも買収提案の撤回や業務提携といった買収以外の内容での合意も想定されます。実際には、決裂から強行策に至るのを回避し、交渉と買収提案の修正を繰り返す中で合意を目指すのが通常です。敵対的買収では(4)強行策が注目されるケースが多いのですが、実際に最も重要なステップは(2)交渉と言えるでしょう。
2. 買収防衛策の意義
前述の通り、従前、敵対的買収への備えとして注目されたのは買収防衛策です。ピークに比べ減ってはいるものの、16年末時点で450社※3が導入しており、軽視し難い存在と言えます。ここでは、その意義について確認しましょう。
「買収防衛」という語感から、対抗措置(通常は新株予約権の無償割当て)によって敵対的な買収者にダメージを与え、企業(経営陣)を守るためのもの、といったイメージを持たれがちですが、そうではありません。その意義は濫用的な買収者から企業価値および株主共同の利益を守ることにあります。そのため、買収防衛策は取締役会および(買収者を除く)一般株主が、買収者が濫用的か否かを合理的に判断できるよう、買収者が守るべき手続きを定めるとともに、濫用的と判断した場合の対抗措置を示す内容になっているのが通常です。
なお、企業側が対抗措置を発動すれば、買収者は差し止め請求により法廷闘争に持ち込む可能性が高く、その場合には双方に費用面・時間面の負担が生じる上、差し止め請求が認められるリスクも否定できません。明らかに買収者が濫用的なケースを除くと、軽々に対抗措置を発動することは企業にとって得策でない点に留意する必要があります。買収防衛策を導入する場合であっても、対抗措置の発動に依存するのではなく、対抗措置を示すことで買収者をけん制して拙速な買収提案を予防し、買収時の手続きを定めることで買収者と交渉するための十分な時間・情報を確保するためのツールと考えるべきです。
3. CGの重要性
敵対的な買収提案が行われた場合、経営陣と買収者のどちらがより企業価値を高め、株主共同の利益に資することができるか、といった判断が重要になります。最終的な判断は一般株主に委ねられますが、一般株主がアクセスできるのは公開情報に限定されるため、非公開情報を考慮した判断が示されれば、それは一定程度尊重されます。最も非公開情報に近いのは経営陣ですが、買収が成立すれば経営陣は交代を迫られる可能性があるなど、敵対的買収は経営陣自身の立場・利害に大きな影響を与える可能性があるため、客観的かつ公平な判断を行うのは困難です。
非公開情報を考慮し、かつ経営陣から独立した立場で判断することを可能にする仕組み、それがCGであり、その主たる担い手が独立社外取締役です(<図2>参照)。欧米では、敵対的買収の際に被買収企業の取締役会が重要な役割を担うことが多く、一般株主はその判断を尊重する傾向があります。しかし、その背景には取締役会の独立性が高く(独立した取締役が大半を占める)、取締役会で客観的かつ公平な判断が期待できることがあります。これに比べると、日本企業の取締役会の独立性は高いとは言い難いのが通常ですが、独立社外取締役を最大限に活用することで、判断の客観性・公平性を高めることが重要です。
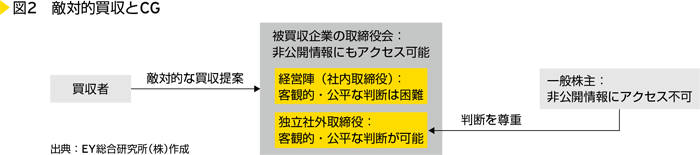
日本企業の買収防衛策では独立委員会を設置し、前記の判断について諮問するのが通常ですが、これが必要とされるのは、大半を経営陣(社内取締役)が占める取締役会では公平な判断が困難なためです。CGが有効に機能しない場合、例えば同委員会の答申を経営陣中心の取締役会が十分に尊重しない場合には、法廷闘争に持ち込まれた場合に不利になる、あるいは一般株主の支持を得られない、といった事態も想定されます。最近では独立社外取締役が独立委員会のメンバーとなるケースが増えていることもあり、買収防衛策を導入する企業でも、導入しない企業でも、CG、特に独立社外取締役が重要な役割を担う点で変わりがないと言えます。
Ⅳ 敵対的買収への備え:日本企業には何が求められるか
最後に、敵対的買収への備えとして日本企業に求められるものについて解説します。
1. 独立社外取締役の確保
まず必要なのが、独立した立場から前述の判断を行う独立社外取締役の確保ですが、これについては、近年、相当の進展が見られます。主要企業(TOPIX500採用企業※4)についてアベノミクス直前の13年と直近(17年2月末)を比較すると、独立社外取締役の平均人数は1.5名から2.7名、同人数が2名以上の企業は41%から94%、同比率が3分の1以上の企業は12%から30%へと増加・上昇しています※5。冒頭で述べた通り、日本企業は一定数・比率の独立社外取締役の設置を前提とした「CGコード時代」に突入したと言えるでしょう。
2. 企業価値向上策の共有
次に求められるのが、独立社外取締役が適切な判断を行うための材料、すなわち企業価値向上策を共有することです。独立社外取締役はその判断に際し、経営陣と買収者の企業価値向上策を比較します。買収者が実現する企業価値は買収価格に他ならないため、経営陣は買収価格を上回る水準まで企業価値を向上させる策を示す必要があります。敵対的買収という事態に直面し、慌てて企業価値向上策を策定して独立社外取締役に説明しているようでは、買収者との交渉が後手に回りかねません。平時から企業価値向上策を策定するだけでなく、同策の内容と進捗(しんちょく)状況や課題、さらには同策の実現を想定した企業価値について、独立社外取締役と共有しておくことが求められます。策定の過程から独立社外取締役に説明し、意見を得るプロセスを経ておくとスムーズでしょう。
そもそも、企業価値向上策が全て株価に反映されていれば、(特にアクティビストによる)買収リスクは大きく低減するはずです。IR(インベスター・リレーションズ)を通じて企業価値向上策を株式市場に伝えられているか、再確認することも重要です。
3. 事務局の体制整備
Ⅳ 1. 2.は経営陣や独立社外取締役の役割ですが、それを実務的に支える事務局が担う役割も重要です。買収者との交渉において社内外から情報を収集して分析を行い、状況に応じた対応案を策定して経営陣や取締役会に諮るのは事務局の役割です。社内の関連部署(企画・財務・IR・総務・法務など)に加え、外部アドバイザーとの連携においても中心的な役割を担います。短期間での対応を迫られるケースが少なくないこともあり、平時からの敵対的買収への備えとして、事務局の体制整備は不可欠と考えられます。例えば、社内規定を整備し、関与する担当者や責任の所在・役割分担などを明確にしておくことが求められます。さらに、敵対的買収を想定したシミュレーションを行い、これらをブラッシュアップするのも効果的でしょう。
4. CGの実効性向上に生かす
前述のⅣ 1.~3.はCGの実効性に深く関わっています。特に独立社外取締役が企業価値向上策の内容と進捗・課題を共有するということは、プラン(P)とチェック(C)を通じて経営のPDCAを機能させるということであり、これは取締役会の監督機能に他なりません※6。CGの実効性が向上すれば、敵対的買収への備えも強固になるといった好循環につながります。また、この好循環が企業価値向上策を再点検するきっかけになることも期待されます。CGコード時代の敵対的買収への備えを、より前向きな取り組みとして考えてみる価値があるのではないでしょうか。
※1『MARR』((株)レコフデータ)より
※2事業投資家として自らの経営戦略にのっとり、必要な企業の買収を目指す買収者。アクティビストのように、自らの経営戦略とは無関係に、株価の割安性などに注目して買収を行う買収者は、フィナンシャル・バイヤー(金融投資家)と呼ばれる。
※3『MARR』((株)レコフデータ)より
※4対象は必要なデータを取得可能な490社。「日経バリューサーチ」より
※5CGコードは独立社外取締役について2名以上、3分の1以上という人数・比率の水準を示している。
※6拙著「取締役会が担うべき監督機能とは?~ 欧米企業のベスト・プラクティスを踏まえて」を参照



