EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

情報センサー2020年2月号 Digital Audit
品質管理本部 アシュアランステクノロジー部
公認会計士 市原直通
2003年、当法人入所。金融機関におけるデリバティブの公正価値評価やリスク管理に関する監査、アドバイザリー業務に従事。16年より会計学と機械学習を用いた不正会計予測モデルの構築・運用や監査業務におけるAI活用に関する研究開発に従事している。日本証券アナリスト協会 検定会員。
公認会計士 山本誠一
2008年、当法人入所。製造業、建設業、サービス業などの上場会社およびIPO関連業務の監査に従事。18年より仕訳の異常検知システム EY Helix GLADの開発・運用に従事し、Digital Auditの推進に取り組んでいる。
公認会計士 小島久人
2010年、当法人入所。製造業、農業などの上場会社および金融機関の監査に従事。19年より仕訳の異常検知システムEY Helix GLADの開発・運用に従事し、Digital Auditの推進に取り組んでいる。
Ⅰ はじめに
財務分析は投資や与信などその用途は幅広く、分析に用いられる指標もさまざまなものがあります。しかし、ほとんどの分析は貸借対照表と損益計算書、キャッシュ・フロー計算書に基づく分析であり期中の日々の財務の動きを捉えることはできないため、分析の粒度という観点では限界があります。一方で、昨今ビッグデータを取り扱うインフラが整い、また財務会計に関するサービスが広がり、対象企業の仕訳データが入手可能な状況も増えています。仕訳データはこれまでの財務諸表に記載されている集計値と比べ、はるかに詳細な情報である一方、どう分析するのかというノウハウは確立したものがありません。
当法人では2017年10月から独自の会計仕訳の異常検知アルゴリズムを開発し、17年11月から運用しています(18年6月に特許取得)。20年1月からはEYグローバルの仕訳の異常検知システム EY Helix General Ledger Anomaly Detector(GLAD)として世界中で展開され、国内外延べ350社以上で利用され、その運用を通じて仕訳を分析するノウハウを蓄積してきました。
本稿では、仕訳データをどういう切り口で見るとこれまでの集計値では分からなかった情報が明らかになるのか、高解像度な財務分析手法について紹介します。また、さらに高度な分析として仕訳データに異常検知などのアルゴリズムを適用する効果と限界や将来の展望についてお話したいと思います。
Ⅱ 分析対象データについて
本稿で分析例として示す図は、EYが米国で学生向けに開講しているデータアナリティクス講座の教材データを利用しています。この教材はあらかじめ不正な仕訳が組み込まれてあり、学生が財務分析により不正を見つけるというものです。本稿は必ずしも不正発見だけを想定して分析手法の紹介をしているわけではありませんが、一部の分析例において不正仕訳の影響により不自然な部分があることをご了承ください。
Ⅲ 期中の勘定科目の動きを捉える
分析に用いる情報の粒度が細かいほど、分析結果から深い理解が得られます。例えば、伝統的な財務分析で棚卸資産の回転期間が延びていたときに、期末の棚卸資産が大きいということは分かってもそれ以上の情報はありません。一方で、科目ごとの時系列分析を行い仕訳データから棚卸資産の動きを時系列で追うことで、一年を通じて取引量が増えたのか、期末に在庫が増えたのか、それとも期中の特定の日に何かがあったのかを把握することができます。
<図1>では棚卸資産の日次の借方計上額を赤線で、貸方計上額を青線で表しています。これを見ると、黄色の丸で囲んだところ(15年12月半ば)で大きな借方計上が起こっているのが分かります。
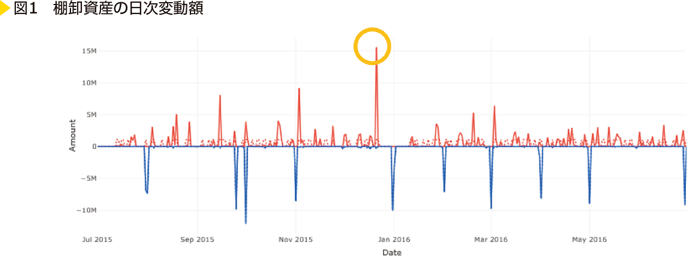
さらに<図2>のように年初からの日次の変動額を積み上げた累積を前年と比較すると計上パターンの変化も読み取れます。
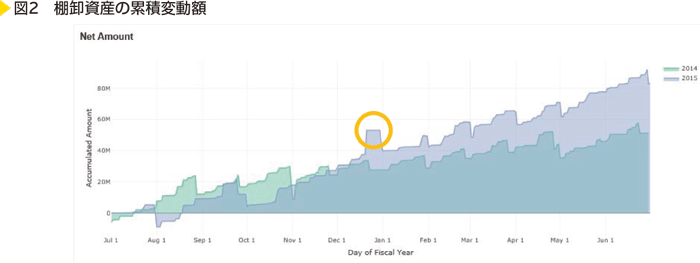
<図2>を見ると、15年12月半ばに大きな増加があり、期末に減少はあるものの年初からの累積額を比較すると1月以降前年よりも増加しており、その増加幅が年度末に向かうにつれて大きくなっていることが分かります。
同様に時系列の分析を売上高に対して行うことで翌期に不自然な赤伝票がないかを確認できます。さらに入力日を使った時系列の分析により売上高の前倒計上の可能性がある期末日後の多額の売上入力がないかを確認しやすくなります。
このように時系列分析により期中の勘定科目の動きを捉えることで勘定科目の変動の要因をより詳細に把握することができるようになり、不正発見にも役立ちます。
Ⅳ 仕訳の付帯情報と紐(ひも)付けて俯瞰(ふかん)する
もしも仕訳データに起票者や支店、取引種別、取引先などの情報が入力されていれば、こういった付帯情報を用いて仕訳起票者ごとや支店ごと、取引種別や取引先ごとにどの科目をいくら計上しているのかといった分析が可能になります。
例えば、投資判断や与信判断においてビジネスユニットごと、取引種別ごと、取引先ごとなどの観点で収益性を分析することができます。また、監査において不自然な動きに気付くことができます。<図3>は仕訳起票者をx軸、勘定科目をy軸とし計上金額をz軸に3次元グラフ(ヒートマップ)を表示したもので、このグラフから特定の仕訳起票者の計上した仕訳の中で計上額が大きい科目を見つけ、原因となった取引が何かについて深掘りをしていくというような活用が考えられます。
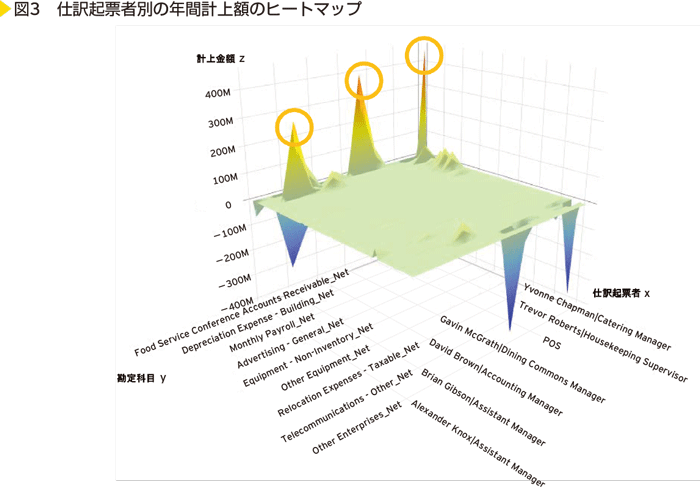
このように仕訳の付帯情報を紐付けた分析により、より立体的に企業活動を捉えることができるようになります。
Ⅴ 仕訳の付帯情報を紐付けた時系列分析
さらに今紹介した二つの分析手法を合わせることも考えられます。仕訳の付帯情報を用いて特定の仕訳を絞り込んだ上で時系列分析を行うことで、例えばビジネスユニットごとの各種段階利益や運転資本の時系列分析、前期比較、予実分析などが可能になります。
<図4>は営業利益が期首から期末までどう推移したのかを前年と比較する形で表したものです。通常、企業はビジネスユニットごとに利益責任を有していることから、ビジネスユニットごとに利益の時系列分析を行うことで、予算達成のために不自然な利益計上があった際に発見しやすくなります。つまりビジネスユニットごとに、どの日の影響により利益が増減しているのかを特定することができ、また前期と比較することや、予算と比較することで前期と異なる傾向や予算の達成度および予算達成のタイミングを把握することができます。例えば、第4四半期に急激に利益計上のペースが上がり、最後にぎりぎりで予算を達成したというような状況があれば視覚的に把握をすることができるのです。
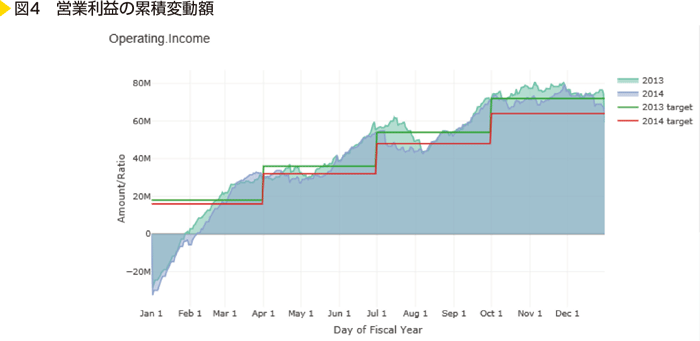
ビジネスユニットで仕訳を絞り込む代わりに取引種別や取引先などによって絞り込むことで収益の認識のタイミングやパターンを把握するといった使いみちも考えられます。また集計する科目を営業利益ではなく現預金、棚卸資産、売上、運転資本など様々な科目に着目することで、それぞれの時系列分析をすることも有用です。
Ⅵ 科目間の関係性の分析
仕訳の付帯情報の活用には他にもさまざまな方法が考えられます。例えば、<図5>はX軸(横方向)を売上、Y軸(縦方向)を売上原価とし、計上月ごとの売上・売上原価をグラフにプロットしたものになります。<図5>では1月が最も売上が少なくかつ売上原価が少ない月であり、逆に12月が最も売上が多くかつ売上原価が多い月であること示しています。グラフは左下にいくほど利益が多く、右上に行くほど利益が少なくなります。9月の売上は12月の売上ほど多くないものの、売上原価が少なくなっている結果、9月の利益が12月より多くなっていることが分かります。
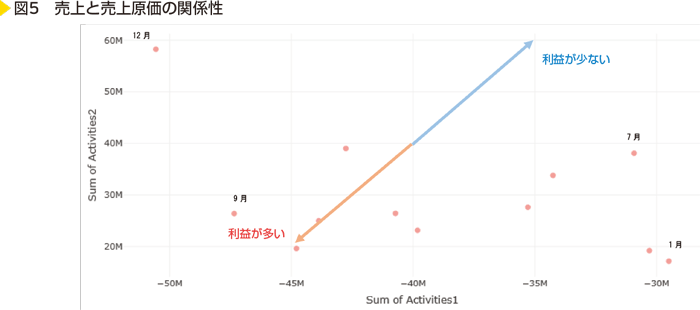
また売上と売上原価以外に、売上と売掛金、仕入と買掛金などの関係性など目的に応じた組み合わせによりさまざまな分析をすることができます。
<図5>では計上月の側面から二つの科目の関係性を視覚化しましたが、付帯情報として計上日、入力日などを用いた科目間の関係性のほか、同様の手法により支店ごと、商品ごと、取引先ごとの科目の関連性の分析により収益性の高いところを視覚的に把握する、また安全性を比較するといったことも可能となります。
支店ごとに二つの科目がどう関係しているか、取引先ごとにどう関係しているか、営業担当者ごとにどう関係しているかなどのさまざまな側面を用いることで「不自然な利益計上をしていることの多い取引先」「経費が不自然に多い営業担当」などを見つけて架空売上や架空経費の兆候の発見に役立てることもできます。
Ⅶ 科目間のつながりの分析
仕訳には借方と貸方でどの科目が使われたのかという情報があるため、そのつながりを分析し視覚化することで科目間を振り替えてどう売上が現金に変わっていくのか、また費用が原価になっていくのかといった理解が可能になります。これにより勘定科目の期末日での断面ではなく、勘定科目が期中を通じてどう他の科目と関連しているのかという立体的な理解が可能となります。
例えば一年を通じて次の仕訳が起票されたとします。
- 仕訳#1(借方)売掛金100(貸方)売上 100
- 仕訳#2(借方)売掛金 50(貸方)売上 50
- 仕訳#3(借方)現金 30(貸方)売上 30
- 仕訳#4(借方)現金 120(貸方)売掛金120
この四つの仕訳を借方・貸方の科目のペアごとに集計すると次のように集計できます。
(借方)売掛金150 (貸方)売上 150
(借方)現金 30 (貸方)売上 30
(借方)現金 120 (貸方)売掛金120
この借方科目・貸方科目の組み合わせをじっと見ていると、180の売上が30の現金と150の売掛金につながり、150の売掛金のうち120の売掛金は現金へとつながる、という連環に気づきます。
もちろん、この作業を実際の数千万行の仕訳を相手に人間がすることは無謀ですが、科目の組み合わせごとの金額を集計し、Sankey diagramで表示すれば<図6>のように科目の連環が視覚的に把握できます。
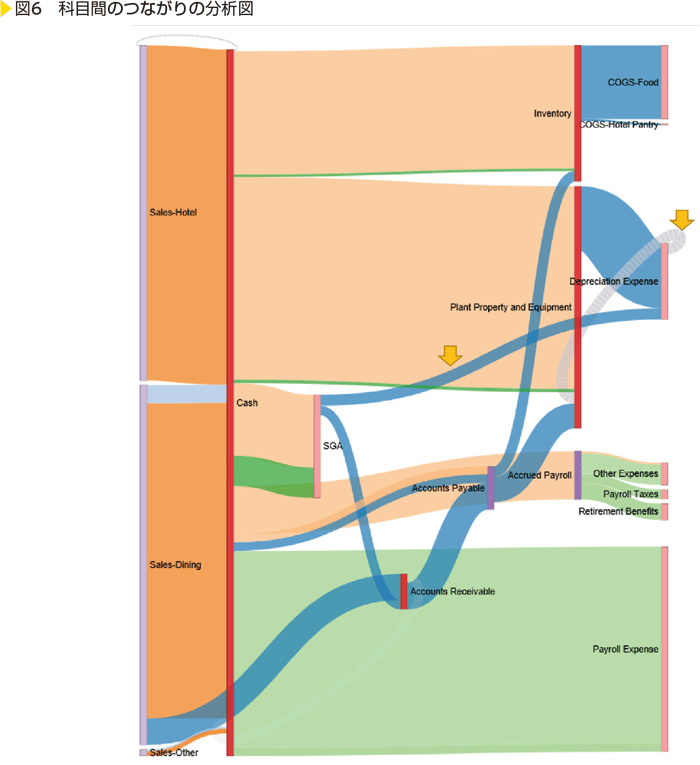
<図6>では縦棒が科目を表しています。縦棒と縦棒を結ぶ帯がその二つの科目が借方・貸方でつながる仕訳の金額的な大きさを表します。一番左側にSales-HotelとSales-Dining、Sales-Otherとありますが、これは三つの売上科目が使われていることを表します。これらの売上はSales-Diningの一部がAccounts Receivable (売掛金)とつながっていることを除けば全てその右隣のCash(現預金)と書かれた赤の縦棒とつながっています。
また、このCashとピンクの縦棒のSGA(販管費)がつながっていることが見て取れます。これは次の仕訳がこの帯の太さだけ計上されたということを表しています。
(借方)販管費 (貸方)現預金
この販管費からよく見ると濃い青い帯でDepreciation Expense(減価償却費)につながっていることが分かります。現金支出の販管費が減価償却費に振り替えられており、そこからグレーの帯でPlant Property and Equipment(有形固定資産)というところにつながっている、つまり、次の仕訳で最終的に現金支出が有形固定資産に振り替わっていることが分かります。
(借方)減価償却費 (貸方)販管費
(借方)有形固定資産 (貸方)減価償却費
Ⅷ 異常検知アルゴリズムの適用について
仕訳データを用いることで前述のようなより高解像度な分析が可能となり、今までに見えなかったリスクの発見に役立てることができます。一方で、科目数が多いと全ての科目の動きに目を通し、さまざまな科目の組み合わせごとにその関連性を確認するのは人間には酷な作業となります。
支店ごと、取引先ごと、商品ごとなどさまざまな切り口から勘定科目の計上パターンを学習し、通常と外れた動きを自動的に検出していくような技術の活用が今後重要になっていくと考えられます。
一方で、整理しなければならない論点も幾つかあります。例えば、異常検知されなかった部分についてどの程度の信頼度をもって問題ないと言えるのか、またこういったアルゴリズムによりどこまで人の検証を置き換えることが可能なのか、さらに監査法人が異常検知アルゴリズムを活用し日次で会社の取引をモニターするようになった場合に異常検知やその情報提供が企業の内部統制の一部とならないようにするためにはどういった仕組みが必要なのかなどの議論が起こっています。
Ⅸ おわりに
ITインフラの発達により、今後仕訳データなどの粒度の細かい財務・会計データや非財務データなどが分析可能な形で利用可能になる状況も増えてくると予想されます。そういったデータをどう分析すればよいのか、次世代の財務分析手法が必要な時代はすぐそこに来ています。
またこういった分析手法は与信や監査だけでなく、企業の内部統制や内部監査の手法としても有効な手段となります。多数の海外子会社の膨大な取引情報を日次ベースで分析し、適時にリスクを識別するといったことにも有用です。ガバナンス強化の一環として高解像度の財務分析インフラの整備や日次ベースの異常検知システムの導入というのは、デジタルトランスフォーメーションのアジェンダの一つとして検討する価値があると思います。
次号は業種ごとの不正の手口を踏まえた分析手法を紹介予定です。ご期待ください。



