EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

情報センサー2020年11月号 パブリックセクター
インフラストラクチャー・アドバイザリーグループ 福田健一郎
大手シンクタンクのコンサルタントを経て、2012年より現職。水道、下水道、ガスなどの公営/公共インフラ事業の経営や、料金、官民連携などに関する戦略立案業務を統括。主な著書(共著)に『PPP/PFI 実践の手引き』(中央経済社)、『フランスの上下水道経営』(日本水道新聞社)。国土交通省PPPサポーター。当法人 シニアマネージャー。
Ⅰ はじめに
都市での経済活動や市民生活は、上下水道や電力、ガスといったユーティリティインフラに支えられています。ユーティリティインフラは、間断なく安定して使えることが当たり前で、多くの市民にとって、こうしたインフラ設備がどのように維持されているか、日常で強く意識をすることはありません。しかし、その実態は電力であれ、上下水道であれ、持続に向けた課題に直面しています。ユーティリティインフラの基盤なくしては、スマートシティも成り立ちません。今回は、インフラの運営の在り方、特に体制の在り方に焦点を当てます。
Ⅱ 地域ユーティリティインフラが抱える課題
ユーティリティインフラの持続に向けた課題にはどのようなものがあるでしょうか。代表的なものは、人口減少による「低密度化」が事業の非効率化を生み出すことです。ユーティリティインフラは、人口が減少すると料金を払う人が少なくなり、水道局や電力会社の収入が減ります。しかし、水道管や送電網といった資産は、人口が減ったからといって、使うのをやめたり、取り除いたりすることはできず、維持更新していく費用がかかり続けます。
水道事業を例にとってみましょう。当法人が公表している「人口減少時代の水道料金はどうなるのか」※1によると、今後人口減少と老朽化した施設の更新に直面すると、90%の事業(自治体)で、2040年度までに水道料金の値上げが必要と推計されています。全国平均の料金上昇の推計幅は、34%です。「3割の値上げで済むのか」とも思えてきますが、値上がり後の料金が2万円/月※2を超える地域(福岡県みやこ町)も出現する可能性があります※3。また、料金が高額になる恐れがある事業は、過疎が進む地方部に多く、職員も数名という体制崩壊の瀬戸際で運営をしている※4状況です。
こうした状態では、IT技術の活用を含めた経営革新の取組検討自体が困難であり、官民連携を解決策にしようとも、そのままでは赤字前提になり民間事業者も対応が難しいという課題も横たわります。
一方で、広域インフラの代表格ともいえる電力事業も課題を抱えています。2019年の台風15号では、千葉県の房総半島で鉄塔が倒壊し、北海道では、2018年の胆振東部地震によって、それぞれ大規模な停電が発生し、復旧に数日~数週間を要しました。広域インフラゆえの災害時の弱さが露呈しました。
こうした中で、エネルギー供給のレジリエンス向上がトピックスとなり、2020年の電気事業法等の一部を改正する法律では、従来の電力会社の送配電網から独立した運用も可能な地域の送配電網の仕組みも整備されました。
このように、自治体単位で営まれてきたインフラでも、広域的に営まれてきたインフラでも、「地域」の単位を新たに考える必要があるという点で課題は共通しているようです。
Ⅲ 「地域」ユーティリティをどのような単位で考えるべきか
しかし、現在、新たな地域の考え方として手軽な指針や枠組みがわれわれの手元にあるわけではありません。水道事業では、市町村経営原則のもとで運営されてきた水道事業の広域化推進策も盛り込まれた改正水道法が2018年に成立し、都道府県がリーダーシップ発揮を期待されていますが、市町村ごとに異なる施設整備状況、料金水準で行われてきた事業を統合することは容易ではない状況です。
他方、電力事業でも、主に地域の再生可能エネルギーの地産地消を目的として、市町村単位で「自治体新電力」が、民間企業と地元自治体の出資などの形態で設立されてきました。2010年代初頭から増え続け、今では約50を超える、自治体出資の新電力会社が存在しているとされています。近年では、大手電力会社との価格競争の中で、自治体新電力が苦戦する事例や、経営リスクを踏まえて自治体新電力の新規設立を断念する事例も出てきています。
一方で、地域インフラの単位・主体という視点で欧州の事例を見てみると、さまざまなモデルがあります。
1. 複数の中核市が「地域インフラ持株会社」を設立(ドイツ・ボーフム市など)
ドイツ西部にボーフム市(Bochum、人口約37万人)、ヘルネ市(Herne、人口約16万人)とヴィッテン市(Witten、人口約10万人)という、隣接した三つの自治体があります。3市にはそれぞれ、古いものは19世紀から、電力、ガス、水道、地域熱供給といったユーティリティ事業を一手に営んでいる会社(シュタットベルケ・ボーフム社、シュタットベルケ・ヘルネ社、シュタットベルケ・ヴィッテン社)があります。ここまでは、「シュタットベルケ」と呼ばれる地域インフラ会社のごく一般的な事例ですが、この3市の事例がユニークなのは、3市は共同出資で「持株会社」であるewmr社(中部ルール地方エネルギー・水道会社)を設立し、各インフラ会社の持ち分の99%をewmr社に保有させている点です。つまり、各市で事業を行う会社はそれぞれ独立した主体ですが、その株主は一つの持株会社に共通化されているわけです(<図1>参照)。
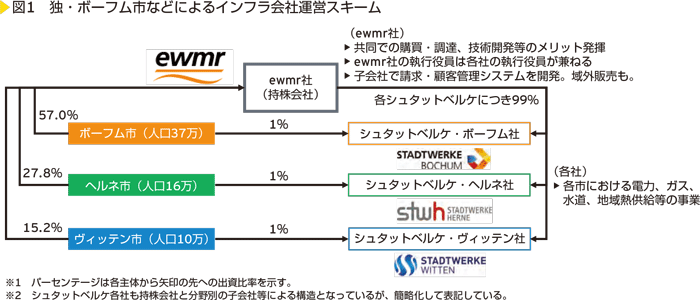
この共同持株会社のモデルは1998年に導入されました。その背景には、ドイツではエネルギー市場の自由化が進み、各市のシュタットベルケの競争力強化が必要となっていたという事情がありました。しかしながら、3市のシュタットベルケは、ボーフム市が1850年代、ヘルネ市でも1900年初頭から、それぞれの「わが街のユーティリティ事業者」として経営されてきた歴史的経緯もあり、それらを一つの主体に統合することは必ずしも容易ではなかったと想像されます。そこで、各社の独立性は保ちながら、調達面や技術開発などさまざまな面で、規模拡大のメリットを獲得するために、持株会社が設立されたわけです。この事例は、ドイツの公共ユーティリティインフラで初めての「自治体の水平連携」の事例とされ、規模拡大による効率性確保と顧客サービスの維持・向上を可能としました。また、ewmr社の子会社は共通の請求・顧客管理システムを開発し、それを域外に販売し収益確保をする、といった積極的な取組も行っています。このように、自治体の枠を取り払うべきところは取り払い、地域性は残すという「決断」のもと、ユーティリティインフラの持続性確保策が講じられたのです。
2. 国によるインフラ供給単位の新たな定義と地域のイニシアティブ(フランス)
ボーフム市などの事例は、いずれも10万人以上の人口規模がある都市における水平連携事例でした。しかし、今後の持続が困難になるような限界地域はどうすればよいのでしょうか。フランスの事例を見てみましょう。
フランスでは、2015年に成立した「共和国の新たな組織に関する法律」(通称:ノートル法)によって、基礎自治体であるコミューンが有していた上下水道の事業主体の権限が、2020年1月までに広域連合体の権限に移譲されることが法律上の義務となりました。ここでポイントになるのは、法律による強制によって、基礎自治体が担っていたインフラ事業を広域化するということのみならず、「広域連合体」という枠組みに集約されていることです。広域連合体は、複数の基礎自治体によって組成され、税財源も広域連合体に移譲され、広域連合体としての議会も設置されます。基礎自治体と県の中間のような広域的な生活・経済・行政圏ともいえる広域連合体に、上下水道に限らず、住宅制約、都市政策や地域経済政策といった行政サービスが法律によって移譲されています。フランス国政府の地域行政サービス供給単位を改めるという「決断」です。
また、フランス最西部の港湾都市であるブレスト市(Brest)では、広域連合体として100%出資の上下水道受託会社を作り、99年契約の事業運営権(コンセッション)契約により自らの地域の上下水道事業を管理させるとともに、隣接する他自治体にも会社の事業エリアを広げて、「地域の上下水道の受け皿会社」化を図り、今も成長を続けています。ブレスト市はかつて水メジャーの一翼であるヴェオリア社と事業運営権契約を締結していた、いわゆる「再公営化」事例ですが、再公営化に伴ってブレスト市が下した「決断」は、単に上下水道を市役所に戻したというわけではなく、機動的・柔軟に事業ができる受け皿会社の創出だったというわけです(<図2>参照)。
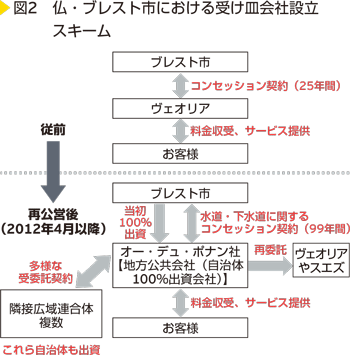
Ⅳ おわりに
ユーティリティインフラは地域に強く根ざしたものである一方で、持続していくには、従来の自治体の地理的境界での事業の完結を常に前提としていては、ITや民間の魅力的な製品、ノウハウの獲得も困難になり、最適解には近づけません。本誌2020年10月号の第2回で紹介したようなニュータイプ企業といえども、限定された範囲のビジネスではより優れたコストパフォーマンスや事業品質は発揮できません。
この難しい課題に、国や自治体がどう判断して、少しでも良い解に近づくことができるかが問われています。諸外国では、地域インフラ統括組織といえる持株会社化、国による生活圏へのインフラ集約、事業受け皿会社の設立など多様な運営方法で、最適解を模索しています。翻ってわが国の状況を見てみると、かつての第3セクターの失敗の経験が新たな運営組織の検討に二の足を踏ませています。また、国はインフラ供給の単位を強く定義していない状況です。グランドデザインとインフラ供給の単位と主体の在り方を地域で決断するときは近づいています。
※1 当法人と水の安全保障戦略機構の共同研究として2015年以来3年に一度実施している、全国約1,200の公営水道事業の個別将来料金推計等のレポート(ey.com/ja_jp/news/2018/03/ey-japan-press-release-2018-03-29)
※2 標準的な世帯を使用量である20立方メートル/月の水道料金推計値
※3 27事業(全体で1,263事業)で月1万円以上の水道料金となる可能性がある。
※4 水道統計(H28年度)によると、給水人口1万人未満の事業(220事業)の平均職員数は3名である。



