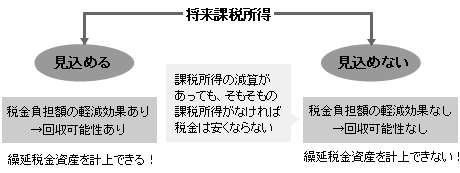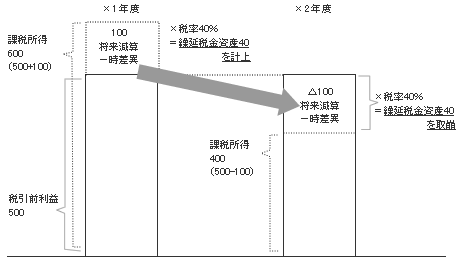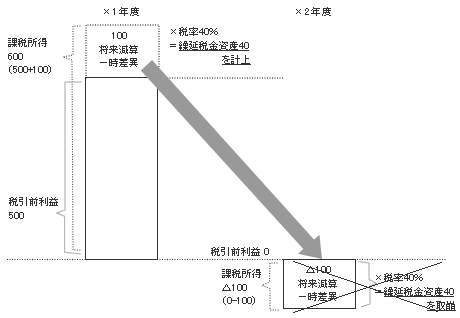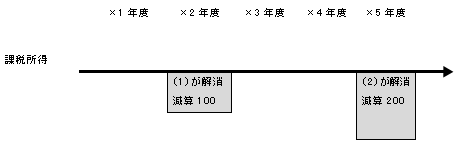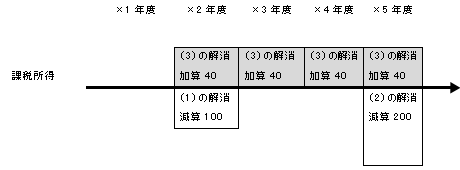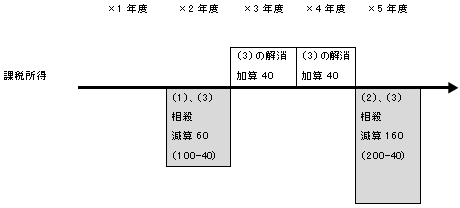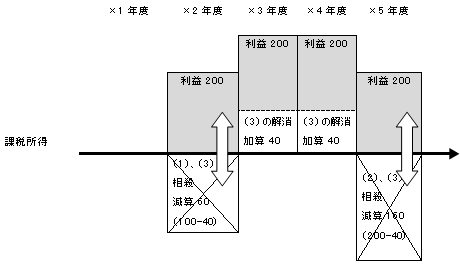わかりやすい解説シリーズ「税効果」 第4回:繰延税金資産の回収可能性
1. 繰延税金資産の回収可能性とは?
【ポイント】
- 繰延税金資産を計上するためには、その資産性(回収可能性)の検討が必要となります。
- 繰延税金資産の回収可能性とは、繰延税金資産が将来の支払税金を減額する効果があるかどうかをいいます。
「繰延税金資産」については、資産性(回収可能性)があるもののみ計上が認められるため、その資産性の検討が必要になります。
また、繰延税金資産の資産性の検討に当たっては、会社法上で配当制限がなく配当財源に含められることにも留意することとなります。例えば、明らかに回収可能性がない繰延税金資産を計上した場合、会社の実態と乖離(かいり)した過大な配当を行ってしまうことも考えられます。
ここでは、この「繰延税金資産の回収可能性」がどういうものかを説明します。
※「繰延税金負債」についても計上額を決定するに当たって、その支払可能性が認められる(将来支払いが見込まれる)もののみ計上することとなりますが、支払可能性が認められないケースは限定的です。
-
繰延税金資産の回収可能性とは、繰延税金資産が将来の支払税金を減額する効果があるかどうか、をいいます。
繰延税金資産の算定基礎である将来減算一時差異には、それが解消する時に将来の課税所得を減額(マイナス)する効果がありますが、将来減算一時差異が解消する時にそもそも将来の課税所得がなければ、税金は安くなりません。
従って、将来の課税所得が見込めなければ、将来の税金負担額は変わらない(将来の税金が安くなる権利を行使できない)ため、繰延税金資産を計上することができない、ということになります。
繰延税金資産が将来の支払税金を減額する効果が『ある』場合のイメージ
×2年度において、税引前利益は500ですが、将来減算一時差異100が解消した結果、課税所得が100減少し、支払税金が40だけ減額されています(将来減算一時差異100×税率40%=40)。
これは×1年度に計上した繰延税金資産に「将来の支払税金を減額する効果があり、回収可能性がある」といえます。
繰延税金資産が将来の支払税金を減額する効果が『ない』場合のイメージ
×2年度において、税引前利益が0(将来減算一時差異を考慮する前のそもそもの課税所得が0)のため、将来減算一時差異100が解消し課税所得が△100(=0-100)となりますが、通常、納税額はマイナスとはならないため「△100×40%」も納税額△40とはならずに、納税額0となります。
これは×1年度に計上した繰延税金資産に「将来の支払税金を減額する効果がなく、回収可能性がない」といえます。
2. 繰延税金資産の回収可能性の具体的な検討方法
具体的には下表のようなステップで検討していきます。
そして検討した結果、次の3要件のいずれかを満たせば「繰延税金資産の回収可能性」がある、と判断できることとなります。
-
主に、将来減算一時差異の解消年度等に、課税所得が発生する可能性が高いと見込まれることをいいます。
イメージとしては、繰延税金資産が将来における税金負担額の軽減効果を発揮するために「会社が営んでいる事業から将来の利益(課税所得)が十分に見込めるか?」ということになります。
-
主に、将来減算一時差異の解消年度等に、含み益のある固定資産又は有価証券を売却するなど課税所得を発生させる特別な計画(=タックスプランニング)が存在することをいいます。そして、単に計画があるだけでは足りず、その実現可能性も必要となります。
イメージとしては、繰延税金資産が将来における税金負担額の軽減効果を発揮するために「含み益のある保有資産を使用して将来の利益(課税所得)を出すための実現可能性の高い計画はあるか?」ということになります。
-
主に、将来減算一時差異の解消年度等に将来加算一時差異の解消が見込まれることをいいます。
イメージとしては、「将来減算一時差異と『相殺』できる将来加算一時差異は十分にあるか?」ということになります。
「繰延税金資産の回収可能性」の具体的な検討ステップのイメージ
-
【前提】
- ×1年度が当期
- ×1年度末の将来減算一時差異300:
(1) 長期滞留在庫の評価損100(社内規程により×2年度に廃却する予定)
(2) 役員退職慰労引当金200(社内規程により×5年度に退任する予定) - ×1年度末の将来加算一時差異160:
(3) 積立金方式による圧縮積立金160(毎期40ずつ解消し×5年度までに全て解消) - 毎期税引前利益を200計上
- 将来年度の課税所得を×5年度まで見積る
1. 期末における将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングを行う
2. 期末における将来加算一時差異の解消見込年度のスケジューリングを行う
3. 将来減算一時差異の解消見込額と将来加算一時差異の解消見込額を解消見込年度ごとに相殺する
- ×2年度:将来減算一時差異の解消見込額100と将来加算一時差異の解消見込額40を相殺(将来減算一時差異60が残る)
- ×5年度:将来減算一時差異の解消見込額200と将来加算一時差異の解消見込額40を相殺(将来減算一時差異160が残る)
4. 3.で相殺しきれなかった将来減算一時差異の解消見込額については、その金額を将来年度の課税所得の見積額(タックスプランニングによる課税所得の発生見込額を含む)と、解消見込年度ごとに相殺する。
- ×2年度:3.で相殺しきれなかった将来減算一時差異の解消見込額60と将来年度の課税所得の見積額(利益)を相殺
(「将来減算一時差異60 < 課税所得見積額200」のため、将来減算一時差異は全て解消) - ×5年度:3.で相殺しきれなかった将来減算一時差異の解消見込額160と将来年度の課税所得の見積額(利益)を相殺
(「将来減算一時差異160 < 課税所得見積額200」のため、将来減算一時差異は全て解消)
この例では上記のとおり、×1年度末の将来減算一時差異300(長期滞留在庫の評価損100、役員退職慰労引当金200)は、それぞれ解消する時に将来の課税所得を減額(マイナス)する効果を発揮しています。
そのため、×1年度に計上する将来減算一時差異300に係る繰延税金資産 (=将来減算一時差異×税率)には「将来の支払税金を減額する効果があり、回収可能性がある」と判断できることとなります。
3. 繰延税金資産の回収可能性に関する判断指針
なお、将来加算一時差異の金額が将来減算一時差異の金額を下回るケースが多いことが見込まれるため、繰延税金資産の回収可能性は、多くの場合、将来年度の会社の収益力に基づく課税所得によって判断することになります。
ただし、将来年度の会社の収益力を客観的に判断することは実務上困難な場合が多いため、会社の過去の業績等の状況を主たる判断基準として、将来年度の課税所得の見積額による繰延税金資産の回収可能性を判断する場合の指針が示されています。
決算実務の現場ではよく繰延税金資産の回収可能性の検討に当たって、「②の会社だから~~」、「④ただし書きの会社だから~~」などの表現が使われますが、これはこの指針に対応した呼称になっています。
-
|
|
期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得を毎期計上している会社等
|
|
|
業績は安定しているが、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得がない会社等
|
|
|
業績が不安定であり、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得がない会社等
|
|
|
|
|
|
過去連続して重要な税務上の欠損金を計上している会社等
|
|
|
|
①...
一般的に、繰延税金資産の全額について、その回収可能性があると判断できます。
②...
一時差異等のスケジューリングの結果に基づき、それに係る繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産は回収可能性があると判断できます。
③...
将来の合理的な見積可能期間(概ね5年)内の課税所得の見積額を限度として、当該期間内の一時差異等のスケジューリングの結果に基づき、それに係る繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産は回収可能性があると判断できます。
④本則...
原則として、翌期に課税所得の発生が確実に見込まれる場合で、かつ、その範囲内で翌期の一時差異等のスケジューリングの結果に基づき、それに係る繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産は回収可能性があると判断できます。
④ただし書き(重要な税務上の繰越欠損金が非経常的な特別の原因により発生し、それを除けば課税所得を毎期計上している会社等)...
将来の合理的な見積可能期間(概ね5年)内の課税所得の見積額を限度として、当該期間内の一時差異等のスケジューリングの結果に基づき、それに係る繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産は回収可能性があると判断できます。
⑤...
原則として、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金等に係る繰延税金資産の回収可能性はないものと判断します。
なお、先述した「2.繰延税金資産の回収可能性の具体的な検討方法」の具体例では、前提として「将来年度の課税所得を×5年度まで見積る」と見積期間を限定していますので、この具体例の会社の場合は、③の会社、又は④ただし書きの会社に該当していると想定されます。
わかりやすい解説シリーズ「税効果」 一括ダウンロード
わかりやすい解説シリーズ「税効果」
- 第4回:繰延税金資産の回収可能性 (2012.04.13)
You are visiting EY jp (ja)
jp
ja