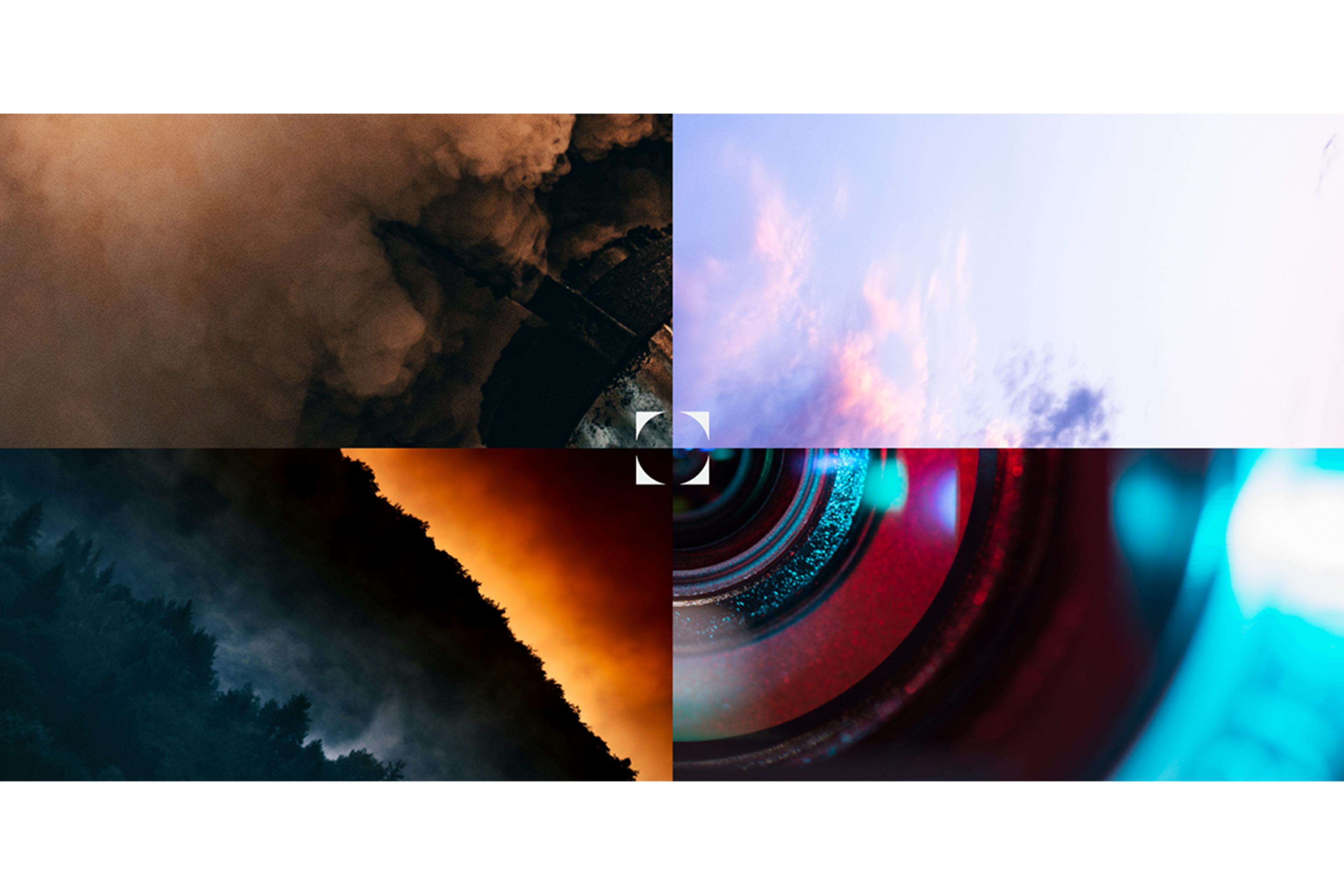EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

EUのESPR規則で義務化されるデジタル製品パスポート(DPP)とは? 企業が備えるべき対応ポイントと最新ワーキングプランの要点を解説します。
要点
- 欧州では2024年7月に、製品の持続可能性と循環性を促進するESPR(エコデザイン規則)が発効した。その中で、サプライチェーン情報のデジタル管理・透明化を求めるデジタル製品パスポート(DPP)の義務化がうたわれている。
- 2025年4月に2025-2030 working plan for the Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) and Energy Labelling Regulation(以降、ワーキングプラン)が発表され、DPPの優先セクターと実装タイムラインが具体的に示された。日本においても、欧州とつながるサプライチェーン企業はその対応を迫られることになる。
- EYは、欧州チームと連携してDPP対応の支援を実施している。DPPの法的要求事項を整理し、該当製品を特定した上でギャップ分析を行って対応戦略策定支援を行う。さらに、デジタルソリューションのシステム構築や既存システムとの接続までも支援可能。
1. DPPの背景
EUでは、2030年までに材料の循環利用率を倍増させ、エネルギー効率目標を達成するための政策として、2024年7月18日に「持続可能な製品のためのエコデザイン規則(Ecodesign for Sustainable Products Regulation: 以降、「ESPR規則」)」が発効しました。主な狙いは、エコデザイン要件を定め、特定の製品グループの情報や製品性能をまとめることで、欧州マーケットに上市する製品のサーキュラリティ、エネルギー効率等環境・サステナビリティ要素を改善することです。
ESPR規則の一環として、サプライチェーン情報をデジタル管理するためのデジタル製品パスポート(Digital Product Passport:以降、「DPP」)も義務化されます。DPPとは、製品の材料構成や懸念物質、安全な使用・リサイクル・廃棄方法等に関する情報を電子的に提供し、製品が市場に出た後も、トレーサビリティを確保するものです。これらの環境情報やパフォーマンス情報等を可視化することで、製品のライフサイクル全体にわたる管理が容易になるとともに、サプライチェーン全体での責任ある対応を促すことが目的です。
2. DPPの内容と適用
2025年4月16日にESPR規則とその柱となるDPP要件のスコープの詳細を含む2025年~2030年ワーキングプラン(“Ecodesign for Sustainable Products and Energy labelling Working Plan 2025-2030”)が発表されました。その内容から、DPPの対象製品群、適用の過程と除外製品についてこのセクションで解説します。
2.1 対象製品群
ESPR規則が定める全ての対象製品が段階的にDPPを付与されることになりますが、その中から特に、以下の10製品がこれまで優先製品群として設定されていました:
- 鉄鋼
- アルミニウム
- 繊維製品(特に衣類と履物)
- 家具マットレス
- タイヤ
- 洗剤
- 塗料
- 潤滑油
- 化学製品
- ICT製品およびエネルギー関連製品
今回の2025年~2030年ワーキングプランでは、この中でも特に以下の4つの完成品、2つの中間製品が優先対象となることが決定されました。
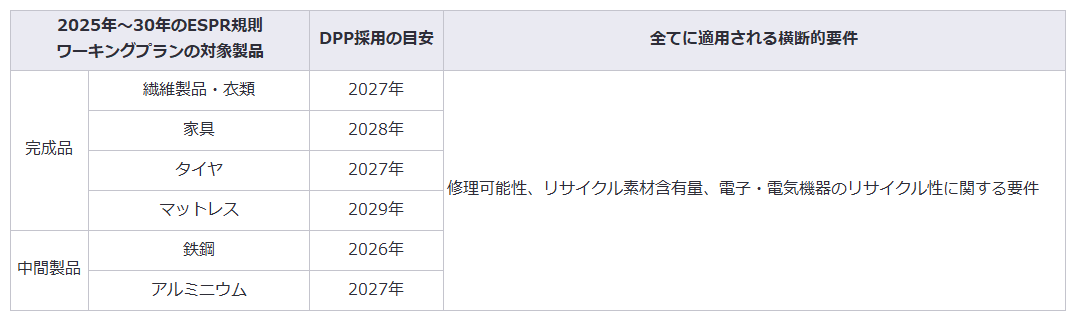
※ 衣類には履物は含まない。また、ICT製品およびエネルギー関連製品については、引き続き既存の指令または今後の見直しの中で対応が進められる。
また、ESPR規則以外の法的措置等でDPPと同等の情報を提供する代替的なデジタル情報提供システムがある製品は、DPPの付与義務が免除されます。
2.2 タイムライン
要件導入の時期だが、ESPR規則の発効時点でDPPが義務化されたわけではなく、製品ごとの委任法(product-specific delegated acts)によって段階的に適用される予定です。初の委員規則の発行は2026年を予定しており、上記の優先製品群は最初の対象となります。また、DPPに収集・提供される情報は、個別製品ごと、または類似製品のグループをまとめた形で、委任法を通じて設定されます。
2.3 その他
情報開示要件、パフォーマンス要件に適合しない事業者に対して、加盟国によっては違反時に罰金や調達排除といった制裁が課される可能性があり、今後の各国の方針に注目する必要があります。
また、上記のとおり、ESPR規則以外の措置等により代替的なデジタル情報提供システムによって製品情報が提供されている、またはされる予定の製品については、DPPの適用が免除されます。エネルギーラベルが付与され、EPRELというデータベースを通じて情報が提供されているエネルギー製品はその一例です。
3. 企業における課題
3.1 法令理解の課題
DPP対応に向けて、欧州との物理的な距離がある日本企業には主に規則理解の課題、ケイパビリティの課題があると考えられます。
まず、DPPに関連するESPR規則の法的要件を正しく理解することが一つのハードルとなっており、自社のどの製品が対象で、どの情報を収集・提供する必要があるのかを把握しきれていない可能性があります。GHG排出量の情報収集の初期段階でも問題点として挙げられてきたように、自社の製品ライフサイクルに関わるサプライヤーによるデータの取得・定量化が不十分な場合、データギャップの特定だけでリソースが使われるケースが少なくないでしょう。特に、サステナビリティ室で法務的知見を持つ人材がいなければ、解釈の誤りがサプライチェーン全体に波及するリスクも考えられます。
3.2 デジタル・ケイパビリティの課題
DPPの導入には、製品情報の収集と同時に、その継続的な管理とDPP情報提供システムへの提出を可能にするデジタル基盤が不可欠です。
ESPR規則にのっとりDPPへの対応を行う際、製品ごとのデータ提供が求められます。製品の種類や展開する市場によっては、一製品当たり必要となるデータポイントが多くなり、結果として扱う情報が膨大になります。そのため、一見するとGHG算定と同様のデータ収集プロセスのように見えますが、実際にはGHG算定以上の高度なデータ集約力と情報管理体制が必要となります。この点が、DPP対応の課題の一つだと予想されるため、早い段階で自社の対応ケイパビリティを確認しておく必要があると言えます。
環境負荷に関する情報等を一元管理してこなかった企業の場合、DPPの継続的な適用に必要な体制やデジタルインフラが整っていない可能性があります。社内の既存のデジタルシステム(例えばGHG排出量集計システム)とどう連携させるか、また、海外パートナーとのデータの相互運用性・統一の確保も長期的な課題として浮上します。
加えて、DPPのもう一つの側面、パフォーマンス要件を満たすための課題がより長期的な変革を必要とします。パフォーマンス要件としては、製品の解体、原材料の選定、消費者向けのリサイクル情報等含むリサイクルに関連するデータの提供が求められていることから、実際に製造オペレーションレベルでの改善が求められます。その意味で、製造業は持続可能で循環型の製品づくりに向けて、製品、ビジネスモデル、サプライチェーン、そして関連システムを実際に再設計することとなります。ESPR規則のパフォーマンス要件を満たすためには、最終的には製品やプロセスの改善が必要であり、新たなテクノロジーや材料への投資も求められる可能性もあります。
4. EY支援の特徴
EYでは、企業がESPR規則に基づく情報提供およびパフォーマンス要件に備えるために、確度が高い要件を先行して検討を進める「ノーリグレット(後悔しない)」行動の考え方に基づいた支援を実施しています。これにより、将来多数の項目を短い検討期間で一気に検討するような事態を避け、確実に余裕を持った対応を進められ、今後のエコデザイン要件の達成に向けて、先行者利益(head start)を得ることができます。この支援は、「法的理解」「ギャップ分析」「システム構築と実装」から構成されます。
4.1 法的理解
DPP取り組みへの第一歩として、規則要件を理解することが重要です。EYでは、ESPR規則および関連する最新情報を踏まえてDPPに準拠するための法的要件およびタイムラインを解説します。具体的には、ESPR規則の主要な要素や要求事項を詳細に分析し、企業が順守すべき法的枠組みを明確にします。また、法的要件の変化に対する適応策や、順守のためのベストプラクティスも提供します。
4.2 ギャップ分析
この項では、まずDPP要求事項に基づいて対象となる製品群を特定します。対象製品群が明確になった後、1つの製品(年間売上高が最も多い製品、大規模な製品グループの代表的な製品等)のテストケースを実行することを提案します。そのために、現在入手可能な製品情報と、ソフトウェアシステムにおけるデータ品質および統合の状態を明確にするためのギャップ評価を行います。解明したギャップを解消するために対応戦略とアクションプランを策定します。このアクションプランには、ソフトウェア統合のプランも含めることで、前記デジタル・ケイパビリティの課題の解消を支援します。
4.3 システム構築と実装
EYでは、DPP対応のためのシステムおよびデジタル要件の検証を行い、多様なデジタルソフトウェアのセットでの対応を支援します。具体的には、企業のニーズに応じたカスタマイズされたシステム設計を行い、ESPR規則に基づく要件を満たすための技術的なソリューションを提供します。また、既存システムとどのように連携についても支援することが可能で、データの一貫性や整合性を保ちながら、新しいシステムを効果的に統合するための戦略を策定します。これにより、企業は効率的にDPPの要件を満たし、持続可能なビジネスモデルを構築できます。
5. まとめ
DPPは、EU域内の規制にとどまらず、国際的な企業のサステナビリティの在り方にまで影響を及ぼす仕組みとなることが予想されます。企業はこの動きを単なる規制対応としてではなく、サステナブルなモノづくりのさらなる促進のきっかけとも捉えるべきです。DPPへの対応には、ESPR規則のデータ開示とパフォーマンス要件の法的理解、デジタル基盤の整備が不可欠であり、その実現には多角で継続的な専門性が求められます。
EYは、「法的理解」「ギャップ分析」「システム構築と実装」のプロセスを通して、企業のDPP対応を支援することが可能です。テストケースの実装を評価して、主要な改善点を特定し、今後の対応戦略に反映します。また、企業の製品ポートフォリオを評価して、次のステップのテストケースから長期的な実装戦略まで策定します。
このように、EYは企業の製品ライフサイクル管理だけでなく、長期的な開示と要件達成に向けたシステム構築とともに、今後の追加的な要件を見据えた戦略策定を行い、長期的なDPP対応支援を行うことが可能です。
参考文献
“Ecodesign for Sustainable Products and Energy labelling Working Plan 2025-2030”, European Commission,environment.ec.europa.eu/document/download/5f7ff5e2-ebe9-4bd4-a139-db881bd6398f_en?filename=FAQ-UPDATE-4th-Iteration_clean.pdf (2025年4月16日アクセス)
【共同執筆者】
Liliana Martinez Rivera(マルティネス リベラ リリアナ)
EY新日本有限責任監査法人 CCaSS事業部(気候変動・サステナビリティ・サービス)
シニア
法政大学サステナビリティ学修士。サステナビリティに関する動向を解説するコラムの執筆経験を有する。国際海事機関(IMO)海洋環境保護委員会等においてTechnical Advisorとして参画し、パブリックセクター向けの国際動向調査に従事した後、民間セクターにおける気候変動関連の情報開示支援業務に携わる。2024年よりEY新日本有限責任監査法人にて、生物多様性関連のアドバイザリー業務に従事している。
サマリー
欧州のESPR規則で義務化されるデジタル製品パスポート(DPP)とは? 企業が備えるべき対応ポイントと最新ワーキングプランの要点を解説します。
EYの最新の見解
サーキュラーエコノミーの新指標 GCP v1.0が企業にもたらす3つの効果(概要編)
ビジネスのためのグローバル循環プロトコル(GCP) v1.0の概要と特徴、市場にもたらすインパクト、日本企業が押さえるべきポイントを解説します。
サーキュラーエコノミーの新指標 GCP v1.0が企業にもたらす3つの効果(実務編)
ビジネスのためのグローバル循環プロトコル(GCP) v1.0の概要と特徴、市場にもたらすインパクト、日本企業が押さえるべきポイントを解説します。
Four Futures Japan: 気候変動に関する科学的シナリオ没入体験型プログラム
2025年3月、EY Japanは、気候変動に関する没入型体験プログラム「Four Futures Japan」を東京にて開催しました。本プログラムは科学とテクノロジーを活用したストーリーテリングにより気候変動の現実的な影響を伝え、参加者に革新的な思考を促進します。
EUDR(欧州森林破壊防止規則)で日本企業に求められる対応と基盤づくりのステップ
欧州森林破壊防止規則(EUDR)の適用開始時期が12カ月延長されることが2024年11月に決定しました。企業は適用開始までに必要情報の収集およびデューデリジェンス実施体制の整備が求められます。EUDRの適用対象となる企業の定義と、EUDR対応のための基盤構築のポイントを解説します。
欧州企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令で企業がおさえるべき実務上の留意点(1)
2024年7月に発効した欧州企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令は、事業活動が人権や環境に与える負の影響に対応するためのデューデリジェンスの実施を企業に求めています。日本企業にも影響が及ぶことから、 デューデリジェンス義務履行のために必要な取り組みの中でも特に企業が留意すべき事項について解説しています。
近年脚光を浴びるサーキュラーエコノミーについて、そのコンセプトを改めて整理し、グローバルにおける規制・政策、標準化、情報開示の動向を解説します。