EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

海運業における新リース会計基準の適用は、会計処理に大きな影響を生じさせる可能性があります。慣行的にリースの範囲外とされていた定期傭船契約が、リースの対象に含まれるためです。同業界の皆さまにとって参考になるよう、新リース会計基準の主なポイントや実務上の課題について解説します。
本稿の執筆者
EY新日本有限責任監査法人 海運セクター 公認会計士 内田 聡
海運セクターナレッジリーダー。入社後海運業を中心に上場会社の監査業務やIPO支援業務に従事。雑誌への寄稿、書籍執筆、講演活動等にも携わっている。元日本公認会計士協会海運業研究部会部会長。
要点
- 海運業では慣行的にリースの範囲外とされていた定期傭船契約が、新リース会計基準の適用によりリースの対象に含まれる。
- 定期傭船契約に類似する傭船契約があり、その取扱いをどうするか、契約文言に捉われずに実質的な判断を行う必要がある。
- 傭船契約に含まれるリースを構成する部分とそれ以外との区別、リース期間をどのように算定するかといった契約形態に応じた判断のルール化が必要となる。また、システム導入の検討も必要である。
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)から2024年9月13日に「リースに関する会計基準」(以下、本会計基準)、「リースに関する会計基準の適用指針」(以下、本適用指針)等が公表されました。適用時期は27年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から原則適用となっており、25年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から早期適用することが認められています。
本会計基準の適用により現行の会計基準における借手のオペレーティング・リースや定期傭船契約についてもオンバランスされることになり、海運企業において大きな影響がある可能性があります。本会計基準は、このように多くの海運企業に影響を与える可能性があり、早期に検討する必要があると考えられます。本稿では、借手の会計処理及び論点を中心に解説します。
なお、文中意見に係る部分は筆者の私見である旨、あらかじめ申し添えます。
Ⅱ 海運業セクターの特色
狭義の海運業は船舶を用いて旅客又は貨物を海上輸送するというサービスを提供することで収益を得る事業体を指し、広義では船舶を賃貸することによって収益を得る事業体(船舶貸渡業)も含みます。いずれの事業においても船舶という資産を運用して収益を得ることでは共通しており、使用する船舶を調達する方法として自社で船舶を建造・買船する以外に他社から傭船する(船舶を賃借する)ことも歴史的に広く行われています。そのため、新リース会計基準導入による影響が非常に大きいセクターであると言えます。
また、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第2条に定義されているいわゆる「別記事業」(水運業)に該当することから、対応する準則である「海運企業財務諸表準則」(以下、海運業準則)と本会計基準及び本適用指針に示された処理(勘定科目)との整合性をどのように図るかということも問題となり得ます(25年5月末時点において海運業準則は改訂がなされていません)。
Ⅲ セクター特有の論点
1. 定期傭船契約の本会計基準及び本適用指針上の取扱い
貨物船の傭船契約については以下のように区分されます。
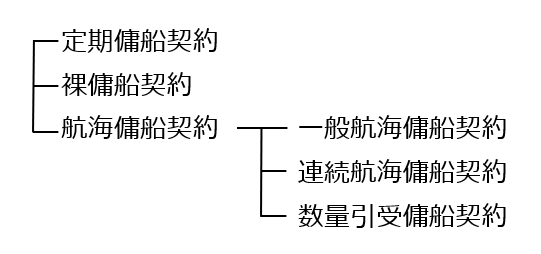
定期傭船契約とは一定期間を定めて船主が船舶に船員を配乗させ傭船者に貸与する契約です。裸傭船契約との違いは船長を含む船員の手配と修繕、保険、船用品調達等の船舶管理を船主が行うのか、傭船者が行うのかという点です。裸傭船においてはそれらを傭船者が行いますが定期傭船においては船主が行う形になります。
そのため、従前も裸傭船契約はリース契約として会計上取り扱われてきましたが、定期傭船契約は船員手配や船舶管理という役務提供を船主が行うため、役務提供契約の一種であるとしてリース契約としての取扱いが実務上なされていませんでした(オペレーティング・リースとしての注記もなされていませんでした)。
本会計基準においては「リース」を「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分をいう」(本会計基準第6項)と定義するとともに、「借手及び貸手は、リースを含む契約について、原則として、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分けて会計処理を行う」(本会計基準第28項)とされており、定期傭船契約に含まれる構成要素のうち、リースを構成する部分、すなわち、原資産を使用する権利部分を区分してリースとして取り扱うことになりました。そのため、定期傭船契約に含まれる当該権利部分とそれ以外の部分をいかにして区分するかという検討が必要となります。
2. 定期傭船契約に類似する傭船契約の取扱い
前述の航海傭船契約のうち、一般航海傭船契約とは特定の船腹の全部又は一部を船主が荷主に貸して物品の運送を引き受ける契約を指し、通常の不定期船における一航海当たりの運送契約です。一方、連続航海傭船契約とは一般航海傭船契約を複数回(一定期間)行う契約を指します。数量引受契約とは物品の運送に関して運送量や運送期間を定めて行う傭船契約であり、連続航海傭船契約に類似はしていますが、数量引受契約は船舶の特定は行わないという点で異なります。
これらの契約をリース契約として取り扱うかどうかについては、契約上、原資産(船舶)の特定がなされているかどうかが1つの判断基準となり得ると考えます(本適用指針6項)。ただし、契約上は船舶の特定はなされていないものの、実質的には特定されている場合もありケース・バイ・ケースでの検討は必要となります。
なお、海運企業が連続航海傭船契約や数量引受契約で船腹を調達するケースはほぼないと考えられるため、これらの検討は主に海運企業とこれらの契約を締結することにより製品等の輸送を行う企業(自動車、鉄鋼等の製造業)でなされることになります(借手側のリース契約に該当するかどうかの検討)。
3. リース期間(傭船期間)の検討
本会計基準において、「借手のリース期間」については、解約不能期間に下記を加えた期間とされています。
- 借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間
- 借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間
なお、貸手のみがリースを解約する権利を有している場合、当該期間は借手の解約不能期間に含まれます(本会計基準31項)。
「貸手のリース期間」については、「借手のリース期間と同様に決定する方法」のほか、「借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間(事実上解約不能と認められる期間を含む。)にリースが置かれている状況からみて借手が再リースする意思が明らかな場合の再リース期間を加えて決定する方法」のいずれかを選択することが可能です(本会計基準32項)。
傭船契約においては延長オプションあるいは解約オプションが設定されていることがあり、当該資産の運用について経済的合理性を踏まえた上でのリース期間の検討が必要となります。
なお、外航海運業の場合、パナマやリベリアといったタックスヘイブン国等(便宜地国)に設立した子会社に船舶を所有させた上で親会社が当該船舶を傭船するというスキームがあり、これは仕組船(便宜置籍船)と呼ばれます。子会社であるため傭船期間について契約上自由に定めることが可能です(当該期間終了後更新可能)。
しかし、仕組船は親会社で船舶を保有する代わりに、低コストの外国人船員の配乗、登記費用や固定資産税の負担の削減といった目的のために便宜地国に設立した子会社に船舶を保有させるものであり、通常は当該船舶の使用可能期間にわたって裸傭船契約が継続します。そのため、個別決算上は当該船舶の経済的耐用年数といった予定リース期間を検討し、会計処理を行うことになると考えられます(連結上は連結子会社所有の船舶が連結貸借対照表に計上されるとともに傭船契約は相殺消去されます)。
Ⅳ 今後の実務上の課題
第Ⅲ章までに述べた通り、リースとして取り扱う傭船契約とそれ以外の傭船契約をどう区別するか、傭船契約に含まれるリースを構成する部分とそれ以外とをどのように区別するか、あるいはリース期間をどのように算定するか、契約形態に応じた判断のルール化が必要となります。また、システム導入の検討も必要となるでしょう。
Ⅴ その他
第Ⅱ章に記載の通り、別記事業として「海運業準則」が適用される場合、傭船契約に関する収益費用は「貸船料」及び「借船料」という科目を用いると規定されており、勘定科目と含まれる金額(利息部分をどう表示するか)の検討が必要です(海運業準則は個別財務諸表の開示のみを定めているため、連結財務諸表の科目の整合性をどう図るかの検討も含まれます)。
定期傭船契約等、本会計基準及び本適用指針適用前にはリースの範囲に含めていなかったものが リースとして取り扱われるため、リース注記の開示に含まれることは当然ですが、逆に「収益認識に関する会計基準」の対象ではなくなるため、収益認識関係注記等からは除かれる点に留意が必要です。
サマリー
新リース会計基準は、多くの企業の財務諸表に影響を与えています。海運業の特徴として、慣行的に従前はリースの範囲外とされていた定期傭船契約が、今回の改正に伴いリースの対象に含まれるという点が最も大きな影響を与えると考えられます。これらの影響や新リース会計基準の動向についてご紹介します。
関連コンテンツのご紹介
海運業のTCFD開示から各社が共通して認識しているリスクおよび国際海運の2050年カーボンニュートラル達成に向けた動向と「国際海運GHGゼロエミッションプロジェクト」で提案された経済的手法について紹介します。
収益認識会計基準の原則適用が始まりました。海運業において従前の実務からどのような変更が生じるか、開示(顧客との契約から生じた債権、契約資産、契約負債の表示)の論点に絞って解説します。
新たな収益認識基準が業種別会計に与える影響をシリーズで分かりやすく解説します。第8回の本稿では海運業に関連する収益認識の論点について取り上げます。
EY新日本有限責任監査法人より、会計・監査や経営にまつわる最新情報、解説記事などを発信しています。
業種別の会計の基礎について、コラム記事を掲載しています。
全国に拠点を持ち、日本最大規模の人員を擁する監査法人が、監査および保証業務をはじめ、各種財務関連アドバイザリーサービスなどを提供しています。
情報センサー
EYのプロフェッショナルが、国内外の会計、税務、アドバイザリーなど企業の経営や実務に役立つトピックを解説します。




