EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
Sales DX総点検 ~いまこそ、顧客接点を再構築する~ 第2回:Sales DX総点検--営業偏重組織からの脱却
寄稿記事
日本企業では、直販だけでなく販売企業や代理店に高く依存することが多く、近年直販チャネルをいかに強化するかが経営の課題となっています。また、ビジネスモデルがモノ売りからコト売りへ変わる中で、営業偏重な組織からいかに脱却するか、そしてSales DXをいかに成功させるか、発生しがちなボトルネックとその解消方法について解説します。
第1回において提示された営業人員不足だけでなく、モノ売りからコト売りへと商材のソリューション化が進むにつれ、営業の皆さんは提案に関して多能かつ習熟を要する役割を果たすことが求められているでしょう。これは営業個人/部門にとって、とてもタフな要求と言わざるを得ません。
特に営業担当者に新規の獲得や顧客との関係性構築を依存している「営業偏重組織」においては影響が大きいでしょう。そうした状況において、戦略もしくはマネジメントを担う側はどのように対応すべきなのでしょうか。
ここでは、主な読者であるデジタル施策担当の皆さんがさらに成果を上げるには、具体的に何を見直したらよいのかについて考えていきましょう。
1. Sales DXでツールを導入すると営業成果が落ちることもある?
営業の効率化や高度化で真っ先に考える対応は、マーケティングオートメーション(MA)ツールや営業支援(SFA)ツールの導入、ホームページ(HP)の拡充による新規獲得リード(新規営業先候補)の増加といったSales DXでしょう。
しかし、ソリューション商材を展開したい場合や、営業活動を営業担当者個人のスキルや販売企業に頼ってきた営業偏重組織においては、ツール導入そのものがSales DXのボトルネックになることがしばしばあります。
2. コト売り=ソリューション営業におけるボトルネック
最近、ボトルネックの一つが「マーケティング部門が創出したリードを営業にいくら渡しても、営業側は使えないと断定して活用しない」というケースです。マーケティング部門がナーチャリング(顧客育成)した成果もスコアリングも使い物にならない、結局ゼロから会話をしなくてはならない、という判断を営業が下し、マーケティング部門は役に立たないと評価されてしまうのです。
このボトルネックは、これまで顧客とのコンタクト開発からリードの創出、成約クロージングまでを営業に任せ、アカウント営業を中心に行って新規を広く集めてこなかった営業偏重組織がSales DXを進める過程でよく見られます。
図1にあるように、新規リードを創出することが役割のマーケティング部門において、リードが営業活動に値すると評価し、(1)営業に渡す率と、(2)それを受け取った営業が実際に有用なリードと判断する率において、マーケティング/営業部門で互いの評価にずれが発生しがちなことが原因です。極端な場合だと、この重要業績評価指数(KPI)を細かく把握していないため、問題の原因をマーケティング部門に押し付けることもあります。
このボトルネックは、マーケティング部門が広報などの拡大機能として、マーケティングと営業という2つの部門でそれぞれ活動を行い、分断されているため、施策修正の内容共有と対応速度、つまり「時間の流れが違う」状態が主な原因の一つです。 また、ファネル=漏斗(じょうご)なので、ついマーケティング部門が担当する上流のKPI(図1の左側)からパフォーマンスの改善を考えてしまうことも原因です。
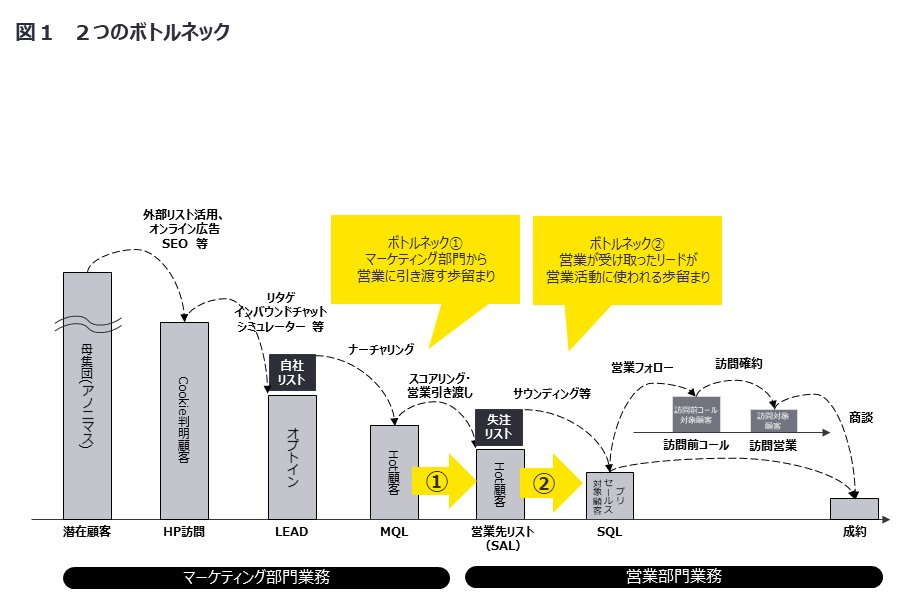
図1:2つのボトルネック
3. ボトルネックの発生原因と解決方法
(1) マーケティング部門の担当する上流のKPI(図2の左側)から、全体のパフォーマンス改善を考えてしまう
実は先ほどから、マーケティングから営業にリードを「渡す」という表現を続けています。これにより、ファネル上流で何ができるのかを考えてしまいがちです(図2)。
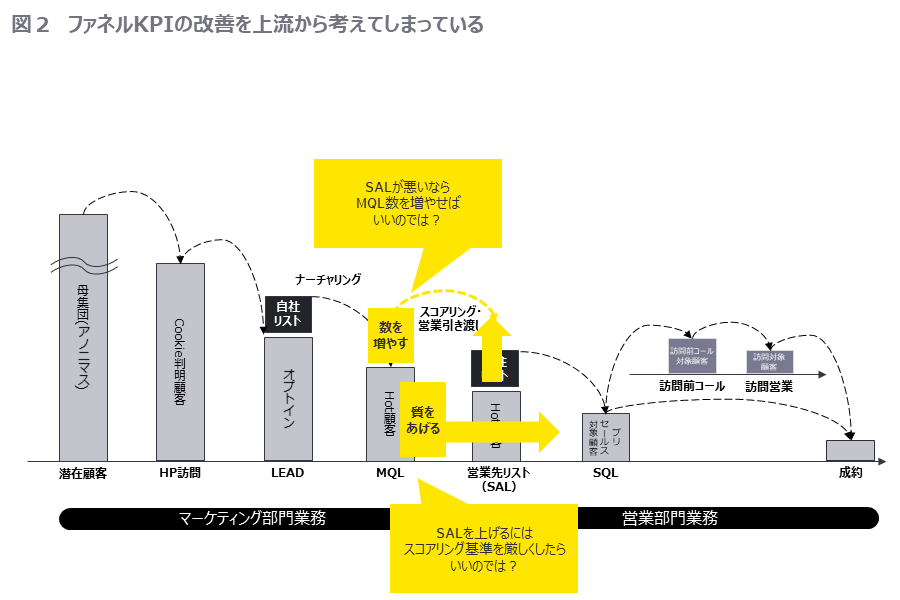
図2:ファネルKPIの改善を上流から考えてしまっている
アカウントベースドマーケティング(ABM)の基本の考え方に、「ファネルをひっくり返す」ことがあります。マーケティングからリードを渡すのではなく、営業がどれくらいのリードを営業活動でさばけるか(吸収できるか)によって引き渡すリードの質と量をコントロールする、つまり営業がリードを「受け取る」方法のマネジメントで活動を設計するという考え方です。
解決策:ファネルのKPIは営業側からコントロールする
全ての活動のゴールは成約を獲得することですが、営業部門においては限られた人数で、固定費でもある営業人員を最適なパフォーマンスで稼働させることが、全体のパフォーマンスを上げるポイントとなります。そのためには、SQL(Sales Qualified Lead:営業部門に引き渡す見込顧客)の量と質を後工程の稼働状況に合わせてコントロールすることが有効になります(図3)。
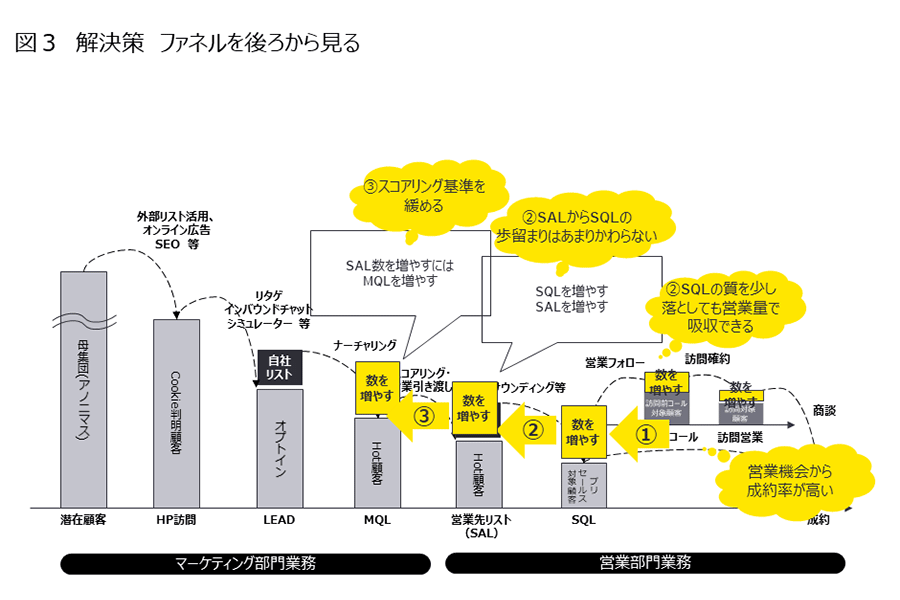
図3:ファネルを後ろから見る
例えば、商談からの成約率が高い場合、同じ営業工数(営業スタッフの稼働時間)であれば、もっと多くのプレコールや訪問ができるため、SQLを増やす余力が生まれます。つまり、今の評価基準を緩めてSQL数を増やすことになります。それは、SAL(Sales Accepted Lead:営業部門がアプローチすると判断した顧客)を増やし、MQL(Marketing Qualified Lead:マーケティング部門が創出する見込顧客)からの基準を緩めることにつながります。ファネルの一つ手前の数と質をどうコントロールするかは、後工程側である営業の処理能力や余力によって決まります。
逆に商談からの成約率が低いのであれば、当然営業現場では商談回数や時間を増加させることが必要となり、営業が持つSQL、ひいてはSAL・MQLは減らしてよいことになります。それは、マーケティング側にとっては、ナーチャリングに時間をかけ、スコアリングの閾(しきい)値を高め、営業への引き渡し数を減らし、リードの質を上げるという判断へとつながります。
営業という「資産」の稼働を最適化し、ファネル全体のパフォーマンスを最大化するには、「ファネルを後ろから見る」ことが有効とイメージしやすくなったのではないでしょうか。
(2) マーケティング/営業部門の分断は、活動目的の違いから発生する
もう一つの問題に目を向けましょう。マーケティング活動において、特にデジタルアドを出稿している場合、ストーリーを多少逸脱しても反応の良さでコンテンツやクリエーティブをチューニングしがちです(図4:マーケティング部門業務)。ただ、これにより顧客が改めて営業から話を聞いた際に「思っていたものと違う」という期待値とのギャップが生まれ、営業にとっては適当な説明をして質の悪いリードを大量生産していると感じることがあります。
一方で営業も、同じ商材でも価格や機能などの条件を変化したり、もともと想定していた商材と異なる商材や自社商材と連携可能な外部の商材を組み合わせたり、買い手の立場に立った踏み込んだ提案をするためにストーリーを組み換え、商談獲得や成約の割合や獲得コストを上げるチューニングを行います(図4の「営業部門業務」参照)。
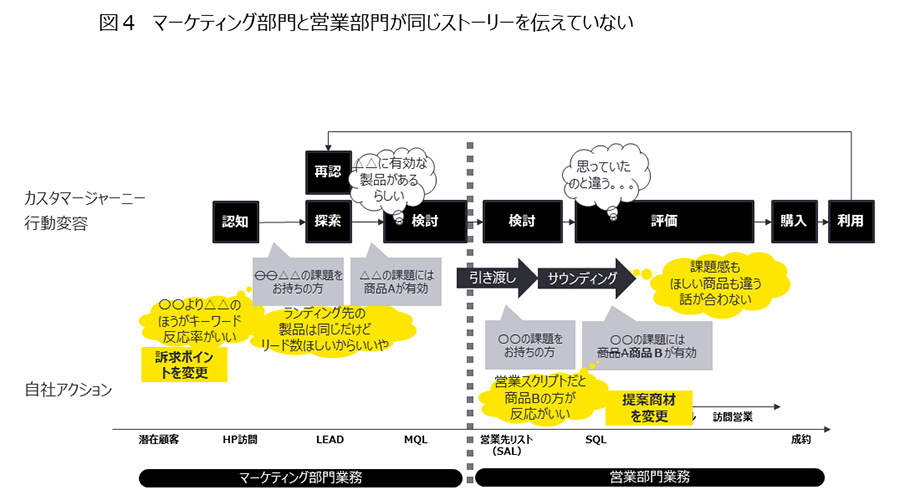
図4:マーケティング部門と営業部門が同じストーリーを伝えていない
つまり、当初のストーリーから提示課題と解決方法(商材など)を週次や極論日次で変えていくのですが、このいい意味で柔軟な変化をマーケティング側でのコンテンツ繁栄に求めることは、素材準備やシナリオ改修にかかる時間やコストからなかなか難しいです。マーケティングと営業はそれぞれのゴールに最適な形でストーリー変更を行うため、結果として顧客が受け取るストーリーに一貫性がなくなることがあります。
解決策:一貫性のある顧客のストーリー体験の実現
しかし、マーケティングと営業の訴求内容やコンテンツが異なり、顧客がそれぞれから受け取る情報や提案が異なることは避けなければなりません。
そこでマーケティング側は、営業側のストーリーに合わせ、営業部門側の顧客像(ターゲットペルソナ)と営業スクリプトを踏まえてカスタマージャーニー像を書き直し(TOBE像)つつ、一連の体験の起点となるコンテンツを提供する、というプロセスを進めます(図5)。
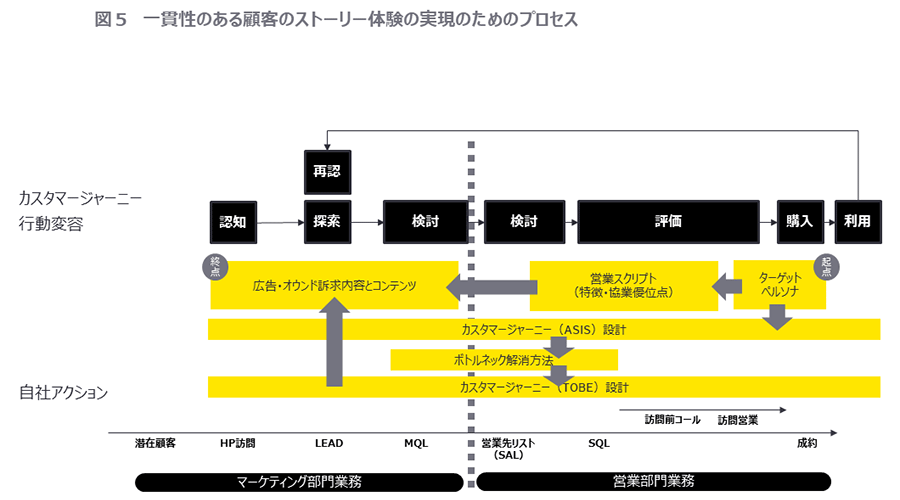
図5:一貫性のあるストーリー体験を実現するプロセス
ここでのポイントは、課題や訴求メッセージ、提案する商材のコンテンツをモジュール化し、順番や課題と商材の組み合わせなど、ストーリーを組み替えやすくしておくことです。運用において営業スクリプトやツールの修正に合わせ、マーケティング部門では広告やオウンドメディアの訴求内容とコンテンツを修正し、顧客が同じストーリーに触れるようにします。
営業側の実態を把握するためにも、マーケティング部門の担当者も最低限月次、できれば週次の営業会議に参加し、実態を把握することが望ましく、その頻度で図5のプロセスを回せばストーリーのずれはかなり解消できるでしょう。
4. まとめ
営業偏重組織から営業DXを行う際において、マーケティングや営業支援ツールの導入だけでなく、マーケティング組織を構築したり、ファネルのパフォーマンスを管理したりするようになったことで、顕在化したボトルネックを解消する手を打たないと、ツールの導入が逆にパフォーマンスの低下と組織間の確執を生みかねないと分かってもらえたかと思います。
そのために、成約に向けたスループットをファネルの後ろからコントロールし、営業とマーケティングにおける訴求とコンテンツを統一することが必要となります。
これらは理論上設計はできますが、実現することは難易度が高いため、ツールベンダーなどに導入前提で相談するより、ツールにかかわらず営業変革をどのように行うか、また発生し得るボトルネックをいかに解消するか、という設計から始めることをお勧めします。導入するデジタルツールの効果をさらに向上させる取り組みとして、まずは現状を見直してみてはいかがでしょうか?




