EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

サステナビリティ開示基準(SSBJ基準)のうち、サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」及びサステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」の概要や開示要求事項など、企業の開示実務に影響を与える重要な点を中心に解説します。
本稿の執筆者
EY新日本有限責任監査法人 サステナビリティ開示推進室 兼 品質管理本部 会計監理部 公認会計士 サステナビリティ情報審査人 岡本 裕二
国内事業会社の財務諸表監査業務に加え、会計処理及び開示に関して相談を受ける業務に従事。また、2021~24年の間、財務省関東財務局理財部統括証券監査官に在籍し、企業情報の開示充実に向けた有価証券報告書レビュー業務に携わる。
要点
- 適用基準は、SSBJ基準に準拠したサステナビリティ関連財務開示を作成し、報告する場合における基本となる事項を定めた基準であり、SSBJ基準の適用において必ず適用しなければならない基準である。
- 一般基準は、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報について、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標及び目標の4つの構成要素で開示することを求めている。
- SSBJ基準においてテーマ別基準が存在しない場合、一般基準に従って具体的なサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報の開示が行われることになる。
Ⅰ はじめに
本稿では、2025年3月にサステナビリティ基準委員会(以下、SSBJ)から公表されたサステナビリティ開示基準(以下、SSBJ基準)のうち、サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」(以下、適用基準)及びサステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」(以下、一般基準)の概要や開示要求事項など、企業の開示実務に影響を与える重要な点を中心に解説します。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添えます。
Ⅱ 適用基準の概要及び主な開示要求事項
1. 目的及び範囲
適用基準は、SSBJ基準に準拠したサステナビリティ関連財務開示を作成し、報告する場合において、基本となる事項を示すことを目的としています。そして、SSBJが公表するサステナビリティ開示基準に従ってサステナビリティ関連財務開示を作成し報告するにあたり、適用しなければならない基準となります。なお、SSBJ基準に準拠している旨を表明するためには、すべてのSSBJ基準を適用しなければならない点に留意が必要となります(適用基準BC14項)。
また、SSBJ基準は、金融商品取引法の枠組みにおいて、特にプライム上場企業が適用することを想定して開発が行われています。しかし、プライム上場企業以外の企業がSSBJ基準に従いサステナビリティ関連財務開示を作成することを奨励すべきとの考えから、プライム上場企業以外の企業も適用することができます。なお、金融商品取引法に基づく有価証券報告書におけるSSBJ基準の適用対象企業及び適用時期等については、金融庁が金融審議会に設置した「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の検討に基づき、金融庁が法令において定めることが想定されますが、現時点ではまだ法令において定められていません。
2. 報告企業
適用基準は、財務諸表の作成を要求される又はこれを選択する企業を報告企業と定義しており(適用基準第4項(1))、サステナビリティ関連財務開示は、関連する財務諸表と同じ報告企業に関するものでなければならず、報告企業が連結財務諸表を作成している場合、親会社及びその子会社のサステナビリティ関連のリスク及び機会が理解できるものでなければなりません(適用基準第5項、第6項)。従って、サステナビリティ関連財務開示として開示するサステナビリティ関連のリスク及び機会は、連結財務諸表に含まれる子会社の範囲と整合的である必要があると考えられます。
3. 報告期間と報告のタイミング
サステナビリティ関連財務開示は、原則として、関連する財務諸表と同じ報告期間を対象とし、同時に報告しなければなりません(適用基準第67項、第68項)。連結財務諸表を日本基準で作成している場合、親会社の財務情報の報告期間と子会社等の財務報告期間が異なる場合があります。この場合、サステナビリティ関連財務開示に取り込まれる親会社及び子会社等のサステナビリティ関連財務情報の報告期間は、それぞれの財務情報の報告期間と同じ期間が対象になると考えられます。
また、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関連する指標として、企業が活動する法域の法令の要請により報告することが要求されている指標を用いることを選択する場合があると考えられます。この場合、当該法令において定められている指標の報告のための算定期間が、サステナビリティ関連財務開示(及び関連する財務諸表)の報告期間と異なる場合もあると考えられますが、この場合においてもサステナビリティ関連財務開示(及び関連する財務諸表)の報告期間を対象として開示する必要があると考えられます。
4. 情報の記載場所
サステナビリティ関連財務開示は、関連する財務諸表に含まれる情報を補足し、補完するものであると考えられており、サステナビリティ関連財務開示は、原則として、関連する財務諸表とあわせて開示しなければなりません。しかし、SSBJ基準は、関連する財務諸表の会計基準を問わず適用できるとしていることから、主要な利用者がサステナビリティ関連財務開示を理解するためには、関連する財務諸表を作成するにあたり準拠した会計基準を理解する必要があると考えられます。このため、サステナビリティ関連財務開示は、関連する財務諸表を特定できるようにしなければなりません(適用基準第7項)。
この点、サステナビリティ関連財務開示が関連する財務諸表と同じ文書において報告されている場合は、関連する財務諸表の作成にあたり準拠した会計基準は開示されているものと考えられますが、サステナビリティ関連財務開示は、関連する財務諸表と同じ文書において報告されない場合も考えられます。このため、サステナビリティ関連財務開示と同じ文書において関連する財務諸表が報告されない場合には、「関連する財務情報の入手方法」と「関連する財務諸表の作成にあたり準拠した会計基準の名称」を開示しなければならないとされています(適用基準第7項)。
5. リスク及び機会の情報の開示
適用基準では、サステナビリティ関連財務開示を行う際に、企業は①企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会の識別、②バリュー・チェーンの範囲の決定、③識別した当該リスク及び機会に関する重要性がある情報の識別をしなければならないとされています(適用基準第35項)。
(1) リスク及び機会の識別
適用基準では、サステナビリティ関連のリスク及び機会の識別にあたり、参照するガイダンスの種類を「ガイダンスの情報源」として定めています。「ガイダンスの情報源」は「適用しなければならない」情報源、「参照し、その適用可能性を考慮しなければならない」情報源、「参照し、その適用可能性を考慮することができる」情報源に分類し、企業はこの「ガイダンスの情報源」の定めに従ってサステナビリティ関連のリスク及び機会を識別することになります(適用基準第37項)。
また、「適用しなければならない」情報源としてSSBJ基準を定めており(適用基準第40項)、「参照し、その適用可能性を考慮しなければならない」情報源としてIFRS財団が公表する「SASBスタンダード」(2023年12月最終改訂)における開示トピックを定めています(適用基準第41項)。そして、「参照し、その適用可能性を考慮することができる」情報源として、国際サステナビリティ基準審議会(以下、ISSB)が公表するIFRSサステナビリティ開示基準(以下、ISSB基準)及び付属するガイダンスやIFRS財団が公表する「水関連開示のためのCDSBフレームワーク適用ガイダンス」及び「生物多様性関連開示のためのCDSBフレームワーク適用ガイダンス」(以下、あわせて「CDSBフレームワーク適用ガイダンス」)、主要な利用者の情報ニーズを満たすように要求事項が設計されている他の基準設定主体による直近の公表文書や同じ産業又は地理的地域において事業を営む企業によって識別されたサステナビリティ関連のリスク及び機会を定めています(適用基準第43項)。
(2) バリュー・チェーンの範囲の決定
識別したサステナビリティ関連のリスク及び機会のそれぞれに関連して、バリュー・チェーンの範囲を決定しなければなりません(適用基準第46項)。適用基準では、バリュー・チェーンを、報告企業のビジネス・モデル及び当該企業が事業を営む外部環境に関連する、相互作用、資源及び関係のすべてをいうとしており(適用基準第4項(12))、バリュー・チェーンには、製品又はサービスの構想から提供、消費及び終了まで、企業が利用し依存する人的資源関係や材料及びサービスの調達、製品及びサービスの販売及び配送などや企業が事業を営む財務的環境、地理的環境、地政学的環境及び統制環境が含まれると考えられます。
(3) 重要性がある情報の識別
企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会に関して、重要性がある情報を開示しなければなりません(適用基準第48項)。そのためには、識別したサステナビリティ関連のリスク又は機会に関する重要性がある情報を識別しなければなりません(適用基準第49項)。この重要性がある情報の識別の判断は、サステナビリティ関連のリスク又は機会に具体的に適用されるSSBJ基準の定めが存在するか否かによって異なります。具体的に適用される定めがSSBJ基準に存在する場合は、該当するSSBJ基準の定めを適用して識別したサステナビリティ関連のリスク又は機会に関する重要性がある情報を識別しなければなりません(適用基準第50項)。一方で、具体的に適用される定めがSSBJ基準に存在しない場合は、主要な利用者の意思決定に関連性がある情報やそのサステナビリティ関連のリスク又は機会を忠実に表現する情報を識別するための判断を行うことになります(適用基準第51項)。
6. つながりのある情報
情報が関連する項目の間のつながり、サステナビリティ関連財務開示内の開示の間のつながり、サステナビリティ関連財務開示とその他の財務報告書の情報との間のつながりを理解できる情報を開示しなければなりません(適用基準第29項)。また、サステナビリティ関連財務開示の作成に用いるデータ及び仮定は、関連する財務諸表の作成にあたり準拠した会計基準を考慮した上で、可能な限り、関連する財務諸表の作成に用いるデータ及び仮定と整合させなければなりません(適用基準第30項)。つながりを理解できる情報の開示についての記載例は当基準上示されていませんが、例えば、サステナビリティ関連財務開示とその他の財務報告書の情報との間のつながりを理解できる情報として、低炭素社会への移行影響に直面する場合があるときに、主要設備の更新投資の可能性や、既存設備の減損等の評価に与える影響について説明することが考えられます。
7. 公表承認日と後発事象
報告期間の末日後、サステナビリティ関連財務開示の公表承認日までに報告期間の末日現在で存在していた状況について情報を入手した場合、新規の情報に照らして当該状況に関連する開示を更新しなければなりません(適用基準第71項)。ここで、サステナビリティ関連財務開示の公表承認日とは、サステナビリティ関連財務開示を公表することを承認する権限を有する社内の機関又は個人が公表を承認した日をいい(適用基準第4項(15))、企業が公表するサステナビリティ関連財務開示について、どの時点までの情報が開示に含まれているか、どの機関又は個人が公表を承認したのかに関する情報を提供することは、主要な利用者がサステナビリティ関連財務開示を理解するために必要な情報であると考えられます。また、一般的には、公表承認日と保証報告書日が同日であることが多いと考えられます。
8. 比較情報
比較情報は企業のパフォーマンスに関するトレンドを把握する上で有用な情報であると考えられることから、適用基準は、報告期間に開示されるすべての数値について、前報告期間に係る比較情報を開示することを求めています。ただし、法令の定めに基づきサステナビリティ開示基準に従った開示を行う場合における当該法令又はサステナビリティ開示基準が、前報告期間に係る比較情報を開示することを禁止しているか、前報告期間に係る比較情報を開示しないことを容認している場合又は任意でサステナビリティ開示基準に従った開示を行う場合には、比較情報を開示しないことができるとされています(適用基準第73項)。
Ⅲ 一般基準の概要及び主な開示要求事項
1. 目的及び範囲
一般基準の目的は、財務報告書の主要な利用者が、企業に資源を提供するかどうかに関する意思決定を行うにあたり有用な、企業のサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報の開示について定めることにあるとされています(一般基準第1項)。一般基準は、SSBJが公表するサステナビリティ開示基準に従ってサステナビリティ関連財務開示を作成し、報告する際に、適用しなければなりません(一般基準第3項)。また、SSBJが公表する他のテーマ別基準が、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報の開示について具体的に定めている場合には、これに従わなければなりません(一般基準第4項)。すなわち、SSBJ基準においてテーマ別基準が存在しない場合には、一般基準に従って具体的なサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報の開示が行われることになります。
2. コア・コンテンツの開示
一般基準では、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報について、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標及び目標の4つの構成要素(コア・コンテンツ)で開示することを求めています(一般基準第7項)。ガバナンスに関する開示は、サステナビリティ関連のリスク及び機会をモニタリングし、管理し、監督するために企業が用いるガバナンスのプロセス、統制及び手続を理解できるようにすることが目的となります(一般基準第8項)。戦略に関する開示は、サステナビリティ関連のリスク及び機会を管理する企業の戦略を理解できるようにすることが目的となります(一般基準第11項)。リスク管理に関する開示は、サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするプロセスを理解すること、企業の全体的なリスク・プロファイル及び全体的なリスク管理プロセスを評価することが目的となります(一般基準第28項)。指標及び目標に関する開示は、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関連する企業のパフォーマンスを理解できるようにすることが目的となります(一般基準第30項)。4つの構成要素における主な開示要求事項は<表1>のとおりです。
表1 4つの構成要素における主な開示要求事項
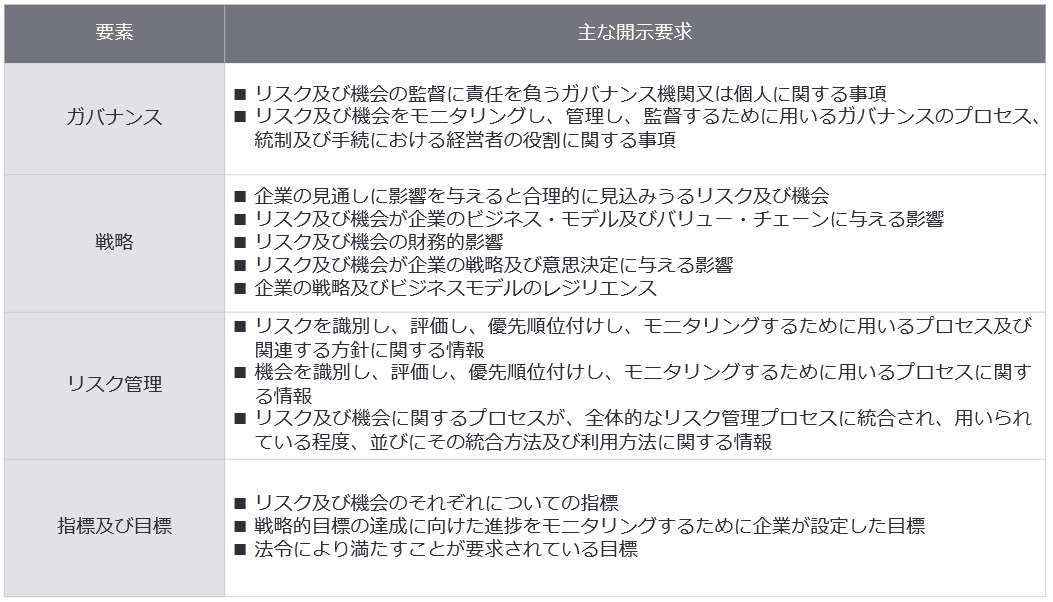
Ⅳ SSBJ基準とISSB基準との整合性
SSBJが公表したSSBJ基準は、SSBJ基準を適用した結果として開示される情報が国際的な比較可能性を大きく損なわせないものとなるようにするため、その基本的な方針として、ISSB基準との整合性を図ることを基礎としています。しかし、SSBJ基準は、一部の定めについて、ISSB基準と異なる定めがあるとともに、ISSB基準に追加した定めもあります。
ここで、SSBJ基準とISSB基準の整合の度合いを理解することを可能とするために、SSBJより「SSBJ基準とISSB基準の差異の一覧」が公表されました。なお、当該差異一覧は、ISSBの母体組織であるIFRS財団においても確認されているものになります。
なお、ISSB基準では、ISSB基準の理解のために、付属ガイダンスや基準に含まれない教育的資料を公表しています。SSBJにおいても、ISSB基準に関する付属ガイダンス及び教育的資料のうち、ISSB基準の適用において参考となるものについて、SSBJ基準の適用においても参考として利用できるようにするため、SSBJより補足文書が公表されています。
Ⅴ おわりに
今後、企業は自社の事業特性や投資家の期待を踏まえて、SSBJ基準に基づく開示の準備を進めることが重要となりますが、現行の企業内容等の開示に関する内閣府令に基づくサステナビリティに関する企業の取組みの開示の充実に向けても、SSBJ基準で示されている内容は参考になると考えられます。
金融商品取引法に基づく有価証券報告書におけるSSBJ基準の適用対象企業及び適用時期等については、今後法令において定められることになりますが、企業価値向上の観点からも、積極的な情報開示を通じてステークホルダーとの対話を深めていくことが期待されます。
サマリー
2025年3月に公表されたSSBJ基準は、ISSB基準との整合性を図りつつ日本企業の実情に配慮した内容となっています。企業は自社の事業特性や投資家の期待を踏まえ、早期に準備を進めることが重要です。原則適用は段階的に行われる見込みですが、企業価値向上の観点からも、積極的な情報開示によるステークホルダーとの対話の深化が期待されます。
関連コンテンツのご紹介
【3月公表!】速報連載第1回 サステナビリティ開示基準(SSBJ基準)を読み解く:概要
2025年3月、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)よりサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)が公表されました。本稿では、SSBJ基準の基本的な構成や特徴、ISSB基準との相違点、適用時期など、企業の開示実務に影響を与える重要ポイントを解説します。
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)から、2025年3月4日に、サステナビリティ開示に関する以下の3つの基準が公表されました。
サステナビリティ情報開示とは、企業が環境、社会、経済の3つの観点から、持続可能な社会の実現に向けて行っている取り組みを報告することです。2023年3月期に内閣府令が改正され、有価証券報告書等でサステナビリティ情報の開示が求められるようになりました。
情報センサー
EYのプロフェッショナルが、国内外の会計、税務、アドバイザリーなど企業の経営や実務に役立つトピックを解説します。







